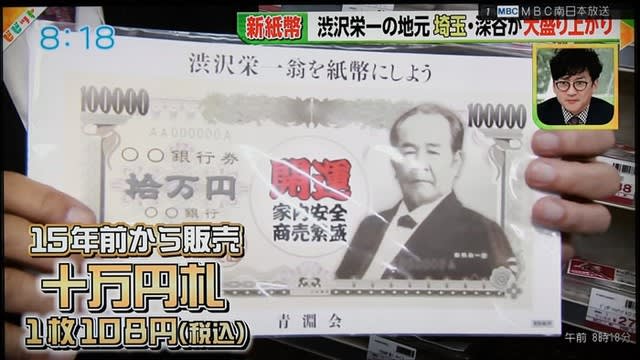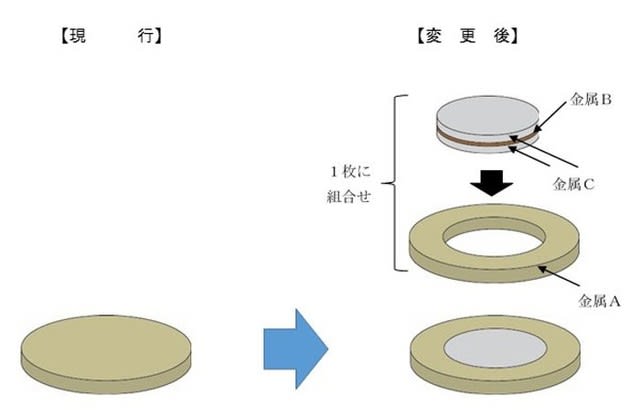4月28日(日)10連休の最中、唐芋(サツマイモ)畝を作りました。
シャリンバイが花盛り 以下の画像は4月28日に撮影

砂山に咲くハマヒルガオ

浜の丸の砂山から 吹上浜日置海岸

吹上浜は初夏の風景となりました。東寄りの風で海は穏やか、所々にキス釣りの人がいました。浜を北側に少し歩き小さな川を過ぎた「浜の丸」の砂山です。
地引網が盛んだった昭和40年代頃まではここに網小屋がありました。浜に戻らず竹林沿いを歩くうちに脇道を100mほど進むと、初めて訪れる古い墓地でした。
竹藪に半ば埋もれていますが今も数基は使われていて、水道がありバケツが置かれていました。合掌し周辺の昔を思い出しました。遠い御先祖に呼ばれたような不思議な体験でした。
実家庭先のツツジが花盛り

白木蓮の枝を切り日差しが功を奏したのか今年は例年になく沢山の花が咲きました。氏神様の周囲を掃除して米と塩、焼酎をお供えし手を合わせました。
砂山の恵比須さん

浜を少し南側へ歩いたところに残る恵比須さんです。左に祭られた石板には海神様などの名前が刻まれており比較的新しい感じです。恵比須さんは戦後のもので風化が進んでいますが、今も笑顔で海を見守っています。貝殻に米と塩を盛り、焼酎をお供えして海の幸をお願いしました。
昨年は猛暑と不漁のため、一度もキス釣りをしませんでした。今年は釣りにも頑張って、食べなれたキスのてんぷらを味わいたいものと神頼みでした。
順調に育つ苦瓜(ゴーヤー)

蔓が小さな竹の支柱をつかんでしっかりと成長しています。風除けのビニルを外して長い支柱を立てる時期が近づきました。この時期は強い風雨にさらされることもあり、茎が折れると成長が大幅に遅れますので様子を見ています。
大根の花も終わりが近い

唐芋の苗が育ってきました。新芽が密集しているので切り取って植え付けないと次の脇芽が伸びず、新たな苗が育ちません。大根の花は終わりに近づき一部は種ができ始めていました。
挿木で育てたアジサイなどを移植

昨年秋に挿木して冬を越したアジサイ、ムクゲ、チロリアンランプ、ツルニチニチソウを畑の隅などに移植しました。アジサイは根元近くからの剪定にも耐えるため野菜作りへの影響は少ないはずです。大きく成長する木はいつの間にか畑を狭めて日当たりを妨げるので植える場所には注意が必要です。
唐芋苗を準備

草取り、大根の撤去、えんどう豆の収穫後にアジサイなどを移植。17時を回っていましたが唐芋の畝つくりに着手しました。鹿児島市の最高気温は21.7度、南東風が吹きあまり汗も流れません。鍬を持つ手は軽く作業が捗りました。18時半までかかって予定の倍以上の7列を作りました。
4月19日に三又で耕した後の雨量が少ないため、まだ土の塊がほぐれていません。もう少し雨に当てて畝の形を整え、マルチシートを張って唐芋を植付ける予定です。
ミカンの花も終わり

心地良い香りを届けてくれたミカンの花も終わりに近づいています。これほどの花が咲いたのは初めて、今度こそ実が付くことでしょう。予定よりも作業が進み満足感を胸に45分ほどの夜道を帰途につきました。
シャリンバイが花盛り 以下の画像は4月28日に撮影

砂山に咲くハマヒルガオ

浜の丸の砂山から 吹上浜日置海岸

吹上浜は初夏の風景となりました。東寄りの風で海は穏やか、所々にキス釣りの人がいました。浜を北側に少し歩き小さな川を過ぎた「浜の丸」の砂山です。
地引網が盛んだった昭和40年代頃まではここに網小屋がありました。浜に戻らず竹林沿いを歩くうちに脇道を100mほど進むと、初めて訪れる古い墓地でした。
竹藪に半ば埋もれていますが今も数基は使われていて、水道がありバケツが置かれていました。合掌し周辺の昔を思い出しました。遠い御先祖に呼ばれたような不思議な体験でした。
実家庭先のツツジが花盛り

白木蓮の枝を切り日差しが功を奏したのか今年は例年になく沢山の花が咲きました。氏神様の周囲を掃除して米と塩、焼酎をお供えし手を合わせました。
砂山の恵比須さん

浜を少し南側へ歩いたところに残る恵比須さんです。左に祭られた石板には海神様などの名前が刻まれており比較的新しい感じです。恵比須さんは戦後のもので風化が進んでいますが、今も笑顔で海を見守っています。貝殻に米と塩を盛り、焼酎をお供えして海の幸をお願いしました。
昨年は猛暑と不漁のため、一度もキス釣りをしませんでした。今年は釣りにも頑張って、食べなれたキスのてんぷらを味わいたいものと神頼みでした。
順調に育つ苦瓜(ゴーヤー)

蔓が小さな竹の支柱をつかんでしっかりと成長しています。風除けのビニルを外して長い支柱を立てる時期が近づきました。この時期は強い風雨にさらされることもあり、茎が折れると成長が大幅に遅れますので様子を見ています。
大根の花も終わりが近い

唐芋の苗が育ってきました。新芽が密集しているので切り取って植え付けないと次の脇芽が伸びず、新たな苗が育ちません。大根の花は終わりに近づき一部は種ができ始めていました。
挿木で育てたアジサイなどを移植

昨年秋に挿木して冬を越したアジサイ、ムクゲ、チロリアンランプ、ツルニチニチソウを畑の隅などに移植しました。アジサイは根元近くからの剪定にも耐えるため野菜作りへの影響は少ないはずです。大きく成長する木はいつの間にか畑を狭めて日当たりを妨げるので植える場所には注意が必要です。
唐芋苗を準備

草取り、大根の撤去、えんどう豆の収穫後にアジサイなどを移植。17時を回っていましたが唐芋の畝つくりに着手しました。鹿児島市の最高気温は21.7度、南東風が吹きあまり汗も流れません。鍬を持つ手は軽く作業が捗りました。18時半までかかって予定の倍以上の7列を作りました。
4月19日に三又で耕した後の雨量が少ないため、まだ土の塊がほぐれていません。もう少し雨に当てて畝の形を整え、マルチシートを張って唐芋を植付ける予定です。
ミカンの花も終わり

心地良い香りを届けてくれたミカンの花も終わりに近づいています。これほどの花が咲いたのは初めて、今度こそ実が付くことでしょう。予定よりも作業が進み満足感を胸に45分ほどの夜道を帰途につきました。