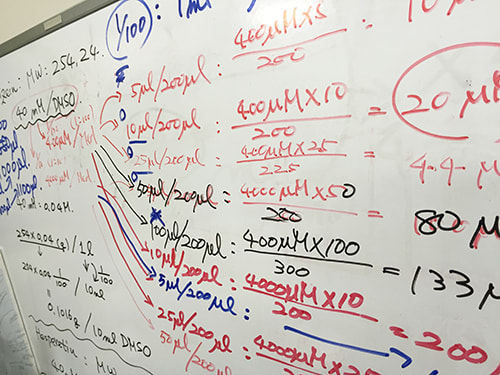今日は寒くなかったけどなー。
gooニュース
全国的に雨日本海側を中心に強く降る所も
あす17日は今季一番の寒気流入 北海道は平地も初雪か 西日本の暑さも収まる (tenki.jp)
来週中頃は早くも次の寒気
北日本は荒天のおそれも(ウェザーニュース)
明日は今日よりも10度以上気温が下がるらしい。
久々に司馬遼太郎を読みました。
夏草の賦
四国を平定した長曾我部元親の物語です。まあ、四国平定してもあっという間に秀吉に屈して土佐一国に戻されちまいますが・・・・
物語の始まりは、彼ではなく彼の嫁さん。斎藤利三の妹、菜々です。斎藤利三といえば明智光秀の第一の家臣で、後に徳川家で大奥の基礎を作った春日局のお父ちゃんです。逆臣光秀の家臣の娘お福がなんで徳川家に雇われたかというと、家康が孫の乳母を公募したんで夫の稲葉正成を捨てて応募したら採用されたという命知らずな女傑であります。菜々は彼女の叔母にあたります。司馬遼太郎は、「この家の女系には思いきった性格の血が流れているのかもしれない」と記述しています。美濃から流刑地、鬼国とされる土佐へお嫁に行くのはすごい思い切りです。当時の長曽我部はまだ土佐を平定してなかった。一郡の領主でしかなかった。まあ、その状況で美濃の織田の重臣から姫を娶ろうとしたんだから長曾我部元親の慧眼もすごい。織田家はやっとこさ美濃に進出して岐阜城を作ったとこだった。四国を平らげた後は、大勢力となった織田家とことを構える可能性があるという考えだったのでしょう。彼の読みは毛利でも三好でもなく織田だった。
元親が一両具足という国民皆兵のシステムを作った理由は、土佐が陸の孤島で阿波や伊予へ進攻するときに圧倒的に兵が足りなかったから。ただ、土佐は背後が太平洋でどこからも襲われない。だから、民を全部兵にして阿波と伊予へ同時進攻した。土佐を空っぽにして。おかげで、農民の三男や四男でも手柄を立てて出世するチャンスが生まれたし、農民であっても戦に出るため土佐を自分の国として考える思考が生まれた。これが長曽我部が没落後に山内氏が入った後も続き、上士(山内侍)・下士(長曽我部侍)の二重構造が生まれ、幕末には下士層に志士が多数育った。商人であり下士の家で坂本龍馬のような人が育ったのは偶然ではない。
戊辰戦争で東北に侵攻した際に官軍の土佐軍を指揮していた乾退助(板垣退助)が、東北の農民が自分の国の侍が蹂躙されるのを安全なところで他人事のように眺めているのを見て、「これではいかん」と退助が憤慨したのもしょうがないことであります。東北は東北で武家と庶民の階層がかけ離れていた。国民全部を兵にする土佐や当時の長州とは気質が違う。
歴史もの小説は結末がわかってる。主人公の晩年がどう描かれるかが興味の一つです。
秀吉に屈した元親は人が変わったようにやる気をなくしてそのまま長曽我部を没落させてしまう。これは山内容堂が、鳥羽伏見の戦いの後、江戸に向かって侵攻する官軍に参加した土佐軍を見送って以降、完全にやる気をなくし、東京で買った徳川家の別邸で酒と女で土佐二十四万石の財産を全部飲み尽くし45歳で亡くなったことと同じ。土佐男の気質そのもので、燃え尽きたらサクッとやめてしまう。
ちなみに光秀による本能寺の変は長曽我部の陰謀の説がありますが、司馬遼太郎氏が存命の時代の後の現代、元親は信長の命に応じて伊予、阿波、讃岐を放棄することに同意していて、そのことを光秀は知らなかったことが定説になっています。元親はギブアップしていたんですね。夏草の賦では元親は徹底抗戦となってます。ただ、元親のギブアップを四国方面を担当していた(と自分は思っていた)光秀は知らなかった。まあ、光秀のおかげで信長は消え、元親による四国平定はなりました。秀吉に潰されますが・・・・戦うこともなく。
本日のお酒:SUNTORY THE PREMIUM MALT'S ダイヤモンドホップの恵み + 梵 純米大吟醸 氷温熟成 磨き三割八分