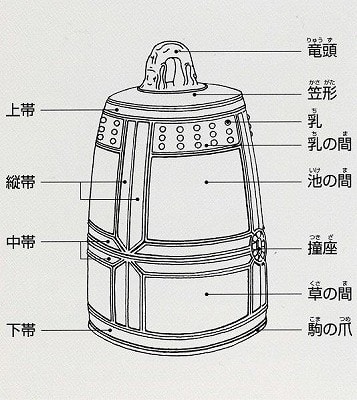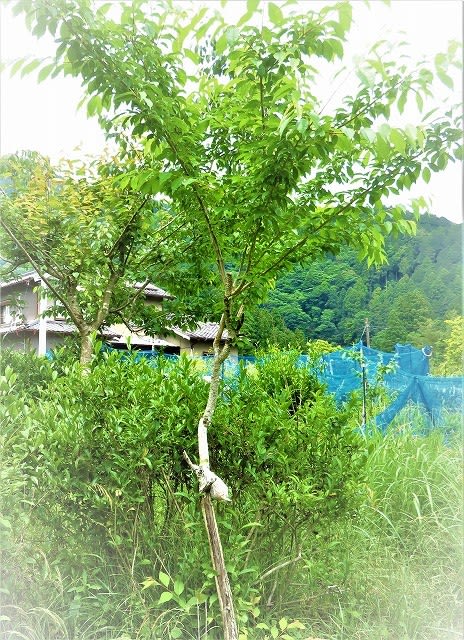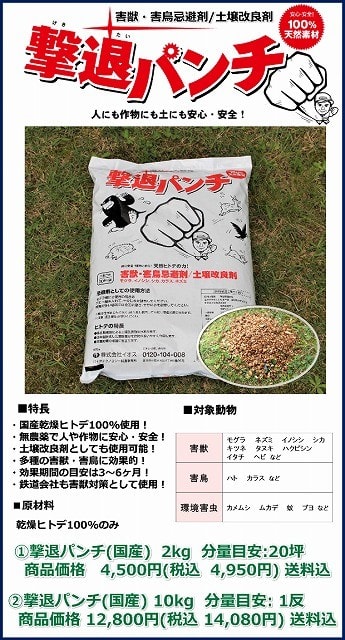ほぼ毎朝のように飲んでいた「野菜ジュース」で活躍していたジューサーがいろいろガタがきたので新しく変えることになった。今までのはシャープ製の中古品だったが、今回は韓国製「クビングス(kuvings)」のジューサーにしてみた。その理由の一つは、高速回転するジューサーはその摩擦熱で酵素がジュースに混入してしまい酸化するので、低速回転でしかも早くジュースができるジューサーにしてみたいということだ。

さらに、従来のジュースづくりは、野菜や果物を小さく切らなければならなかったり、部品の掃除も面倒だったり、忙しい朝としては時間や労力がかかるなどの課題があった。そこで、価格が3~4倍はしたが思い切って低速で強力なジューサーを導入することとなった。ほんとうは日本製にしたいところだが、今回選んだ韓国製のほうが技術的にすすんでいる気がしたのだった。


野菜や果物は大まかに切ればあっという間にジュースになったのにはしばし感嘆するばかり。今まではジューサーが動いている間にいろいろ朝食や洗濯の準備ができていたが、今回はそんな余裕?もなくジュースができてしまう。この点では日本製でもよかったが、後片付けの洗浄に手間がかかる「ストレーナー」の網の部分を掃除する「回転洗浄ブラシ」という新兵器?にびっくり。ジューサーへの愛情と技術的工夫への心意気が感じられる。

最近のジュースの色が見事だった。黄色は黄色いパブリカやミカン、緑色は甘長トウガラシ・キャベツ・キウイ、赤っぽいピンクは冷凍していたブルーベリーやニンジン、白色はトウガン・リンゴなどが反映されていた。季節によっては旬の野菜や果物が投入されるので色合いも違ってくる。もちろん、自家製の野菜や果物が主流で、近隣からいただいた野菜・果物も添えられる。そこに、酢・梅肉エキス・カボスなどで味を調整する。甘味と酸味とのバランスを図るが毎回味が微妙に違うのが楽しみとなっている。市販するとしたら一杯1000円はどうかと胸を張る??