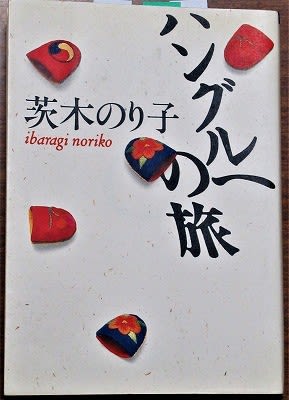25日のクリスマスの日に食べようと思っていたローストチキンをプレ大晦日にやっと食べる。年内にやることが次々出てきてしまってどんどんクリスマスが遠のいてしまった。といっても、クリスチャンではないのでクリスマスにはこだわらない。七輪の上に香草焼きのスパイスをまぶしたチキンをアルミホイルで包んで乗せる。

芯までローストするには弱火でゆっくり焼いていくつもりで時間をかける。それでも、焼き過ぎたようでスパイスは焦げて皮はアルミにくっついてしまった。そのため、味が十分滲みこまないものとなってしまった。やっぱり、酒・味醂・砂糖・醤油・ガラスープの素をブレンドした液にしっかり漬け込むべきだったかもしれない。
ついでに、いつものようにイワシも焼いていく。 静かな大晦日はもちろんのことだが、ふだんから人に会うこと自体少ないのだから、コロナがあろうがなかろうが、隔離生活には変わらない。

先日、集落の小さな集まりのとき、おじさんたちは嘆く。「最近の<紅白>はつまらない。演出が派手なだけで演歌も肩身が狭い」「そうだよな、テレビを見ててもバラエティーやお笑いそれにグルメばっかり」の声に一同笑って共感する。ほんとに、心が洗われる番組はない。もっぱら、取りためた録画を見るほかない。
コロナに翻弄された一年だった。世界は一極集中社会にシフトされている。だから当然格差も出てくる。林業では暮らしていけない、農業では暮らしていけない、田舎では暮らしていけない、マスメディアに脳髄を吸い取られている、そういう人間の基本的な暮しが破壊されている。それを許してしまってきた隙間にコロナが発生した。コロナは人類に日本に問いかけしているのだ。「このままの状態は本当にいいのでしょうか。生きる原点に戻りましょうよ。」と。新年はその答えを出していく実行の年となる。