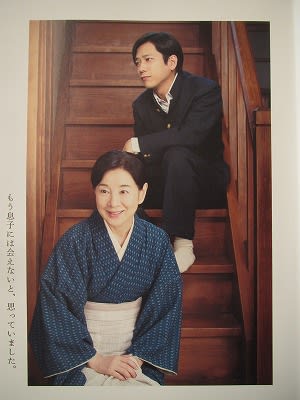収穫したショウガをスライスして天日干ししたり、乾燥機に入れたりして、ショウガチップができていく。
ここまでするのが結構な手間がかかる。

それを「ミルサー」に入れて、粉にしていく。
大量にはできないので、少しづつ作っていく。
和宮様の忍耐力が発揮される。


ミルサーでできた粉はまだ粗いので、目の細かい茶漉しでさらに小さい粉を作る。
粉が舞うのでくしゃみに注意しなければならない。
消毒した空き瓶に完成した粉ショウガを入れていく。

大量にあったショウガを粉にすると「こんなものか」と思うほど少なく見える。
店で粉ショウガを買うとなると結構な値段がするが、手間を考えると納得する。
なんとか、年内にショウガを粉にすることができた。
ひとりでやりきった和宮様にまたまた平身低頭がしばらく続く。
< 伊勢谷友介『社会彫刻』より >
「70億人が日本人と同じ生活をすると、地球は2.4個必要だという。
すでに破綻している我々の生活。
ただ、現在のテクノロジーと古(イニシエ)からの知恵を総動員すれば、人類が地球に生き 残れる循環はつくれる。
利他的な人間の数が増えることは、種として一つの大きな進化になる。」
ここまでするのが結構な手間がかかる。

それを「ミルサー」に入れて、粉にしていく。
大量にはできないので、少しづつ作っていく。
和宮様の忍耐力が発揮される。


ミルサーでできた粉はまだ粗いので、目の細かい茶漉しでさらに小さい粉を作る。
粉が舞うのでくしゃみに注意しなければならない。
消毒した空き瓶に完成した粉ショウガを入れていく。

大量にあったショウガを粉にすると「こんなものか」と思うほど少なく見える。
店で粉ショウガを買うとなると結構な値段がするが、手間を考えると納得する。
なんとか、年内にショウガを粉にすることができた。
ひとりでやりきった和宮様にまたまた平身低頭がしばらく続く。
< 伊勢谷友介『社会彫刻』より >
「70億人が日本人と同じ生活をすると、地球は2.4個必要だという。
すでに破綻している我々の生活。
ただ、現在のテクノロジーと古(イニシエ)からの知恵を総動員すれば、人類が地球に生き 残れる循環はつくれる。
利他的な人間の数が増えることは、種として一つの大きな進化になる。」





















 先日、スーパーでこけしニンジンに、イエローニンジンを買ってきた。
先日、スーパーでこけしニンジンに、イエローニンジンを買ってきた。







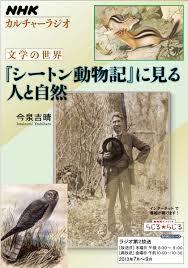 ( 画像はネットから )
( 画像はネットから )