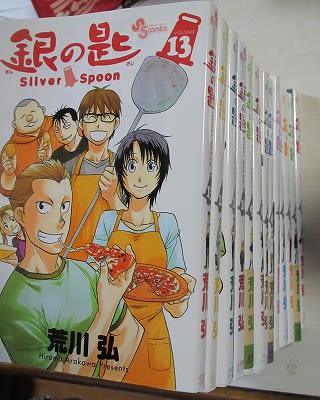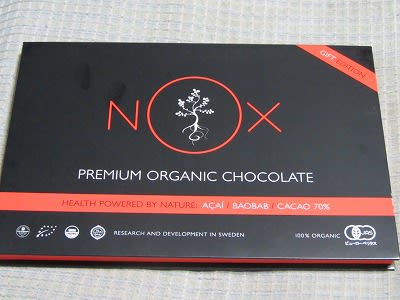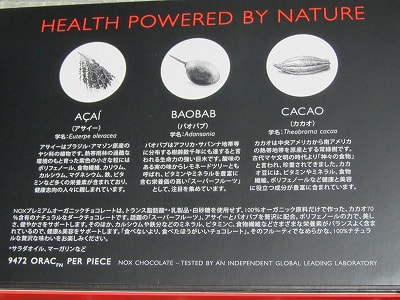『銀の匙』と聞いて思い浮かんだのが、中勘助の代表小説『銀の匙』のこと。
中身はすっかり忘れたが、某有名進学塾の国語の先生が1年間かけてこれを教材にしたという。
さて、家から逃げ出すように大蝦夷農業高校(エゾノー)に入学した主人公「八軒勇吾」に、校長は語る。
●「逃げたことを卑下しないで それをプラスに変えてこそ、逃げた甲斐があるというものです。」(4巻)
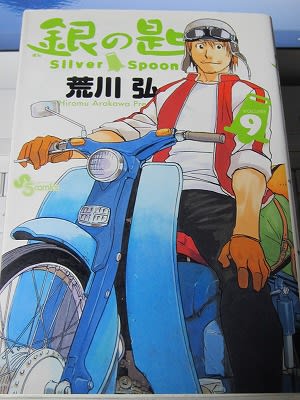
そこには、素敵な人生の先輩がいる。
たとえば獣医の先生が語る。
●「どんなことでもね、叶うにしろ 叶わないにしろ…
夢を持つということは、同時に現実と闘うことになるのを 覚悟することだと思うよ。」(1巻)
この言葉は、作者荒川弘の作画姿勢でもある。

巻末には次号の宣伝コピーが書かれているが、その文章が優れている。
●「人はどこから来て、どこへ行くのか… 八軒は自分のルーツに向き合う。
逃げたことは間違いじゃない。
人生の道順は、一方通行なんかじゃない。
それを教えてもらったから、変われたんだ。
今の自分は、嫌いじゃない。(8巻)

●「夢が散った。
近くで見ていたからわかる。
あいつの悔しさも、あいつの虚しさも…
自分の出る幕じゃないことは 重々承知。
それでもここは引けないんだ。
少年の中に宿る決意…
そしてまた季節はめぐる。
北海道の冬は、どこよりも厳しい…」(7巻)

●「誰よりも頑張った。
それでも報われないこともある。
理不尽を受け入れなければいけないこともある。
でも、きっと誰かが見てくれている。
この世の中、けっこう捨てたもんじゃない。
八軒には、そんな誰かが エゾノーにいる。」(6巻)
マンガそのものは面白おかしく描かれているが、根底には以上のような思い入れが貫通している。
中身はすっかり忘れたが、某有名進学塾の国語の先生が1年間かけてこれを教材にしたという。
さて、家から逃げ出すように大蝦夷農業高校(エゾノー)に入学した主人公「八軒勇吾」に、校長は語る。
●「逃げたことを卑下しないで それをプラスに変えてこそ、逃げた甲斐があるというものです。」(4巻)
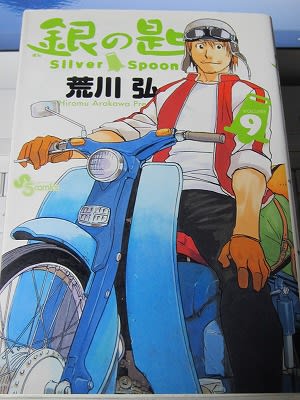
そこには、素敵な人生の先輩がいる。
たとえば獣医の先生が語る。
●「どんなことでもね、叶うにしろ 叶わないにしろ…
夢を持つということは、同時に現実と闘うことになるのを 覚悟することだと思うよ。」(1巻)
この言葉は、作者荒川弘の作画姿勢でもある。

巻末には次号の宣伝コピーが書かれているが、その文章が優れている。
●「人はどこから来て、どこへ行くのか… 八軒は自分のルーツに向き合う。
逃げたことは間違いじゃない。
人生の道順は、一方通行なんかじゃない。
それを教えてもらったから、変われたんだ。
今の自分は、嫌いじゃない。(8巻)

●「夢が散った。
近くで見ていたからわかる。
あいつの悔しさも、あいつの虚しさも…
自分の出る幕じゃないことは 重々承知。
それでもここは引けないんだ。
少年の中に宿る決意…
そしてまた季節はめぐる。
北海道の冬は、どこよりも厳しい…」(7巻)

●「誰よりも頑張った。
それでも報われないこともある。
理不尽を受け入れなければいけないこともある。
でも、きっと誰かが見てくれている。
この世の中、けっこう捨てたもんじゃない。
八軒には、そんな誰かが エゾノーにいる。」(6巻)
マンガそのものは面白おかしく描かれているが、根底には以上のような思い入れが貫通している。