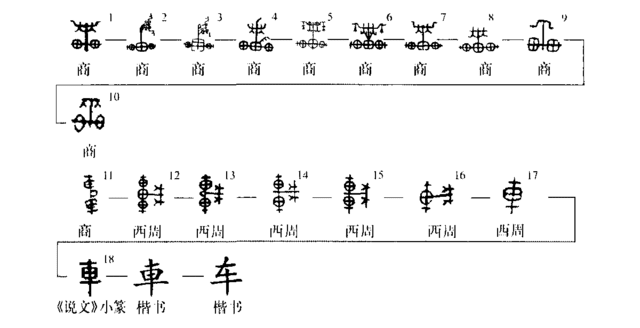今年は玄関横の道で例年以上にイチゴが実ってくれた。このところ、毎日のように口に入ってくる。なにしろ、親元の植木鉢から出るイチゴは少なくて、そこから道沿いにはみ出た所で実をつけるという無頼のイチゴなのだった。小粒ながらそこそこ甘味がある。

野生のイチゴを甘く栽培したのは、なんと世界を制覇していた17~18世紀のオランダだった。チリ産のチリ種と北米産のバージニア種をかけあわせたものだ。それが観賞用として江戸の長崎に伝わったが、本格的にはフランスから導入されその基礎の上に、戦後、アメリカからの「ダナー」種が全国に広まる。1880年代には東の「女峰」、西の「豊の香」の二大品種が全生産量の9割を独占するに至る。

2000年代は開発競争の戦国時代となり、栃木の「とちおとめ」が首位につく。日本の生食の消費量は世界一だという。しかしながら、買うには高値の華だ。だから、赤貧の我が家が買うとすれば半値になった時を狙うしかない。
路地のイチゴ栽培はボーッとしているとアリに食べられてしまう。実が地面についていると食べられてしまう確率が高い。そのため実の下あたりに網を配置してみると多少の効果はあるようだ。

だから、わが家では深紅のイチゴになる前に収穫するしかない。したがって、甘味は今一つで、大きさも小粒になってしまう。しかし、それでも今年が豊作なのは、はみ出た無頼のイチゴの苗の道沿いに少々の肥料を撒いていたのが良かったようだ。鉢の中にも肥料を撒いたが戦果はあまり芳しくなかったのが意外。イチゴがはみ出た所はふだん歩いている玄関前の固い道。耕さないで放置したままのぐーたらイチゴはオイラの性格にぴったり。なにしろ、畑でのイチゴ栽培は失敗続きだったからね。