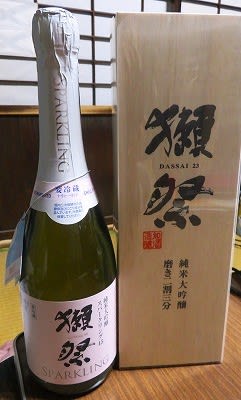先週のこと。わが畑の脇の河津桜がほぼ満開となった。植樹しておよそ十年ほどになるが、シカの食害を受けながらも久しぶりの青空のもとたくましく開花している。これだけ太くなってくると、さすがにシカも手出しはしなくなってきている。シカだから手は出ないのは当たり前か??

それでもまだまだ樹は若い。カワズザクラ自体は、1955年に伊豆河津町で発見、増殖され始めたのが1968年。オラが伊豆の河津町に行ったのがその20年後の80年代かと思われる。それでも、駐車場がなくて苦労するくらい観光客がやってきていた。町あげてまちづくりの目玉にしたというのが戦略的に成功したわけだ。

さて、その隣にもカワズザクラがもう一本あるが、こちらは2分咲きというところ。同じ時期に植えたのに成長が遅い。こちらは、5~6回以上シカに枝をめちゃめちゃに折られ樹皮も食べられ、途中であきらめかけたことがあるほどの状態だった。そういうド根性桜なのだ。こちらも現在は、シカは手出しをしなくなったので傷だらけの防獣柵は卒業となった。このまま順調に生育してほしい。

わが家から車で20分ほど行った所のカワズザクラは、満開のピーク。そろそろ葉が出始めだしたところ。ところがその花見をする人を見たことがない。というオラも、車からチラリと見るだけだが。この並木の延長にはもっと長い桜並木が川沿いにある。目黒川の人ごみあふれる花見もいいが、じっくり花見をするにはおすすめの場所である。

江戸の大名屋敷の庭園は1000箇所を超えるほどあったという。だから、園芸が産業としても成長したとともに植木職人が育ち、染井村で産まれたソメイヨシノが全国に広まっていく。世界一を誇った江戸の田園国家は今や花の代わりにビルとマンションを満開にした。そこには、利権や欲望に群がる魔界のおこぼれこそ豊かさだ国民に洗脳する。
『都市を終わらせる』のは、21世紀の課題だが、現実の世界はジェノサイドをしても心痛まない指導者の魔術に忖度・従順するしかない日々がある。日本は「同調圧力」というみんなと同じ考えにあることで安心を得るという催眠術から未だ醒めない日々が続く。江戸の指導者・大名は少なくとも花を愛する心はあったということは確かなようだ。