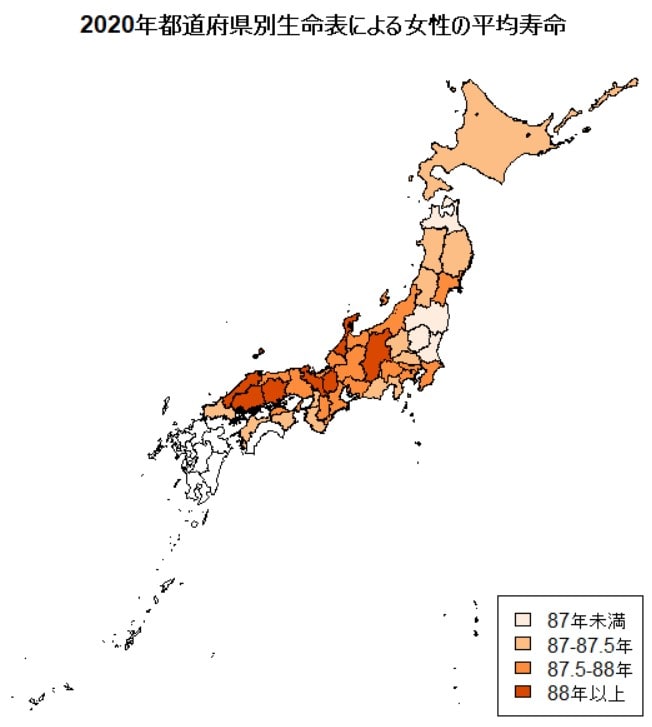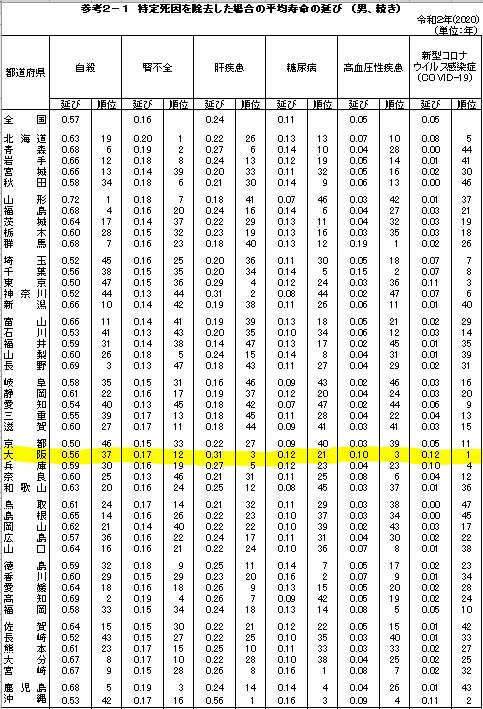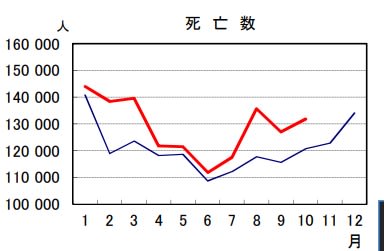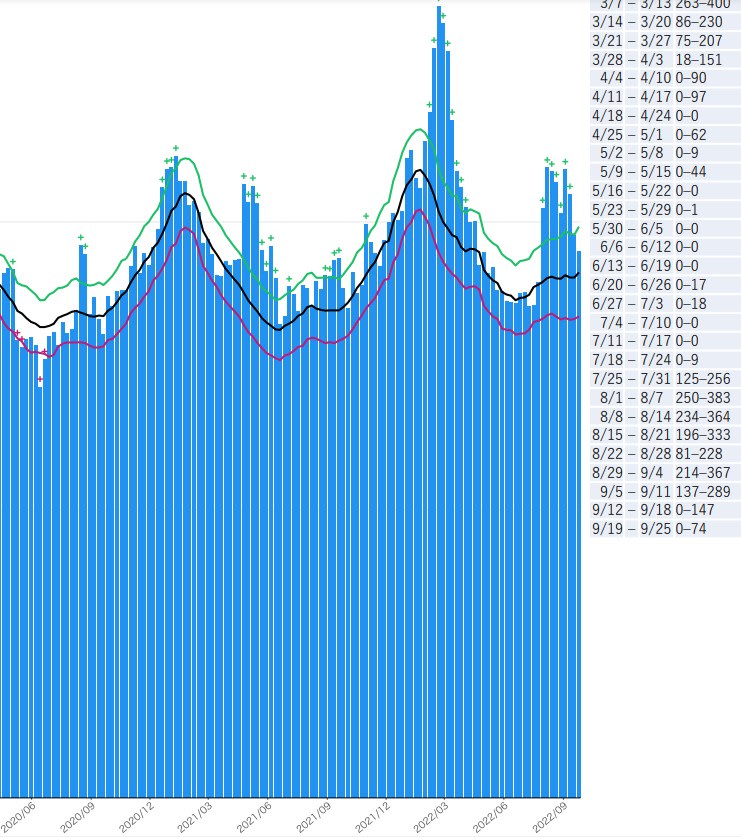先日のつづきです。
池を挟んで形の良い枝ぶりが見えました。
池畔のアカメヤナギ(ヤナギ科)の大木です。
周りがすっかり葉を落としているのと対照的に冬のこの時期にも、葉をまだ残しています。

川岸や池・湖などの岸辺に生える落葉高木
新葉が赤みを帯びるためアカメヤナギと名付けられた
葉は長楕円形で先端が尖り、縁には微かなギザギザがあり、シダレヤナギなどに比べると丸みがあるため、別名をマルバヤナギとも。

散策路を進むとまだ紅葉が、樹木に囲まれた一帯が赤く染まっています。
近づいてみると、ドウダンツツジ(ツツジ科)の背の高い木です。この時期まで楽しませてくれます。

そして、その先で異様な光景に出くわしました。
白い世界が樹木の間に広がっています。
枯れた竹林です。

竹は、開花後枯れるということですが、その開花について、
aff(あふ)<農林水産省を結ぶWebマガジン> 2021年 21年3月号
身近で不思議なタケの生態に迫る!
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2103/spe1_01.html
によれば、
数十年から100年に一度の頻度でしか開花しないタケの開花の仕組みは、現在も謎
・67年周期で開花するというモウソウチク
マダケとハチクの開花は120年周期といわれている
・モウソウチクのように開花した後に地下茎まで枯れるタケもあるが、ハチクのように地下茎は枯れない
・ハチクは1908年前後に開花。地上部分の稈はいったん枯死したが、地下茎からまたタケノコが生まれて再生
120年周期の開花だとすれば、全国的な開花ピークは2028年頃といわれてきたが、竹林ごとに多少のズレがあるため、10年ほど前からすでに開花が始まっている
この枯れた竹林の竹の種類は、何か確かめられませんが、
・タケには節ごとに、細胞が分裂して成長する「成長点」と呼ばれる部分があり・・、仮に節が40個あってそれぞれの成長点が1日に1センチメートルずつ伸びれば、稈は1日で一気に40センチメートル成長することになる
・著しく成長する稈同様、地下茎も生命力が旺盛で、横にぐんぐん伸長していきます。最大で1年に5メートルから8メートルも地下茎が伸びた記録があるほど、タケは繁殖力が強いことが特徴
この枯れた竹林の竹の種類は、何か確かめられませんが、
・タケには節ごとに、細胞が分裂して成長する「成長点」と呼ばれる部分があり・・、仮に節が40個あってそれぞれの成長点が1日に1センチメートルずつ伸びれば、稈は1日で一気に40センチメートル成長することになる
・著しく成長する稈同様、地下茎も生命力が旺盛で、横にぐんぐん伸長していきます。最大で1年に5メートルから8メートルも地下茎が伸びた記録があるほど、タケは繁殖力が強いことが特徴

コロナに苦しむ今の世界と重ね、来年は、竹が立派に再生してほしいと願わずにはいられません。