
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道㉜
100キロ先のムール貝
アムステルダム(オランダ)、アントワープ(ベルギー)
オランダのアムステルダムに駐在したのは、1979年の晩夏から足かけ2年である。
当地でのランチは、お客様である某自動車会社の立派な従業員用canteen(食堂)で食べることが多かった。最初の数日こそ、物珍しさもあって、楽しんで食事をしたのだが、だんだんcanteenから足が遠のいた。
数種類のパン、ハムとチーズ、油でギトギトの春巻き、細長い俵型や丸形のパサパサの味無しコロッケ、ゆで卵、野菜スープ等、来る日も来る日も同じような食べ物ばかり。変化と言えば、せいぜい、スープがトマト味から塩味に変わることくらいだ。
ある日、ランチのテーブルを挟んで、オランダ人マネージャーとcanteenのメシの話になった。
「ここのメシ、結構うまいだろ?」
「ウーン、そうですね…」
正直な私は、ウマイと相槌を打つことができず、浮かない顔をしたまま答えを濁した。彼は、お構いなく続ける。それも得意そうに。
「今日は6種類のハムに5種類のチーズ、揚げ物もあるし、パンだって何種類もある。アップルタルトだってある。最高だろ!」
「……でも、ハムはハム、チーズはチーズでしょ。悪いけれど、毎日ハムとチーズばかりじゃね…。キミらは他のものが食べたくならないの?」
不満が溜まっていたのだろう、私は吐き出すように言ってしまった。気まずい空気が流れ、彼は言葉にならぬ言葉を残し、席を立った。
オランダでの体験については、これまでに何度か駄文を連ねてきたが、オランダを語る上で欠かせない、食べ物に纏わる話が抜けていた。食べ物の話と言っても、美食に関するものではない。その反対である。俗に英国料理は不味いと言われているが、不味さにかけてはオランダ料理の圧勝だと私は思っている。
英国料理は、繊細さに欠け、「煮過ぎ、焼き過ぎ、味が無い」とこき下ろされていて、食の世界で名誉ある地位を占めている訳ではない。試しに、「英国料理」、「イギリス料理」で検索してみると、チェーン店のパブ、フィッシュアンドチップス、ローストビーフ、スコーン、シェパードパイぐらいしかヒットしない。
自虐的な英国人なら、「エッ! イングリッシュブレック・ファスト以外に、そんなに沢山英国料理が見つかるの!?」と感動するかも知れない。そして、自嘲的に眉をしかめて、こう言ったりもするだろう。
「ヨーロッパには、美味しい食べ物が沢山ある。しかし、英国には、美しいテーブルマナーがある!」
私は、不味い料理をエレガントに食べるより、美味しい料理にかぶりつく方がよほど好きだ。とはいえ、英国には救いがある。大都会ロンドンには世界中の美味しいレストランが集まっていて、お金さえ払えば世界中の美味しい食事に不自由することはない。しかし、我が敬愛するオランダの皆様には申し訳ないが、オランダでは、美食に飢えるのである。
オランダの食べ物と言えば何を思い浮かべるだろうか。ゴーダやエダムなどのチーズ、豆のスープ、オランダに春を告げる風物詩でもあるハーリング(英語ではヘリング。塩漬けのニシン)くらいではないだろうか。
オランダは、九州ほどの面積しかない小さな国だが、なんと農産物の輸出額は米国に次ぐ世界第2位である。豊富な乳製品、ニシン、牡蛎、ムール貝などの海の幸も豊富である。それなのに、それなのに、どうして豊かな食文化と無縁なのだろうか。
アムステルダムの下町に、Café de la Paix(カフェ・ド・ラ・ペ)という大衆的ではあるが、洒落た雰囲気のフレンチ・レストランがあった。この店は、フレンチとは名ばかりで、メニューに書かれた料理名と運ばれてくる料理がどうしても結びつかないという不思議な店だった。
白ワインで食事を始め、メインの肉料理に合わせて赤ワインを注文した。ウエイターは、ワインボトルのコルクを抜き、にこやかな顔で先ほどまで白ワインが満たされていた安物のソーダガラスのワイングラスに赤ワインを注ごうとした。
「オイオイ、ちょっと待ってよ。新しいグラスに換えてくれないかな」
「エッ…、何で!?」と言わんばかりに怪訝な表情を浮かべるウエイター。
「オレ、なんか変なことを言ったかな」
と一瞬不安になってしまった。
「OK、OK…」
彼は、めんどうくさい客だなと背中で語りながら、新しいグラスを運んできてくれた。
この事件により、質実剛健を旨とする一般のオランダ人は、食には(あまり)興味がないのだという私の仮説が実証できた気がした。食に無頓着なオランダ人ではあるが、彼らが毎年楽しみにしているものが、三つある。
一つは、春の訪れを告げるホワイトアスパラガス。日足が伸びてくると、街中に「アスパラス入荷」の看板が溢れる。
 ▲ホワイトアスパラガス
▲ホワイトアスパラガス
二つ目はハーリングと呼ばれる塩漬けのニシンだ。5月下旬になると、ハーリングの水揚げが始まり、街中には、趣向を凝らしたハーリングの屋台が軒を連ねる。その年の最初の一匹は王室に献上される。これは、「お召し上がりの儀」と呼ばれ、18世紀から続く伝統行事だ。そして二匹目は、ご祝儀相場として高値で買い取られる。なにやら、日本の初鰹のようだ。

▲ニシンの酢漬け

▲伝統的なニシンの食べ方
そして、次はいよいよ今日の主題、ムール貝だ。ムール貝は、オランダの南西部のジーランド州で、養殖されている。7月から翌年の4月までの結構長い期間に亘って楽しむことができる。
勿論、オランダの至る所で、ムール貝を食すことはできるのだが、私と同僚は美味しいムール貝を求めて、アムステルダムから130キロほど南のベルギーのアントワープ(アントウェルペン)まで足を伸ばすことが多かった。西ヨーロッパでは、高速道路網が国をまたいで整備されていて、時速100キロで計算すれば、ほぼ間違いなくどこにでもたどり着ける。
ベルギーのレストランで饗されるムール貝は総て、オランダのジーランドから運ばれたものだ。同じ材料を使い、同じようなレシピで調理されたものなのに、何故たった100数十キロしか離れていないアムステルダムとアントワープのレストランでこうも味が違うのか? 合理的な説明ができない。私には、大きな謎だ。
食文化は奥が深い。ムール貝には様々な料理法があるが、私が一番好きなのは、白ワイン蒸しだ。店によって細かいレシピの違いはあるが、基本は、パセリ、エシャロット、ニンジン、リーキ(香りの強くない西洋ネギ)、生姜、ニンニクなどの野菜、ハーブ、スパイスと共に専用のポット(バケツ)で調理し、ポットのままテーブルに運ばれてくる。
ウエイターが、芝居がかった身振りで蓋を取ると、うっとりするような香りが広がる。最初のムール貝を両手でこじ開ける。二つ目からは、こじ開けた貝をピンセットのように使って身を挟み出すのが地元の人たちの食べ方だ。
真似してみると、滅法食べやすい。更に、貝の片側をスプーン代わりにしてスープを啜ることもできる。定番の付け合わせ、フリット(フレンチ・フライ)も貝のピンチではさみ、スープに浸して食べる人もいる。英国人が愛する美しいテーブルマナーからは外れるが、こういう自由気儘な食べ方が更に料理を美味しくするに違いない。
ムール貝には、高級な白ワインより安物のシャブリあたりをゴクゴクやる方が合う気がする。爽やかな酸味がつよい、ヒュールガルデン・ホワイトビールなどもお勧めだ。

▲ムール貝の白ワイン蒸し 定番の付け合わせはフリット(フレンチ・フライ)

▲ムール貝を蒸すための専用調理器具
東京で初めて、ムール貝のワイン蒸しを食べた時の衝撃は今も忘れない。味は悪くなかった。ただ、出てきたのは、小ぶりの深皿に恭しく鎮座する6粒ほどの小さなムール貝。その横の小さな皿に乗っているのは数本のフレンチ・フライだった。メニュー上、魚料理のメインの一皿として記載されているのだが、まるでオードブルではないか。これは、悪い冗談か。呆れ、怒っている私を見て、一緒にいた友人が言った。
「まぁ、まぁ、ここは日本なんだから、しょうがないよ」
そうか、日本だから、しょうがないのか。これならオランダのムール貝の方が千倍ましだ、と思ったが、たまたま変な店に当たってしまったのだろうと考え直すことにした。どなたか、美味しいムール貝が食べられるレストランをご存じなら、教えてください。
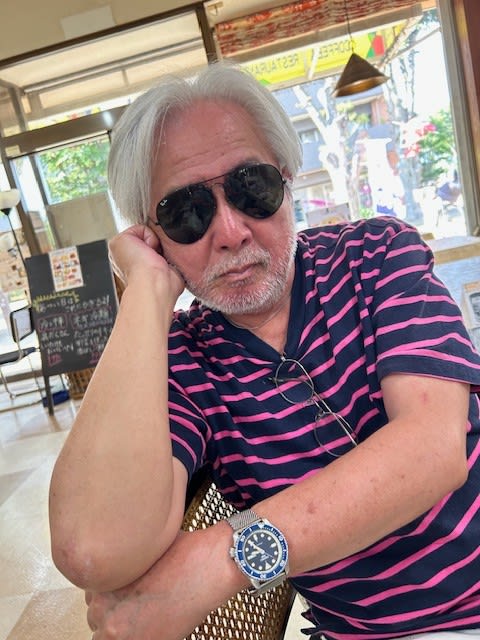
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。

























