
伝教大師最澄様と論争した法相宗の僧徳一に付いては、私は関係する書籍を片っ端から目を通すようにしていますが、最近になって次々と新たな研究成果が発表されています。小林祟仁師の『日本古代の仏教者と山林修行』は昨年八月に出たばかりですが、私には大変参考になりました。
といいますのは、それまで否定されていたことが、逆に脚光を浴びるようになってきたからです。資料が乏しいとはいえ、徳一の説明をめぐっては、立場立場で大きな食い違いがあるからです。
小林師が特筆したのは下記の点です。私はそれに関して論じる知識を持ち合わせてはいませんが、私なりに勉強したいと思っております。「藤原仲麻呂(恵美押勝)子息説は、薗田香融氏が仔細に検討し、その可能性は極めて低いとしたが、近年に保立道久氏は子息説に大きな矛盾は発生しないとする。また興福寺修円の弟子との説は、塩入亮忠氏が両者の年齢関係から疑問視をしたが、そもそも両者の生没自体に不明の点があり判断しかねる。むしろ玄奘や窺基の流れを汲む正統唯識学派の学的系譜からして、南都時代の徳一が、修円と近しい位置にあった可能性は十分にあり得る」
ここで注目されるのは、藤原仲麻呂子息説の再評価です。小林師は保立道久東京大学史料編纂所名誉教授が「藤原仲麻呂息徳一と藤原氏の東国留住」(『千葉史学』六七・二〇一五)を執筆し、「徳一が仲麻呂の子として七四九年(天平勝宝一)頃に生まれたという想定と徳一の生涯の事績との間に大きな矛盾は発生しない」と主張したのを紹介しています。
さらに、保立同名誉教授の説明の文章を注釈において引用しており、それは衝撃的な見方でした。「天平宝宇八年(七六四)の仲麻呂蜂起事件に際し、当時十六歳であった徳一は陸奥に流罪になるものの、後に許されて東大寺へ戻り、さらに藤原氏の氏寺である興福寺に拠点を移したというのは十分に考えられるとする。そして、『徳一があらためて会津に下った理由は、やはり一つの別世界を希求したためと理解すべきであろうか』と述べる。また、仲麻呂の弟の巨勢麻呂の子孫が、常陸や上総などと深い関係をもっていたことを指摘し、『徳一の開基伝承をもつ諸寺院は常陸国から上総にかけて広がる徳一の同族の藤原氏の留住者たちの存在を背景として理解すべきものである』とし、京都と地方の双方で活動した貴族、いわゆる留住貴族の問題を論じている。徳一が実際に仲麻呂の子息で、仲麻呂蜂起事件を契機として同族が東国に留住していたとなれば、それは徳一が斗藪(とそう)の行き先として東国を選択する大きな背景になったと考えられる」
このほか、徳一を修円の弟子とする説については、修円と徳一の双方の生没年が不明であることから、断定を避けることで、可能性の余地を残したともいわれます。このことに関しては今後新たな展開があるとみられていますが、興福寺や室生寺との関係からも、修円と徳一が無関係であったと断定することの方が間違っているのだと思います。














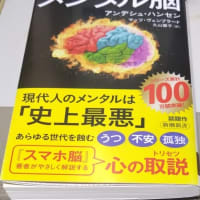




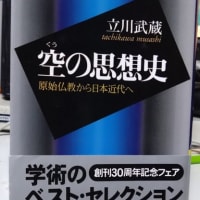






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます