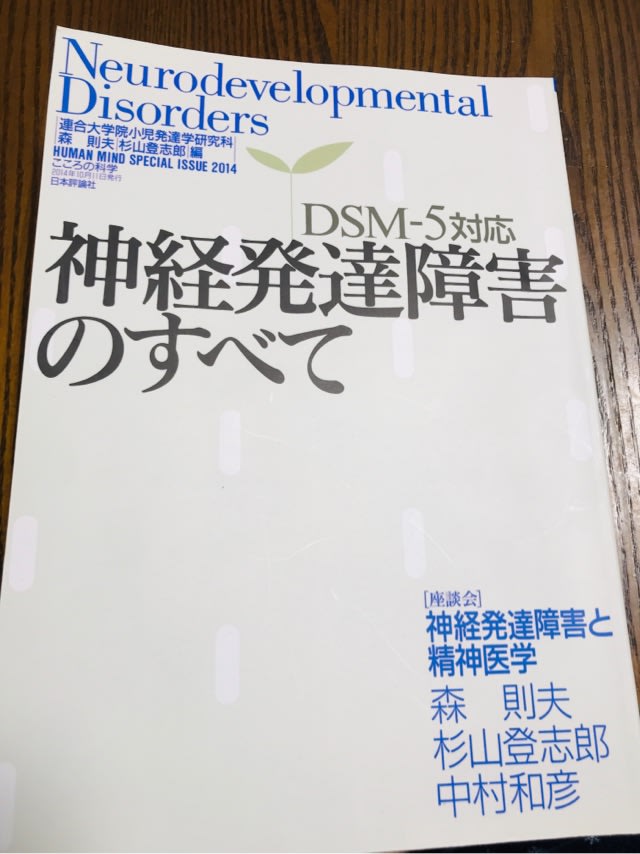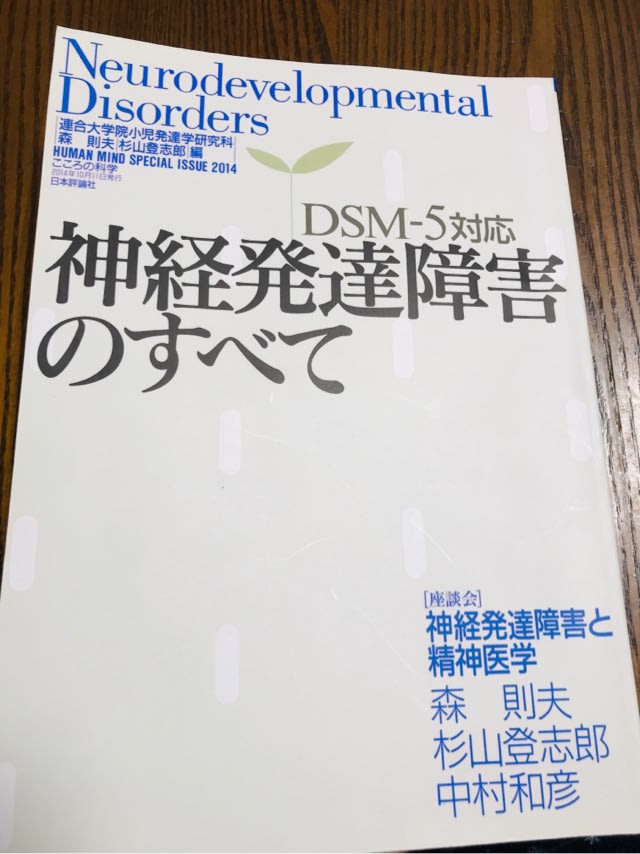早朝の仕事場では、まだ清々しい空気の中仕事が始まります。
場所は、外ではないし、かといって室内でもない、半外のようなところです。
その清々しい時間帯に、同僚が花粉症と闘っていました。
今年初らしいのですが、苦しそうです。
もう、春ですね。
神経発達障害について、まったく腑に落ちなかった『神経発達障害のすべて』。
まぁ、こんなこともあろうかと、こちらも買っておきました。

『臨床かのためのDSM-5虎の巻』
まったく、期待感ゼロな私の心と裏腹に、Amazonでは☆4つの高評化!
ともかく、読んでみよう!と読み進めました。
で、わかりました。
神経発達障害とは何かが。
神経発達障害(neurodevelopmental disorders)は従来の発達障害である。(原文ママ)
私は、英語に暗い者なので、間違ってたらいかんな、と、一応、調べてみましたが、
「発達障害」という言葉の英訳には、「Developmental disorders」という言葉が出てきます。
グーグル先生もウェブリオ先生もほかのよくわからない翻訳先生も、
「発達障害」=「Developmental disorders」
「神経発達障害」=「Neurodevelopmental disorders」と出てきます。
ところが、虎の巻の杉様的には、
「Neuro」がついても、つかなくても「発達障害」でオッケーと言うことのようです。
え?それでいいのか?
「飾りじゃないのよ〜Neuroははは〜〜〜〜っ♪」(某陽水さんの歌のメロディで)と、
思わず、目が点になりました。
これが、DSM-5の虎の巻…。
気をとりなおして、読み進めますが、上記引用の6行あとには、
世界に先駆けて、AD/HDを発達障害と認定したことをわが国は自慢してよいのではないか、という
脳天気さ発揮で、先が思いやられます。
しかし、読み進めます。
知的障害については、「遅滞」という言葉の響きについての言及(私的には虎の巻においての重要性不明)、
「純然たる知的障害のみの者は相対的に減少」「知的障害において併存症は広く存在」と、
診断注意事項の羅列に留まっています。
コミュニケーション障害について、
「手話を用いる聴覚障害に関しても、コミュニケーション症の可能性を考慮することが可能になった」
診断拡大を喜ぶかのような報告がなされています。
特異的学習障害については、文部科学省や教育も科学だろ!とどこかの小学校校長に遠吠え。
要するに、学習障害についても知的障害同様に重症度分類しろよ!
で、その分類の判定はギョーカイに任せろよ!ということと、私は解釈しました。
学びたい子どもにとって、たとえ学習障害があったとしても、
その学習障害の度合いが軽度だ、中等度だ、重度だって、どーでも良いことだと思うのですが。
それを判定することで、学習しやすくなるのでしょうか?
むしろ、「重度だから」といつまでも平仮名の練習などというブラックなことになりそうですけど…。
運動障害については、翻訳本では約12ページばかり割いてあるのですが、
虎の巻では12行あまりという興味の薄さ。
まぁ、虎の巻に項目があるだけで、ありがたいというところでしょうか。
そして、最もボリュームを取っているのは、
もちろん、杉様お得意の自閉症スペクトラムについてです。
さて、虎の巻、ASDの概念変更のまとめの部分に、
「幼児期の症状を中核とした診断基準から、
どの年齢でも用いることが可能なものへと大きく変わった」とあります。
これは、「幼児期の頃、知覚過敏や鈍感なとこなどがなくても、
成人になってそういう症状があればASDかも、って診断できるよね!」と
診断を拡大できることを喜ばしいことのように書いているだけで、一体何の概念変更なのか頭をひねりました。
更に、「自閉症スペクトラム」と「自閉症スペクトラム障害」と「自閉症」という言葉の深堀り。
もう、自閉症スペクトラム好きすぎて、ディープに語るオタク魂炸裂な杉様。(褒めてません)
そして、次のような恐ろしいことをさらりと言ってのけているのだから、
びっくりを通り越して、呆然としたのは言うまでもありません。
以下、引用です。
われわれはDSM-5が出てから、児童精神科の外来にこの新たな診断基準表を置いて、
新患に関してなるべくチェックするようにしてきたが、DSM-Ⅳよりはるかに診断が容易になり、
また診断対象が広がったというのが実感である。それはそうだ。
知覚入力の異常が認められればあと1項目のこだわり行動で基準Bは陽性になる。
しかもAD/HDの併存があっても診断ができる。
「診断が容易になり、診断対象が広がった」ことは喜ぶべきことでしょうか?
「あと、1項目で基準Bクリア!」ってゲームなの?
虎の巻の世界は、私たちが日常生活を送る場所とは異質な闇が広がった世界のようです。
そして、神経発達障害のトリは、今日から君も仲間入り!の「注意欠如/多動性障害」についてです。
ここでは、「症状発現年齢の引き上げ」と
「17歳以上では下位項目を5項目満たせば良いと診断基準が緩和された」こと、
「重症度分類」の導入と、この「緩和」は誰にとっての福音だよ!?と突っ込みどころ満載です。
こんな読むだけで、疲労感を味わえる虎の巻ですが、
我らが杉様は、「治療を組むために役立てなくては診断そのものがラベルにすぎない」などとおっしゃっています。
この言の前のページでは、
「一人のの子どもが、診断カテゴリーを渡り歩く、あるいはいくつもの診断基準を満たす現象」を
「出世魚現象」とよんでいるなどと軽口を叩いておられます。
出世魚現象の「好例」として、
「AD/HD→反抗挑戦性障害→素行障害へと展開する破壊的行動症群の行進(DBDマーチ)」と
冷血さ丸出しです。
だから、治せよ、ということなのですが。
こんな虎の巻を頼りに、大事なお子さんや悩みに悩んで病院に足を運んだ方々を診断するのでしょうか?
治りたい子どもも大人も、治すのはお家、そして、自分ということを肝に銘じて、
診断オタクの餌食にならないようにしたいものですね。
あー、焼酎風呂はいって、邪気払い、邪気払い!
場所は、外ではないし、かといって室内でもない、半外のようなところです。
その清々しい時間帯に、同僚が花粉症と闘っていました。
今年初らしいのですが、苦しそうです。
もう、春ですね。
神経発達障害について、まったく腑に落ちなかった『神経発達障害のすべて』。
まぁ、こんなこともあろうかと、こちらも買っておきました。

『臨床かのためのDSM-5虎の巻』
まったく、期待感ゼロな私の心と裏腹に、Amazonでは☆4つの高評化!
ともかく、読んでみよう!と読み進めました。
で、わかりました。
神経発達障害とは何かが。
神経発達障害(neurodevelopmental disorders)は従来の発達障害である。(原文ママ)
私は、英語に暗い者なので、間違ってたらいかんな、と、一応、調べてみましたが、
「発達障害」という言葉の英訳には、「Developmental disorders」という言葉が出てきます。
グーグル先生もウェブリオ先生もほかのよくわからない翻訳先生も、
「発達障害」=「Developmental disorders」
「神経発達障害」=「Neurodevelopmental disorders」と出てきます。
ところが、虎の巻の杉様的には、
「Neuro」がついても、つかなくても「発達障害」でオッケーと言うことのようです。
え?それでいいのか?
「飾りじゃないのよ〜Neuroははは〜〜〜〜っ♪」(某陽水さんの歌のメロディで)と、
思わず、目が点になりました。
これが、DSM-5の虎の巻…。
気をとりなおして、読み進めますが、上記引用の6行あとには、
世界に先駆けて、AD/HDを発達障害と認定したことをわが国は自慢してよいのではないか、という
脳天気さ発揮で、先が思いやられます。
しかし、読み進めます。
知的障害については、「遅滞」という言葉の響きについての言及(私的には虎の巻においての重要性不明)、
「純然たる知的障害のみの者は相対的に減少」「知的障害において併存症は広く存在」と、
診断注意事項の羅列に留まっています。
コミュニケーション障害について、
「手話を用いる聴覚障害に関しても、コミュニケーション症の可能性を考慮することが可能になった」
診断拡大を喜ぶかのような報告がなされています。
特異的学習障害については、文部科学省や教育も科学だろ!とどこかの小学校校長に遠吠え。
要するに、学習障害についても知的障害同様に重症度分類しろよ!
で、その分類の判定はギョーカイに任せろよ!ということと、私は解釈しました。
学びたい子どもにとって、たとえ学習障害があったとしても、
その学習障害の度合いが軽度だ、中等度だ、重度だって、どーでも良いことだと思うのですが。
それを判定することで、学習しやすくなるのでしょうか?
むしろ、「重度だから」といつまでも平仮名の練習などというブラックなことになりそうですけど…。
運動障害については、翻訳本では約12ページばかり割いてあるのですが、
虎の巻では12行あまりという興味の薄さ。
まぁ、虎の巻に項目があるだけで、ありがたいというところでしょうか。
そして、最もボリュームを取っているのは、
もちろん、杉様お得意の自閉症スペクトラムについてです。
さて、虎の巻、ASDの概念変更のまとめの部分に、
「幼児期の症状を中核とした診断基準から、
どの年齢でも用いることが可能なものへと大きく変わった」とあります。
これは、「幼児期の頃、知覚過敏や鈍感なとこなどがなくても、
成人になってそういう症状があればASDかも、って診断できるよね!」と
診断を拡大できることを喜ばしいことのように書いているだけで、一体何の概念変更なのか頭をひねりました。
更に、「自閉症スペクトラム」と「自閉症スペクトラム障害」と「自閉症」という言葉の深堀り。
もう、自閉症スペクトラム好きすぎて、ディープに語るオタク魂炸裂な杉様。(褒めてません)
そして、次のような恐ろしいことをさらりと言ってのけているのだから、
びっくりを通り越して、呆然としたのは言うまでもありません。
以下、引用です。
われわれはDSM-5が出てから、児童精神科の外来にこの新たな診断基準表を置いて、
新患に関してなるべくチェックするようにしてきたが、DSM-Ⅳよりはるかに診断が容易になり、
また診断対象が広がったというのが実感である。それはそうだ。
知覚入力の異常が認められればあと1項目のこだわり行動で基準Bは陽性になる。
しかもAD/HDの併存があっても診断ができる。
「診断が容易になり、診断対象が広がった」ことは喜ぶべきことでしょうか?
「あと、1項目で基準Bクリア!」ってゲームなの?
虎の巻の世界は、私たちが日常生活を送る場所とは異質な闇が広がった世界のようです。
そして、神経発達障害のトリは、今日から君も仲間入り!の「注意欠如/多動性障害」についてです。
ここでは、「症状発現年齢の引き上げ」と
「17歳以上では下位項目を5項目満たせば良いと診断基準が緩和された」こと、
「重症度分類」の導入と、この「緩和」は誰にとっての福音だよ!?と突っ込みどころ満載です。
こんな読むだけで、疲労感を味わえる虎の巻ですが、
我らが杉様は、「治療を組むために役立てなくては診断そのものがラベルにすぎない」などとおっしゃっています。
この言の前のページでは、
「一人のの子どもが、診断カテゴリーを渡り歩く、あるいはいくつもの診断基準を満たす現象」を
「出世魚現象」とよんでいるなどと軽口を叩いておられます。
出世魚現象の「好例」として、
「AD/HD→反抗挑戦性障害→素行障害へと展開する破壊的行動症群の行進(DBDマーチ)」と
冷血さ丸出しです。
だから、治せよ、ということなのですが。
こんな虎の巻を頼りに、大事なお子さんや悩みに悩んで病院に足を運んだ方々を診断するのでしょうか?
治りたい子どもも大人も、治すのはお家、そして、自分ということを肝に銘じて、
診断オタクの餌食にならないようにしたいものですね。
あー、焼酎風呂はいって、邪気払い、邪気払い!