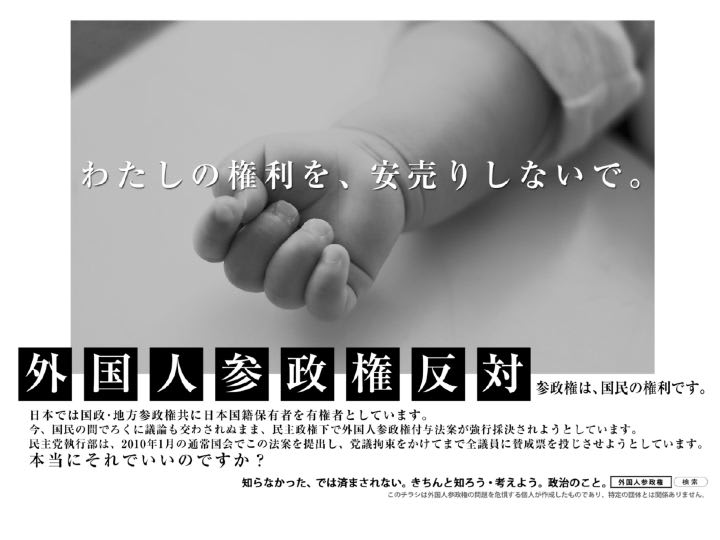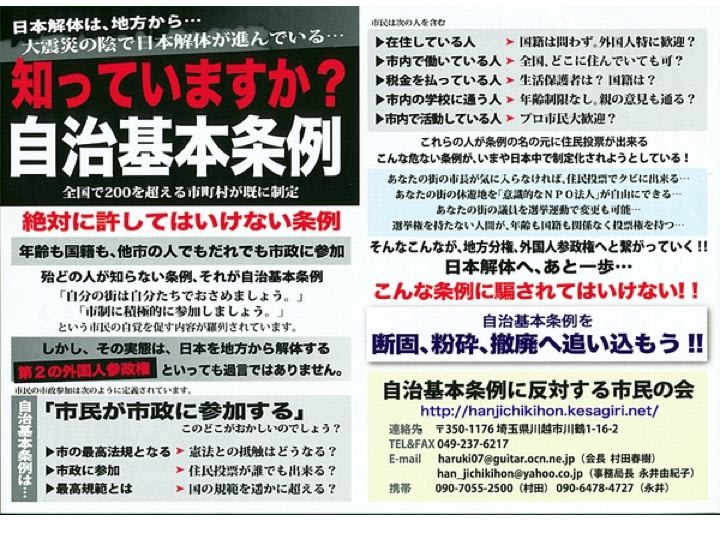朝日新聞の偏向報道から子供の未来を守る!会
朝日新聞は2011年12月4日(日)の社説に「政治を鍛える 自治―『自分たちで決める』が原点だ」を掲載している。以下、一部を転載する。
■議会を変えよう
4年に一度の選挙で知事や市町村長、議員を選ぶ。それだけで私たちは主権者といえるのだろうか。もっと、役所や議会との距離を縮めよう。
まずは議会だ。落選したときを考えれば、一般の勤め人は出にくい。だから自営業など一部の職種の議員が居並び、住民構成とかけ離れた議会になる。住民は関心を抱かず、不信感を募らせる悪循環に陥っている。
会議を夜に開くなどの工夫はもちろん、職場の仕事と議員活動を両立できる休職制度や、議員が議席を持ったまま首長選や国会に挑める制度などの仕組みを整えよう。
いまの議会には予算の提案権はなく、修正にも制約がある。住民に認められている条例制定などの直接請求では、地方税は対象にできない。
こうした地方自治法の規定が、議会や住民を「自治体の財政」に関する議論から遠ざけているとの指摘がある。法改正を検討してもいいだろう。
有権者の間口も広げよう。
「選挙制度」でも提言したが、若者に地域のことを考えてもらうため、地方選挙権は16歳から認める。永住外国人にも地方選挙の投票権を与えよう。「日本国籍をとればいい」という反対論も根強いが、地域の一員として暮らす人々を排除しないことで、多様な意見が行き交い自治が豊かになる。
■もっと住民に聞こう
住民投票制度も進化させる。投票ごとテーマごとに条例をつくるのでなく、あらかじめルールを決め、一定数の請求があれば実施する常設型を増やそう。全国で40余りの自治体が導入しており、岩手県奥州市、愛知県高浜市などでは永住外国人にも投票権を与えている。
また、首長と議会が対立したら、住民投票で決着をはかるのも一案だ。名古屋市のように首長と議会の激しい対立にエネルギーを費やすより、その両方を選んだ住民の判断に委ねるという発想だ。
自治の議論では、大阪都構想や道州制といった自治体の枠組みの議論が華やかに取り上げられがちだ。だが、もっと地道に地方分権を進め、足元を見つめ直すことで、住民自治を強めることが出発点になる。
できる限り、みずから参加して、考え、判断して、決めて、その責任も負う。そんな自治へのかかわりが、私たち自身の「政治」を鍛える。
この社説の問題点は2つある。
1つは言わずと知れた「外国人参政権」である。記事には「永住外国人にも地方選挙の投票権を与えよう」とある。
しかし、「外国人参政権」は憲法15条1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」に明らかに違反する違憲行為であり、朝日新聞は違憲行為を推奨しようとしているのである。
もし、「外国人参政権」が認められ、後段にある「地方分権」が進めば、沖縄に住む中国人が米軍基地に反対する地方議員を選出することで、日本から米軍基地を追い出し、日本侵略に向けて大きな一歩を進めることは目に見えている。
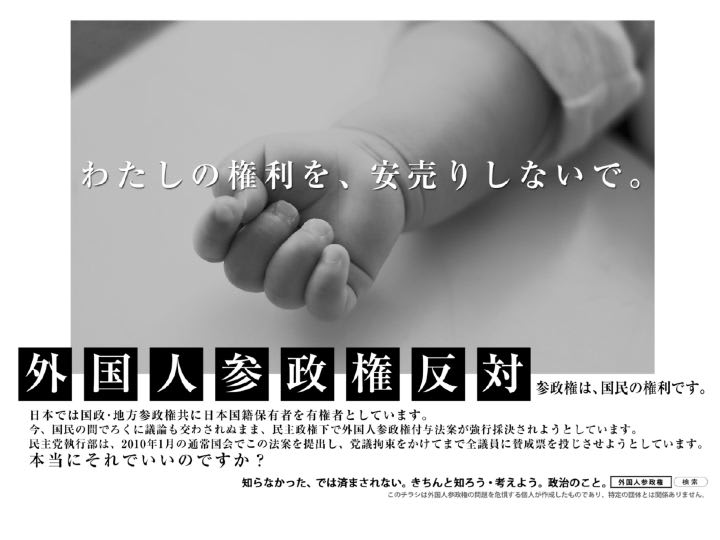
また、2つ目は後段が「自治基本条例」に繋がる考え方であることが指摘される。
これは外国人を含む住民(いわゆる「市民」)が住民投票などの強力な拘束力を持った「直接民主制」によって、条例を作ったり、市長をクビにできるようにする制度である。
これも外国人が事実上、参政権を持つことに繋がり、また、左翼勢力が特定の町に移住することで、自衛隊基地や米軍基地を追い出すような危険が出てくる。
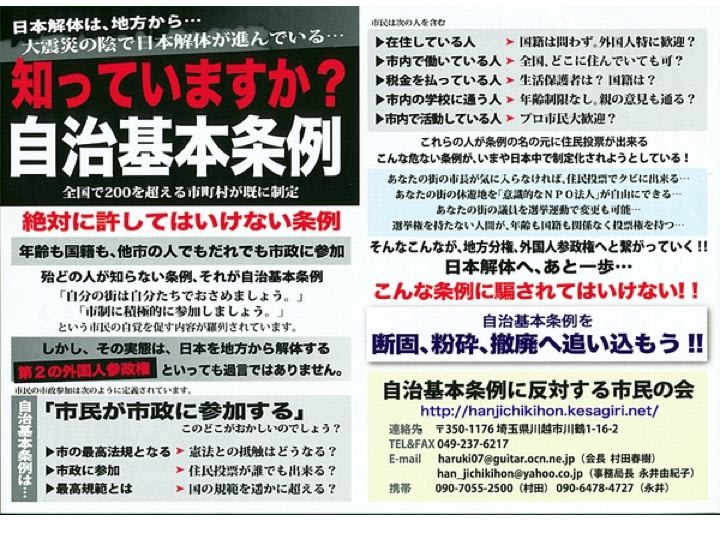
いずれにしても、朝日新聞は、民主党政権と一体となって「国家解体法案(条例)」の成立を促進し、「日本解体」を目指していることが明らかになった社説である。(竜)