学童野球には試合時間という制約があります。Jr(4年生以下)なら60分、Reg(6,5年生)なら90分です。
一番いいのは既定の回数(Jrは5回、Regなら7回)を、この時間内に終わらせることです。
しかし、だいたいは時間が先で終わってしまう事が多いと思います。
私も審判をしていて、この時間以内に終わる試合を数試合みてきました。
では、時間以内に終わる試合と終わらない試合、どこに違いがあるのでしょうか?
時間内に終わらない推定原因
①投手が四球を連発する
②野手のエラーが多い
③投手の投球リズムが悪い
①と②に関してはすぐに直せるものではありません。(特に我がチームです。(´;ω;`)ウッ…)
しかし、③はピッチャーの意識を変えれば、直ぐに直す事ができます。
リズムに乗った投手は、次々とテンポ良く投球してきます。
そういったチームは攻守交替の駆け足や、打席への入り方などもすごくスムーズです。
だから、野球のテンポが一番影響する守備は投手なのです。
何せ、投手が投球しないことには野球の試合は進行しませんので。
だからと言って、キャッチャーから返球されたら、直ぐに投げる必要はありません。
ですが、先に述べた通りテンポよく来ている時には、流れを止めない試合を進めたいです。
逆に、エラーや失点が続いた際には、しっかり時間を取って”流れ”を止めたいですね。
野手は投手と違って、準備(捕球待機)の時間がどうしても長くなり、その時間が長続きしない=エラーが発生しやすいとなってしまいます。
先の述べたように、投手が投球しないとプレイが始まらないからです。
だからこそ「投手の投球間隔が短いと野手が守りやすい」の理由は、こういうところにあるのだと思います。
そして、テンポ良く投球していくことは投手にもメリットがあります。
「迷いや不安がなくなる」ということです。
特にピンチの時など、ピッチャーは
「次の球、打たれたらどうしよう…」
「ストライク入るかな…」
などと不安になるものです。中にはポジティブな投手も居ますが、ほとんどの投手は時間をかければかける程、不安が増します。
逆に考えれば、そういう事を思わない性格の持ち主がピッチャーに向いているとも言います。
でも、やっぱり人間ですから不安も出ます。
投球間隔が間延びすればするだけ、この「迷いや不安が出る時間」を生んでしまいます。
逆に言うと「テンポ良く投げる」ということは「迷いや不安の出るヒマを与えない」ということに繋がるということです。
そして、この投球のテンポは「ピッチャーとキャッチャーの共同作業」で作り上げるものです。
「思い切ってドンドン投げてこい!」とピッチャーを乗せていくのはキャッチャーの役目なのです。
キャッチャーが「女房役」と言われるのは大人になると良く理解できます。
だからといって、ポンポンと一定の間隔で投球していては、相手のバッターも投球と打撃がシンクロしてきます。
そうするとポンポンとヒットが出やすくなってきます。
そうなってくると「兎に角早く投げてベンチに帰りたい!」と思うばかりに、逆にいつのまにか自分のリズムがおかしくなってしまうこともあります。
制球を乱すなど、思い通りのピッチングが出来なくなってしまいます。
とにかく「自分のリズム」というのが大事なんです。
早く投げることもいいですが、最低限自分の間を保てる範囲でなければいけません。
それからランナーが出たときは要注意です。
いつも同じテンポで投げていると盗塁をされやすくなってしまいます。なので走者が出たら警戒しながらじっくり投げることも必要です。
それを覚えるには、はやり沢山経験する(場数を踏む)しかないですね。




















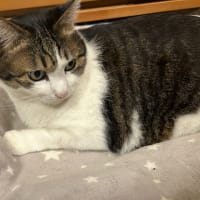
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます