
7年前にふくろうの城と言うとカフェでふくろうを撮影したり触ったりしたことを思い出しました。その時のふくろうがとても可愛くて印象に残っていたので、ネットで探してみました。すると君津市山本に「ふくろうの城・楽鳥園」と言うのがあったので、ツレと行ってみることにしました。11/1(金)のことです。

国道410号線を木更津から久留里方面に進みJR下郡駅を過ぎて、500m位進むと信号があります。それを右折すると畑の中に幟が何本も立った建物が見えてきました。そこが目的地です。

そこにいた犬を飼育している従業員の方に聞いてみると、プレハブの建物の1階がカフェふくろうの城でした。中に入れてもらうとビックリ、ふくろうが沢山いて圧倒されました。また入口のドア近くに木の切り株とそれと同じくらいの大きさのふくろうがいて、大きな目をクリクリさせて私たちを見ています。

まず料金を支払いました。大人1人1100円(税込み)、小学生以下770円(3才以下は無料)ペットボトルのドリンクがサービスで付いています。帰りにいただきました。営業時間は午前11時~17時(受付16時まで)一人1時間まで遊べます。猫カフェ等と同じです。

カフェの中にはお姉さんがいて色々説明をしてくれます。とても分りやすく親切です。中ではフラッシュを使わない撮影や触ったりなぜたりするのもOKです。餌やり体験もしましたが、最初はふくろうが嫌がっていたのですが、直ぐにパクパク食べてくれました。


上はメンフクロウ。下の2枚は沢山ふくろうがいて名前を覚えきれませんでした。



上の3羽はとても小さいふくろうです。全長が15cm位。まだ生まれてまもないそうですが、成鳥になっても大きさは変わらないそうです。


この小さいふくろうに手を近づけるとのってきました。可愛いですね。1羽どの位の値段か聞いてみるとると、色々種類があるのですが、30万くらいとのことでした。チョット手が出ないので、またここに来て遊んでもらおうと思います。





















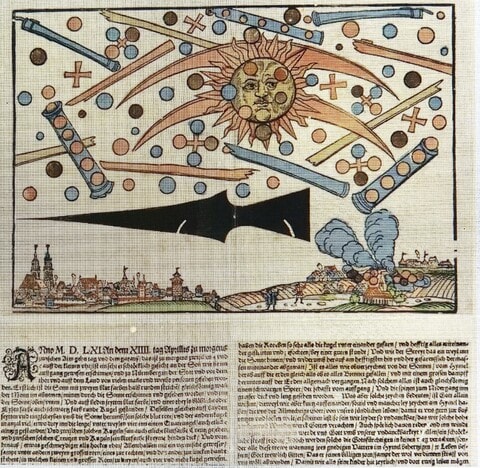
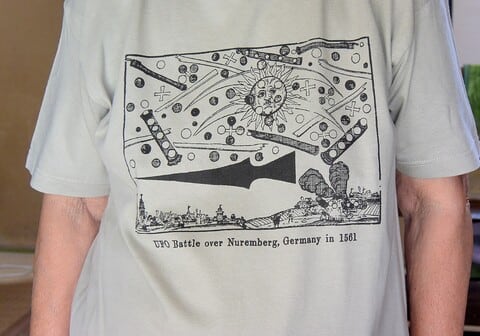

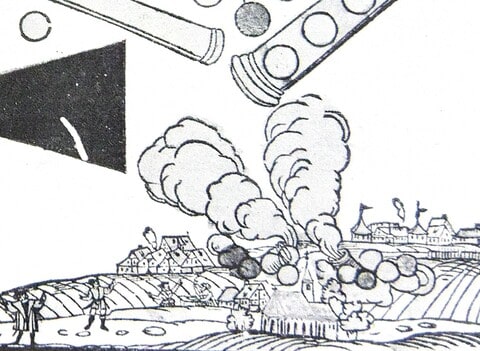
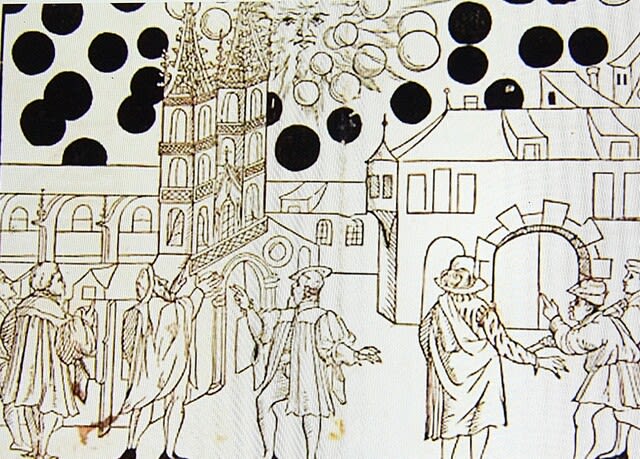
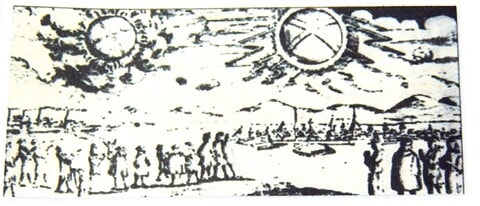

































































 ・
・





