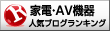で、普通にCPU部分の歩留まりや良品率に需要変動で構成変えてくるんだろうなぁ。
ES版のRyzen7-3xxxって、見るからに追加のCPUダイ乗っけるスペース有るもん@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163911.html
で、詳細(同じくimpress)まで読み進めて行くと、どうも出てくるのは半ば以降との事なので第三四半期の六月以降で、その後に新しいチップセットも出てくるし現行のintelチップに比較して消費電力も3割引よ~と言う事らしい。
PCI-Express4.0対応ではあるが、マザーボード側で対応したチップセットが存在しないので、対応マザーが出てくるのは夏以降の新しいチップセットを松必要があるので、マザーボード側が出そろうまでは旧世代のアップデートで何とかする(PCI-Express4.0対応のビデオカードってまだだよね)にしても、BIOSのアップデートにCPUが必要だったりマザーボード単体でUSBからBIOSアップデート可能だったりするタイプなら問題ない訳だが多くは無かったり(X470マザーなら、割と有るかな?)
まあ、特に問題も無く、コアの量産数やら不良率次第ですがバリエーションもどうなるか歩留まり次第なんでしょう(で、歩留まり良ければEPICに回すから半年先なんだろうな)
普通に基板上の空きスペースから見て、追加のCPUコアを乗っけてRyzen9と名打ったり、同サイズ位までのVega系GPUを乗っけたりしてくるバリエーションも想定の範囲内と言うか当たり前かな(でも、ノート向けでパッケージにとらわれないならintel向けに出したGPUと同様のことが出来るよね)
製造数じゃなく製造技術の世代(ただし、7nmってintelでの10nm世代と一対一で見るべきものではないって何処で読んだか)@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163938.html
まぁ、全体に言えることは、intelの10nm世代が本格稼働した時に対抗できるかと言うこと。
更に言うと、彼方もメインCPUの上にGPUダイやらAtomやら重ねてサンドイッチにするとか、そういった形で異種コア混合構成なんて提示してきていますから、全てでは無いにしろそういった系統と純粋にメイン系の生産効率追求でコスト削減を推し進めるAMDの路線とどちらが数で勝負できるかですね。
さて、性能的にRTX2080相当のRadeon VII@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163914.html
性能的にも、ワットパフォーマンス的にも同レベルを実現して、以下のモデルでも同様にワットパフォーマンスを改善した新シリーズが展開してくるのであればメモリ搭載量に優れるRadeon系を重視するってのも自分的にはアリになります(というか、GTX1060のワットパ凄いのよねぇ)
サイズ的には、製造技術の世代の違いもあるのですが331平方mm(7nm世代)に対して566平方mm(12nm世代は、16nm世代をベースとする)と大幅に違い、歩留まりが生産コストをカバー出来ていてVRAM搭載量がRTX2080の倍……うーむ、HBM2のコストって安くなってるのかな?
ただ、Vega64に対して動電力で25%高速ってなると、ワットパフォーマンス的に見た場合にはお察しって成ったりするのかも知れません。
あと、PS5が出てくるとしたら、同様の構成でZen2か3のコアにVegaとHBMのメインメモリで阿呆みたいなメモリ速度って事もHBMの値段が下がっているとしたら有るかなぁ?
GDDR6と、HBMと……どちらの方が最終的に安いかって話になるとは思うけれどどうなんだろね。
ES版のRyzen7-3xxxって、見るからに追加のCPUダイ乗っけるスペース有るもん@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163911.html
で、詳細(同じくimpress)まで読み進めて行くと、どうも出てくるのは半ば以降との事なので第三四半期の六月以降で、その後に新しいチップセットも出てくるし現行のintelチップに比較して消費電力も3割引よ~と言う事らしい。
PCI-Express4.0対応ではあるが、マザーボード側で対応したチップセットが存在しないので、対応マザーが出てくるのは夏以降の新しいチップセットを松必要があるので、マザーボード側が出そろうまでは旧世代のアップデートで何とかする(PCI-Express4.0対応のビデオカードってまだだよね)にしても、BIOSのアップデートにCPUが必要だったりマザーボード単体でUSBからBIOSアップデート可能だったりするタイプなら問題ない訳だが多くは無かったり(X470マザーなら、割と有るかな?)
まあ、特に問題も無く、コアの量産数やら不良率次第ですがバリエーションもどうなるか歩留まり次第なんでしょう(で、歩留まり良ければEPICに回すから半年先なんだろうな)
普通に基板上の空きスペースから見て、追加のCPUコアを乗っけてRyzen9と名打ったり、同サイズ位までのVega系GPUを乗っけたりしてくるバリエーションも想定の範囲内と言うか当たり前かな(でも、ノート向けでパッケージにとらわれないならintel向けに出したGPUと同様のことが出来るよね)
製造数じゃなく製造技術の世代(ただし、7nmってintelでの10nm世代と一対一で見るべきものではないって何処で読んだか)@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163938.html
まぁ、全体に言えることは、intelの10nm世代が本格稼働した時に対抗できるかと言うこと。
更に言うと、彼方もメインCPUの上にGPUダイやらAtomやら重ねてサンドイッチにするとか、そういった形で異種コア混合構成なんて提示してきていますから、全てでは無いにしろそういった系統と純粋にメイン系の生産効率追求でコスト削減を推し進めるAMDの路線とどちらが数で勝負できるかですね。
さて、性能的にRTX2080相当のRadeon VII@impress
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1163914.html
性能的にも、ワットパフォーマンス的にも同レベルを実現して、以下のモデルでも同様にワットパフォーマンスを改善した新シリーズが展開してくるのであればメモリ搭載量に優れるRadeon系を重視するってのも自分的にはアリになります(というか、GTX1060のワットパ凄いのよねぇ)
サイズ的には、製造技術の世代の違いもあるのですが331平方mm(7nm世代)に対して566平方mm(12nm世代は、16nm世代をベースとする)と大幅に違い、歩留まりが生産コストをカバー出来ていてVRAM搭載量がRTX2080の倍……うーむ、HBM2のコストって安くなってるのかな?
ただ、Vega64に対して動電力で25%高速ってなると、ワットパフォーマンス的に見た場合にはお察しって成ったりするのかも知れません。
あと、PS5が出てくるとしたら、同様の構成でZen2か3のコアにVegaとHBMのメインメモリで阿呆みたいなメモリ速度って事もHBMの値段が下がっているとしたら有るかなぁ?
GDDR6と、HBMと……どちらの方が最終的に安いかって話になるとは思うけれどどうなんだろね。