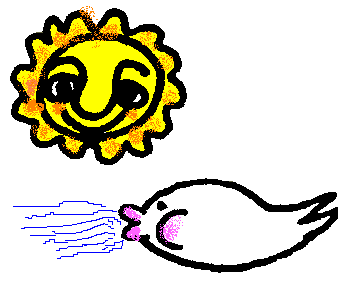頭のいい馬 (PART 1)

(hans01.jpg)

(hans02.jpg)

(horse31c.jpg)

(junko11.jpg)
デンマンさん。。。、最近、頭のいい馬に出会ったのですかァ~? うふふふふふふ。。。

(kato3.gif)
いや。。。 特に頭のいい馬に出会ったというわけじゃないのですよ。。。
それなのに、どういうわけで頭のいい馬を取り上げたのですか?
あのねぇ~、バンクーバー市立図書館で借りていた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのです。。。

(horse33.jpg)
「馬」を「うま(むま)」と訓じるのは、中国語の「マ」(もしくは「バ」)が転じたものである。
つまり倭語にはあの動物を表す言葉がなかったのである。
ほとんど見たこともなかったのであるから、それも当然である。
また、馬のことを駒というのも、「高麗(こま)」つまり高句麗の動物という意味なのであった。
(注: 赤字はデンマンが強調。
読み易くするために改行を加えています。
写真はデンマン・ライブラリーより)
38ページ 『戦争の日本古代史』
著者: 倉本一宏
2017年7月12日 第4刷発行
発行所: 株式会社 講談社

あらっ。。。 馬は昔から日本にいるものだとばっかり思っていましたけれど、昔の高句麗からやって来たのですわねぇ~。。。

そうなのですよ。。。 馬のことを駒というのも、「高麗(こま)」つまり高句麗の動物という箇所を読んで、なるほどと思いましたよ。。。 つまり、高句麗の「句」と「馬」を合体したものが「駒」。。。 この字を「高麗(こま)」と読むことにしたというのですよ。。。 だから、馬が高句麗からやって来たという事実を素直に理解できましたよ。。。
つまり、この事が言いたくて、今日の記事のタイトルをわざわざ頭のいい馬としたのですか?
いや、違います。。。 馬のことでは次のような記事を書いたことがある。。。

(foolw.gif)
Subj:小百合さん、おはよう!
秋晴れのバンクーバーは
爽やかで清々(すがすが)しい
ですよう!
きゃはははは。。。
Date: 24/08/2010 11:57:46 AM
Pacific Daylight Saving Time
日本時間:8月25日(水)午前3時57分
From: denman@coolmail.jp
To: sayuri@hotmail.com
CC: barclay1720@aol.com

(vanc700.jpg)
雲一つない、どこまでも青い空が広がっていますよう。
“天高く馬肥ゆる秋”
昔の人は上のように言ったけれど、
どうして天が高くなると馬が肥えるのか?
馬を使って畑仕事をしたことのない僕には分からないけれど、
そう言えば、僕のお袋の実家が南河原村にあったのですよう。
今では行田市に合併されて無くなってしまった村だけれど、
僕がまだ小さな小さな頃
幼稚園に上がる前ですよう。
おそらく4つか5つだったのでしょうね。
その農家には馬小屋があって
その中で飼われていました。
お袋の話だと、その馬を借りていたそうです。
小さな子供の目には、とてつもなく大きな馬の姿は、まるで恐竜が目の前に現れたような驚きでした。
とても怖いと思った記憶がありますよ。

(horse52.jpg)
それでも興味があるから僕は馬をしみじみと眺めている。
馬だってぇ、小さな子供が興味深そうに眺めているから、僕の様子をじっと見詰めていましたよう。
その大きな目が、とっても優しそうに感じたものです。
今から思えば、その馬は牝馬で母性本能の優しさが目に表れていたのではないだろうか?
その馬が生んだ子馬を見るような優しいまなざしで僕を見つめていたような、そんな感じをその優しい大きな目から感じたものでした。
母親の実家で馬を一番可愛がっていたのは祖父だったそうです。
お袋はどうだったの?と尋ねたら、
長女だったお袋は小学校にあがる頃から、農作業や家事の手伝いをさせられて、
馬の面倒を見るのは、ただただつらいことだったらしくて、
馬が居るから自分の仕事が増えると思って、可愛いどころではなかったそうですよう。

(horse60.jpg)
やがて耕耘機(こううんき)が使われるようになって、
馬は、元の飼い主に返したそうです。
それから何年経った時の話なのか?
僕は忘れてしまったけれど、
ある日、祖父が自転車に乗って農道を走っていたら、
馬がいなないたと言うのですよう。
おやっと思って馬をよく見ると、祖父が可愛がっていた馬だったそうです。
懐かしくなって、馬に近寄って鼻をなでてやりながら、その時の飼い主に、その馬を使っていた頃のことを話してやったそうです。
馬も可愛がってくれた人のことを覚えているのですよね。
その馬は、元々優しい馬だったと僕には思えるのですよう。
今でも、その馬の優しくて大きな目が僕の記憶の片隅に残っているのです。

(horse30.jpg)
バンクーバーの雲一つ無い空を見ていたら、なぜか急に、その馬の優しい目が思い出されてきました。
不思議なことです。
小百合さんも、子供の頃の懐かしい思い出を懐かしみながら軽井沢タリアセン夫人になりきって元気に楽しくルンルン気分で過ごしてね。
ん。。。? 何か面白い話が読みたいの?
じゃあねぇ、次の記事を読んでみてね。

(boy002.jpg)
■『愚かな愚か者』
(2010年8月24日)
笑って元気を出してね。
じゃあ、またねぇ。

(denman01.gif)
『天高く馬肥ゆる秋』より
(2010年8月29日)

あらっ。。。 昔、一緒に働いていたデンマンさんのおじいさんを馬は覚えていたのですわねぇ~。。。

そうなのですよ。。。 馬を持ち主に返してからどれくらい時間が経っていたのか、僕ははっきりと覚えていないけれど、おじいさん自身が驚いたほどだから、おそらく1年以上経っていたのですよ。。。
つまり、この事を言いたかったのですか?
いや。。。 もちろんそれだけじゃないのですよ。。。 この話を思い出してから、かつて愛読していたイギリスのジェームズ・ヘリオットさんが書いた本の中のエピソードを思い出したのです。。。
それは、どのようなお話なのですか?
次のようなエピソードです。

(horse34.jpg)
フレッド爺さんは働き者でした。
毎日、朝日が昇ると畑に出て 草むしりをしたり、羊を放牧地に連れて行ったりするのです。
夕方になると、羊を迎いに行って小屋に連れ戻すのでした。
フレッド爺さんの唯一の楽しみは、すべての仕事が終わったあとで
飼い馬のトッドに引かせた荷車に乗って、近くのパブ(居酒屋)でビールを飲むことでした。
そして常連さんと世間話をするのが常でした。

(pub001.jpg)
でも、時には飲みすぎてトッドがじっと待っていた荷車に乗ると、
すぐに居眠りを始めてしまうのです。
それでも、トッドはちゃんと帰る道を覚えていて
フレッド爺さんがどんなに酔っ払って寝込んでしまっても
無事に家まで連れてゆくのでした。

つまり、この事が言いたかったのですか?

いや。。。 そればかりじゃないのですよ。。。
まだ頭のいい馬がいるのですか?
いるのですよ。。。 世界的に有名になったハンスと呼ばれた馬がいたのです。。。
頭のいい馬 ハンス

(hans02.jpg)
人間の言葉が分かり計算もできるとして19世紀末から20世紀初頭のドイツで話題になったオルロフ・トロッター種の馬である。
実際には観客や飼い主が無意識下で行う微妙な動きを察知して答えを得ていた。
1891年頃から飼い主のヴィルヘルム・フォン・オーステンが出す簡単な問題を蹄で地面を叩く回数で答えると言う事で有名になり、1904年にはカール・シュトゥンプらによって調査されたが、何のトリックもないと結論づけられた。
その後アルバート・モールによって飼い主の動きを追っている事が指摘され、1907年に心理学者オスカー・フングストらによってハンスがどのようにして答えを得ていたかが解明された。
観客や飼い主、出題者、その場に居合わせた誰にも問題が分からないように出題する(あらかじめ紙に書かれた問題を出題者が見ずに出題する、あるいは出題後直ちに立ち去る)と、ハンスは正解を出す事ができなくなったのである。
つまり計算ができるのではなく、回りの雰囲気を敏感に察知することに長けた馬だったのである。
今日ではこのような現象を「クレバー・ハンス効果」と呼び、観察者期待効果としてのちの動物認知学に貢献した。
調査
関心が高まり、ドイツ教育委員会は卿の主張の検証を申し入れた。
哲学者であり心理学者でもあるカール・シュトゥンプは、「ハンス委員会」として知られる評議会に、獣医師やサーカス団長、重騎兵隊隊長、教員ら、ベルリン動物公園園長などを招いた。
13人からなるこの評議会は1904年、「ハンスの能力に誤謬は見当たらない」と結論した。
評議会はこの結果をフングストに通知した。
彼はハンスの能力の根拠を以下の方法で検証した。
1.馬と質問者を見物人から離すことによって、そこから手がかりを得られないようにする。
2.質問者は馬の持ち主であってはいけない。
3.遮眼帯を用いて、馬が質問者から見えるかどうかは変化させる。
4.質問者が質問の答えをあらかじめ知っているかどうかを変える。
十分な回数テストを行ってフングストが得た結果では、質問者が卿である必要はない(詐称ではないことが証明された)が、馬が正しく答えられるためには、質問者が答えを知っておりかつ見える位置にいることが必要だった。
卿が答えを知っている時は馬は89%の確率で正しく答えたが、そうでない時は6%しか正答しなかった。
フングストは次に、質問者の身振りを詳細に観察し、ついに、馬が蹄で叩く回数が期待された回数に近づくにつれ、質問者の体勢と表情が次第にこわばり、最後の一叩きの瞬間にその緊張が開放されているという点を発見した。
馬はこの合図を判断の手がかりに使っていたのだ。
馬の社会システムでは、群れの他の個体の姿勢・体勢・重心移動などが重要であり、ハンスが卿の体勢の変化をたやすく読み取れた理由はここにあったのだろうと想像できる。
卿は、自分がそのような合図を送っていることなどまったく意識していなかっただろう。
しかし、そのような読み取り能力は馬に固有のものではない。
そこでフングストは、馬の立場に人間が立ち、質問者の質問に足のタップで答えるテストをさらに行った。
結果、被験者は90%の場合正解することができた。
なお、卿もハンスも残酷なほどに癇癪持ちであった。
卿は馬が失敗する度に怒り狂う傾向があり、ハンスは実験中、フングストに幾回も噛みついたようである。
こうして公式にハンスの知性が否定された後も、卿はフングストの発見を気に留めることなく、ハンスをドイツ中に紹介して回り、ハンスはその度に大観衆に迎えられたようだ。
そして1909年に卿が亡くなるとハンスは何人もの人の手に渡り、恐らくは第一次世界大戦に投入されたと考えられている。
1916年より後の記録は残っていない。
出典: 「賢馬ハンス」
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。 回りの雰囲気を敏感に察知することで答えを見つけたのですわねぇ~。。。

そういうことですよ。。。
つまり、このハンスを思い出して、馬という生き物は意外に頭がいいということを話したかったのですか?
いや。。。 そればかりじゃないのですよ。。。
まだ他にも言いたいことがあるのですか?
あるのです。。。 もう一度次の箇所を読んでみてください。。。
小さな子供の目には、とてつもなく大きな馬の姿は、まるで恐竜が目の前に現れたような驚きでした。
とても怖いと思った記憶がありますよ。

(horse52.jpg)
それでも興味があるから僕は馬をしみじみと眺めている。
馬だってぇ、小さな子供が興味深そうに眺めているから、僕の様子をじっと見詰めていましたよう。
その大きな目が、とっても優しそうに感じたものです。
今から思えば、その馬は牝馬で母性本能の優しさが目に表れていたのではないだろうか?
その馬が生んだ子馬を見るような優しいまなざしで僕を見つめていたような、そんな感じをその優しい大きな目から感じたものでした。

この時の僕は幼稚園へ上がる前だから4つか5つだったのですよ。。。

。。。で、その時のお馬さんも頭が良かったのですか?
いや。。。 馬じゃなくて、その馬を見ていた僕がその馬が生んだ子馬を見るような優しいまなざしで僕を見つめていたような、そんな感じをその優しい大きな目から感じたのですよ。。。
つまり、4つか5つのデンマンさんもハンスのように 馬の雰囲気を敏感に察知することができたと言いたいのですか?
そうです。。。
でも、それはデンマンさんが大人になってから あとづけで感じたのではありませんか?
いや。。。 僕がその馬を見上げてじっと眺めている時に感じたのですよ。。。 「おウマさんは自分の子供とはなれてさびしいんだねぇ~」と、その時の小さな僕は お馬さんと会話している気分でしたよ。。。

(horse10.jpg)

(laugh16.gif)
(すぐ下のページへ続く)