アベノミクス 庶民に厳しい状況も…電気、食品価格高騰へ目配りを(産経新聞) - goo ニュース
アベノミクスへの期待から株高・円安が続いている。デフレからの脱却を最重要課題とする安倍政権の意向を受けて、日銀も物価上昇率2%の目標を掲げた。先行きの物価上昇を見込むことで企業の投資や家計の消費を促し、デフレで萎縮していた経済を動かすことが狙いだ。ただ、その際にひとつ、留意しておくべきことがある。穀物やエネルギー価格については、中長期的にインフレ傾向をみせていることだ。安倍政権に求められるのは、デフレ脱却と同時に、生活に不可欠な食品や電気料金などの価格上昇を抑制する複合的な視点だ。
◆中産階級の貧困化
1月30日の衆院本会議で、日本維新の会の平沼赳夫国会議員団代表が安倍晋三首相に対してこんな指摘をした。
「最近ではデフレ、インフレの議論の上にスクリューフレーションの危機があり、さらなる中産階級の貧困化を招くといわれている」
デフレとインフレはともかく、スクリューフレーションは聞き慣れない言葉かもしれない。米国経済の現状を表す言葉として最近話題になっている表現だ。中間層の生活水準低下を意味する「スクリューイング」と、物価上昇の「インフレーション」を掛け合わせた造語である。
その意味はこうだ。米国経済は成長してきたが、豊かさを享受しているのは一部の富裕層だけで、中間層の賃金は伸びていない。そんな中で食料品やガソリン代などが高騰したため、富裕層と比べ、支出に占める生活必需品の割合が多い中間層の貧困化が進んでいるという見方である。
第一生命経済研究所の永浜利広主席エコノミストや評論家の中野剛志氏らは、この現象が日本にも当てはまるとして警鐘を鳴らしている。長引くデフレに加えて食糧・エネルギーのインフレ圧力も発生しているという点で事態は米国より深刻かもしれない。
◆円安で影響拡大
では、具体的な状況はどうなのか。日本の製造業は新興国の割安な製品との激しい価格競争に直面している。賃金の安い新興国を相手に競争力を維持しようとすると、賃金にしわ寄せが行く。デフレ下で勤労者収入は減少し、多くの人の生活水準が低下した。
一方で穀物や原油などの相場は2000年代以降、高騰している。08年の食糧危機時ほど深刻化していないが、昨年の米国の干魃(かんばつ)の影響で、大豆やトウモロコシなどの価格は今も高値水準だ。原油相場も1バレル=100ドルを超える水準で高止まりしている。
問題は、価格高騰の背景に中長期的な構造変化があることだ。中国などの新興国の経済成長で需要は急増。世界的な金融緩和であふれたマネーが商品相場に向かう投機的な動きもある。中東情勢など地政学的なリスクも深刻だ。米国産の新型天然ガス「シェールガス」の供給増で価格水準が下がる期待はあるが、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加が決まらない段階で、どれだけ米国から割安で大量のガスを安定的に輸入できるかは見通せない。
日本は穀物やエネルギーの多くを海外に頼る。これまでは円高で割安に輸入できたため価格高騰の影響が緩和されたが、円安時はそうもいかない。レギュラーガソリンの全国平均価格は10週連続で上昇している。生活に車が欠かせない地方ほど痛手だ。
原発の稼働停止も懸念材料だ。火力で代替したため燃料の輸入が膨らみ、電力会社の経営を圧迫。その結果の電力料金の値上げは家計にも大打撃だ。さらに来年4月から税率がアップする消費税には低所得者ほど重税感を伴う逆進性がある。庶民に厳しい状況は今後も次々に出てくる。
◆原発戦略再構築急げ
安倍政権が最優先で取り組むべきことが、所得・雇用環境の改善を伴う形でのデフレ脱却であることは言うまでもない。同時に、食料品や電気料金などのインフレ圧力にも目配りすることが大切だ。行きすぎた円高の是正が日本経済の再生に不可欠な以上、円安で輸入コストが上昇することは、ある程度はやむを得ない。問題は、海外の経済情勢に左右されにくい経済構造をいかに実現するかにある。
例えばエネルギー戦略の再構築だ。脱原発で火力ばかりに頼っていると、エネルギー価格高騰のリスクから逃れられない。中長期的に再生可能エネルギーを普及させることはもちろん、安全性を十分に確保した上で速やかに原発を再稼働させるよう検討すべきだ。庶民の財布に直結する消費税率アップでは、生活必需品への軽減税率適用などの対策を早急に具体化する必要がある。多くの人が豊かさを享受できるようにするため、安倍政権に求められる政策課題は多い。
円安や株高で潤っているところもあるようですが、ガソリン代がどんどん上がって来て車通勤の身にはつらいです。
☟クリックしていただけると嬉しいです。

☟クリックしていただけると嬉しいです。
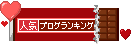
人気ブログランキングへ
アベノミクスへの期待から株高・円安が続いている。デフレからの脱却を最重要課題とする安倍政権の意向を受けて、日銀も物価上昇率2%の目標を掲げた。先行きの物価上昇を見込むことで企業の投資や家計の消費を促し、デフレで萎縮していた経済を動かすことが狙いだ。ただ、その際にひとつ、留意しておくべきことがある。穀物やエネルギー価格については、中長期的にインフレ傾向をみせていることだ。安倍政権に求められるのは、デフレ脱却と同時に、生活に不可欠な食品や電気料金などの価格上昇を抑制する複合的な視点だ。
◆中産階級の貧困化
1月30日の衆院本会議で、日本維新の会の平沼赳夫国会議員団代表が安倍晋三首相に対してこんな指摘をした。
「最近ではデフレ、インフレの議論の上にスクリューフレーションの危機があり、さらなる中産階級の貧困化を招くといわれている」
デフレとインフレはともかく、スクリューフレーションは聞き慣れない言葉かもしれない。米国経済の現状を表す言葉として最近話題になっている表現だ。中間層の生活水準低下を意味する「スクリューイング」と、物価上昇の「インフレーション」を掛け合わせた造語である。
その意味はこうだ。米国経済は成長してきたが、豊かさを享受しているのは一部の富裕層だけで、中間層の賃金は伸びていない。そんな中で食料品やガソリン代などが高騰したため、富裕層と比べ、支出に占める生活必需品の割合が多い中間層の貧困化が進んでいるという見方である。
第一生命経済研究所の永浜利広主席エコノミストや評論家の中野剛志氏らは、この現象が日本にも当てはまるとして警鐘を鳴らしている。長引くデフレに加えて食糧・エネルギーのインフレ圧力も発生しているという点で事態は米国より深刻かもしれない。
◆円安で影響拡大
では、具体的な状況はどうなのか。日本の製造業は新興国の割安な製品との激しい価格競争に直面している。賃金の安い新興国を相手に競争力を維持しようとすると、賃金にしわ寄せが行く。デフレ下で勤労者収入は減少し、多くの人の生活水準が低下した。
一方で穀物や原油などの相場は2000年代以降、高騰している。08年の食糧危機時ほど深刻化していないが、昨年の米国の干魃(かんばつ)の影響で、大豆やトウモロコシなどの価格は今も高値水準だ。原油相場も1バレル=100ドルを超える水準で高止まりしている。
問題は、価格高騰の背景に中長期的な構造変化があることだ。中国などの新興国の経済成長で需要は急増。世界的な金融緩和であふれたマネーが商品相場に向かう投機的な動きもある。中東情勢など地政学的なリスクも深刻だ。米国産の新型天然ガス「シェールガス」の供給増で価格水準が下がる期待はあるが、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)への参加が決まらない段階で、どれだけ米国から割安で大量のガスを安定的に輸入できるかは見通せない。
日本は穀物やエネルギーの多くを海外に頼る。これまでは円高で割安に輸入できたため価格高騰の影響が緩和されたが、円安時はそうもいかない。レギュラーガソリンの全国平均価格は10週連続で上昇している。生活に車が欠かせない地方ほど痛手だ。
原発の稼働停止も懸念材料だ。火力で代替したため燃料の輸入が膨らみ、電力会社の経営を圧迫。その結果の電力料金の値上げは家計にも大打撃だ。さらに来年4月から税率がアップする消費税には低所得者ほど重税感を伴う逆進性がある。庶民に厳しい状況は今後も次々に出てくる。
◆原発戦略再構築急げ
安倍政権が最優先で取り組むべきことが、所得・雇用環境の改善を伴う形でのデフレ脱却であることは言うまでもない。同時に、食料品や電気料金などのインフレ圧力にも目配りすることが大切だ。行きすぎた円高の是正が日本経済の再生に不可欠な以上、円安で輸入コストが上昇することは、ある程度はやむを得ない。問題は、海外の経済情勢に左右されにくい経済構造をいかに実現するかにある。
例えばエネルギー戦略の再構築だ。脱原発で火力ばかりに頼っていると、エネルギー価格高騰のリスクから逃れられない。中長期的に再生可能エネルギーを普及させることはもちろん、安全性を十分に確保した上で速やかに原発を再稼働させるよう検討すべきだ。庶民の財布に直結する消費税率アップでは、生活必需品への軽減税率適用などの対策を早急に具体化する必要がある。多くの人が豊かさを享受できるようにするため、安倍政権に求められる政策課題は多い。
円安や株高で潤っているところもあるようですが、ガソリン代がどんどん上がって来て車通勤の身にはつらいです。
☟クリックしていただけると嬉しいです。

☟クリックしていただけると嬉しいです。
人気ブログランキングへ









