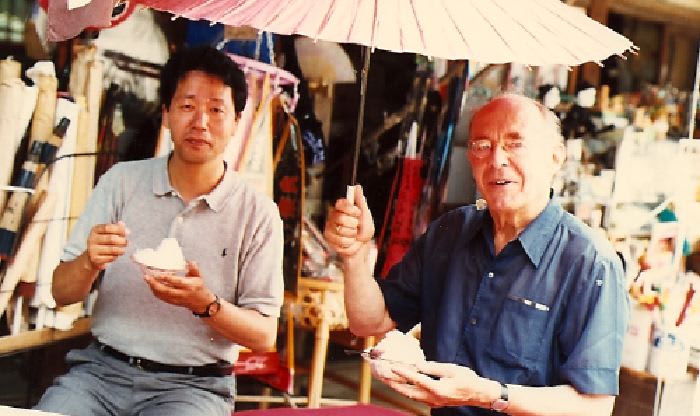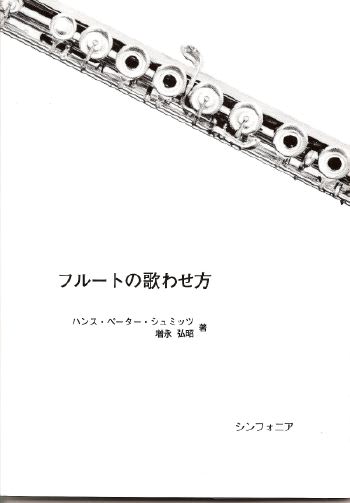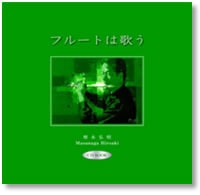図書館で本を借りました。
申し込んでから3ヶ月くらいかな。
ちょっと人気の新刊です。
人気のわけはタイトルを見るとわかります。
スゴい二人の対談です

ちょっと
なるほどと思う事が書いてあったりして
本をあまり読まない私もあっという間に読了。
ヘー,こんな風に考えているのかーと、
なかなか面白かったですし,
村上さん,音楽マニアなんだなぁと,発見。
彼の著書はちょっとしたきっかけがあって
多分、全部読んでいるんです。





















待て! をかけて、良し!来い!


ウチのボッちゃまは飛んできます。
人通りのない所を探してたまに走らせています

天気が良ければ冬は快適だよね。
でも、もう三月なんだよ
さて、おいしいおそばでも茹でようかな
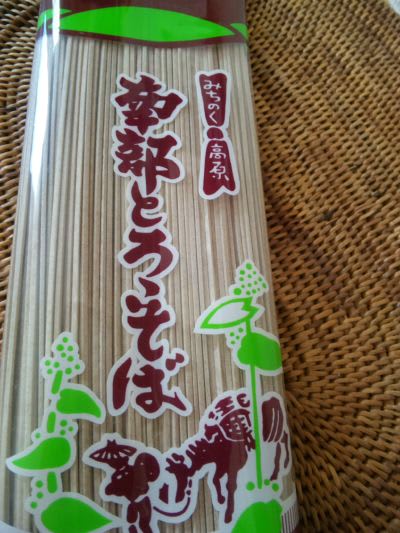
これはもう20年くらい岩手からお取り寄せ。
亡き母が気に入っていたおそばですが、
私も引き続き取り寄せています
岩手製麺さん、頑張ってくださいね~















 に
に


 )
) かも
かも
 トム君
トム君


 かわいいな~
かわいいな~ )
)