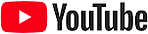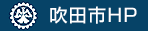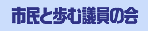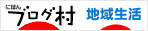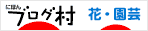未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
議会放映に関する小協議会
議会運営委員会で昨年度から協議を続けてきた「議会放映」に関して、集中して話し合いをするために小協議会を発足させることになり、今日は2回目の会議でした。1回目は委員長(私になりました)や副委員長(村口さん)を決めたり、小協議会の開催日程を決めるだけで終わりましたので、今日が本格的な協議となりました。
議会運営委員会からは小協議会で話し合ったことのまとめを12月議会開催1週間前の議会運営委員会に報告してほしいと言われていますので、そうなると遅くとも11月26日までにある一定まとめなければなりません。しかし、委員の日程が合うのが今日と16日の2日間しかないため、2回の会議で集中協議する必要があります。
そこで、今日までに各会派の意見をアンケートという形で提出してもらって、それを小協議会委員の皆さんに見ていただいておくことで、会議1回分を事前に開いたことになると考え、アンケート調査をさせてもらいました。
その結果を元に、今日は協議を始めました。まずは、アンケートに書いたことについて補足説明あるいは他の会派が書いたことへの質問がないか、尋ねました。
そして、みなさんで共通認識できることが出てきたら、それを逐次「この場でこのことは共通していることを確認します」と言って、一つずつ積み上げていきました。
一応、私が委員長として進行役をしましたが、私も意見を言いましたし、みんなが意見をどんどん出し合えるようにしましたので、2時間でずいぶん話ができたと思います。
結果としては、「できればケーブルテレビとインターネットの両方で放映することを目指す」ということを共通認識として、次回はそのためにいろんな場合ごとの想定予算やメリット、デメリット、また条件があればそれを資料として出して、実際に放映を実現することに向かって話し合うことになりました。
また、放映に関連して、対面方式と一問一答方式について話をし、これについては結論は出ませんでしたが、「対面方式に絶対にしなければならないわけではない」「一問一答方式と一括質問一括答弁方式の両方から議員が選べるようにすればいいのではないか」というところに集約できぞうでしたが、あせって結論を出してもいけないので、次回16日に持ち越すことにしました。
また、「放映することにみんなが了解しているのであれば、試験的にホームビデオカメラで撮影してYouTubeのような簡便な方法で放映してはどうか?」という意見が出ましたが、「せっかくここまで慎重に議論を重ねてきたのだから拙速にしないほうがよい」「試験的に、というのは何を試験するのか?たとえばYouTubeの写り具合をみるのであれば、他の自治体議会の放映を見ればよいのではないか」という意見がでましたし、私も「今の質問のやり方で放映してもよいと考える会派と、そうではなく放映するのであれば質問のやり方や時間配分を見直すべきと考える会派があるので、そのことのある一定のコンセンサスを得る前に試験的であれ放映はしないほうがよい」と申し上げました。
36人(今は35人ですが)議員がいれば、違いの多少はあれ、一人ひとり意見が違うのが当然なので、だからこそ合議体としての議会の存在意義があると思います。その中で、一つずつ石を積み上げるように、時には崩れることもありながら、それでも高く積み上げていく作業(過程)が大事だと思います。
とにかく、次回は16日に開催し話し合いを続けること、また議会運営委員会には16日に話し合ったことまでをまとめて報告すること、その上で、そこで話し合いを終了するのではなく1月末に予定している議会運営委員会の勉強会までの間に小協議会を開き、話し合いを続けたいと議会運営委員会に申し出ることも決めました。
小協議会の委員長として、よく意見を出してくださる委員の皆さんにも恵まれ、協議、討議する会議を進めることができて、とても良かったと思います。委員の皆さん、次回もどうぞよろしくお願いします。
『未来にまっすぐ』をご覧いただいたみなさまへ
ブログランキングに参加しています。下のバナーか、テキストをクリックしてください。ご協力よろしくお願いします。
 にほんブログ村 (政治家・市区町村)
にほんブログ村 (政治家・市区町村)
議会運営委員会からは小協議会で話し合ったことのまとめを12月議会開催1週間前の議会運営委員会に報告してほしいと言われていますので、そうなると遅くとも11月26日までにある一定まとめなければなりません。しかし、委員の日程が合うのが今日と16日の2日間しかないため、2回の会議で集中協議する必要があります。
そこで、今日までに各会派の意見をアンケートという形で提出してもらって、それを小協議会委員の皆さんに見ていただいておくことで、会議1回分を事前に開いたことになると考え、アンケート調査をさせてもらいました。
その結果を元に、今日は協議を始めました。まずは、アンケートに書いたことについて補足説明あるいは他の会派が書いたことへの質問がないか、尋ねました。
そして、みなさんで共通認識できることが出てきたら、それを逐次「この場でこのことは共通していることを確認します」と言って、一つずつ積み上げていきました。
一応、私が委員長として進行役をしましたが、私も意見を言いましたし、みんなが意見をどんどん出し合えるようにしましたので、2時間でずいぶん話ができたと思います。
結果としては、「できればケーブルテレビとインターネットの両方で放映することを目指す」ということを共通認識として、次回はそのためにいろんな場合ごとの想定予算やメリット、デメリット、また条件があればそれを資料として出して、実際に放映を実現することに向かって話し合うことになりました。
また、放映に関連して、対面方式と一問一答方式について話をし、これについては結論は出ませんでしたが、「対面方式に絶対にしなければならないわけではない」「一問一答方式と一括質問一括答弁方式の両方から議員が選べるようにすればいいのではないか」というところに集約できぞうでしたが、あせって結論を出してもいけないので、次回16日に持ち越すことにしました。
また、「放映することにみんなが了解しているのであれば、試験的にホームビデオカメラで撮影してYouTubeのような簡便な方法で放映してはどうか?」という意見が出ましたが、「せっかくここまで慎重に議論を重ねてきたのだから拙速にしないほうがよい」「試験的に、というのは何を試験するのか?たとえばYouTubeの写り具合をみるのであれば、他の自治体議会の放映を見ればよいのではないか」という意見がでましたし、私も「今の質問のやり方で放映してもよいと考える会派と、そうではなく放映するのであれば質問のやり方や時間配分を見直すべきと考える会派があるので、そのことのある一定のコンセンサスを得る前に試験的であれ放映はしないほうがよい」と申し上げました。
36人(今は35人ですが)議員がいれば、違いの多少はあれ、一人ひとり意見が違うのが当然なので、だからこそ合議体としての議会の存在意義があると思います。その中で、一つずつ石を積み上げるように、時には崩れることもありながら、それでも高く積み上げていく作業(過程)が大事だと思います。
とにかく、次回は16日に開催し話し合いを続けること、また議会運営委員会には16日に話し合ったことまでをまとめて報告すること、その上で、そこで話し合いを終了するのではなく1月末に予定している議会運営委員会の勉強会までの間に小協議会を開き、話し合いを続けたいと議会運営委員会に申し出ることも決めました。
小協議会の委員長として、よく意見を出してくださる委員の皆さんにも恵まれ、協議、討議する会議を進めることができて、とても良かったと思います。委員の皆さん、次回もどうぞよろしくお願いします。
『未来にまっすぐ』をご覧いただいたみなさまへ
ブログランキングに参加しています。下のバナーか、テキストをクリックしてください。ご協力よろしくお願いします。
コメント(0)|Trackback()
?