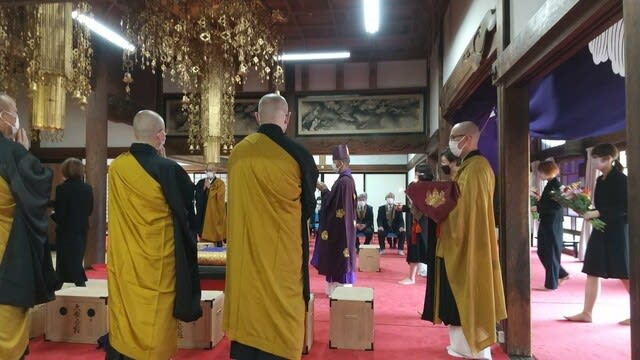菩提寺の婦人部の役を仰せつかっているので(嫁が)
仕事が休めない嫁に代わって、おばあが手伝いに。
『玄光祭』
菩提寺は「金鳳寺」といいますが、
その庫裡の横にある池のわき道を登っていくと、
「玄光神社」なるものがあります。
昔から、うちの(前の)おばあちゃんなぞは、
「おついたち(1日)とおじゅうごんち(15日)には、お詣りに行くのえ」
と、申しておりました。
(どちらも、「お」をつけるところが大事!)
小さな米袋に、お米を入れて腰にぶら下げ、
お寺への道を登って行ったばあちゃんをちょっと覚えています。
今は、こんな場所に玄光様が祀られているなんて、
知らない人の方が多いんでしょうけど。

地元のおじいちゃまたちが、弓道を奉納します。
実際にこのお祭りを見たのは、
私だって7~8年前、役員をした時が初めてでした。
ステキなお祭りなのに、もっと地域の皆さんに教えてあげてもいいのに・・・・。
なんて、思いました。
『開山忌』
続いて「開山忌(かいさんき)」です。

(「開山忌」が始まるのを待つ総代の皆様)
金鳳寺は、1480年(文明12年)に、
浜松の「玖延寺」から「天宗元康大和尚」という方がここにきて開山した、
と言われている古いお寺ですが、
1799年に火事で焼けてしまって、1814年に再建された、とのことですから、
それからだってもう、200年近くたっている、ということになります。
毎年、毎年 繰り返されてきた「開山忌」です。
『大般若会』
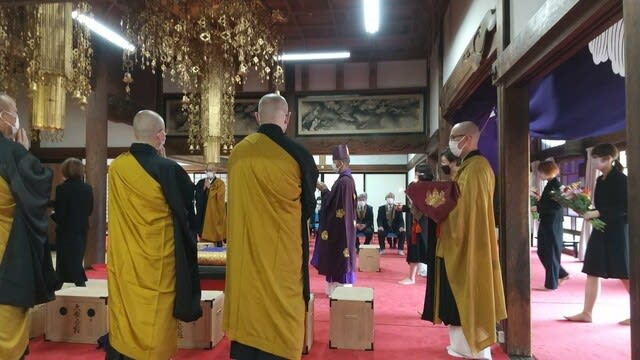
続いて「大般若会」を行いました。
これもね、一度実際にご覧になるといいのに、
と、若い人たちに言いたい!

「大般若」とは、
600巻ある経典を、皆さんで読み上げる、という法要。
白木の箱には経典が50巻ずつが入っていて、
それを12人のお坊さんたち(600÷50=12)で読み上げるのだけれど、
いちいち読んでいられないから、
こうしてパラパラする(転読する)のです。
これが、とっても見ごたえがあります。
その間に、ご住職様は、皆さんとは違う(と思う)お経をずっと唱えています。

最後にご住職様が、
自分の目の前にある、厚さも大きさも、
一回り大きい経典を「転読」します。

コロナ禍で縮小して行っていた(玄光祭は、中止してましたが)
開山忌と大般若会。
3年ぶりにご詠歌の皆さんもお願いして、
檀家の皆様にも来ていただいて、
コロナ前のようにできてよかったなあ、と思いました。


台所では、和敬会(婦人部)の役員の皆さん、
忙しく働いていました。
今年は、来てくださったお坊さんたちも、
和敬会のお母さんがたも
皆さん、若い人が増えたなあ・・・、と思いました。
私が、年を取ったせいか?
もう、おばあの出る幕ではなさそう・・・・・です。