ケーブルを下りたところには。

丹沢、大山周辺では去年あたりから麓の住宅地でも熊の目撃情報があり、小学校では保護者同伴の登下校をしていたりしたようです。
その割には鈴を付けた登山者は見かけませんでした。
大山阿夫利神社 下社

あふりじんじゃと読みます。
江戸期から大山講として庶民の信仰を受け、山岳信仰の霊山としても崇拝されてきたようです。
そういったところからか社殿なども比較的地味ですね。
数年前の本殿建替えで全てが新しいです。

階段を上がった所にはカエル。

別に神使がカエルってわけではなく、お山から「安全に帰る」の語呂合わせのようです。

南の海方面はこんなにいい天気なんですが。

お山の方はというと。 上のほうは雲の中で、もしかすると雨が降ってるかもしれません。 さすがに阿夫利山(雨降り山)です。

階段の両側にある石の欄干?は全て奉納されたもので名前が刻印されています。 日本以外からの物もありました。
厳密に言うと神道は民族宗教なんで信者になれるのは日本人のみのはずなんですが・・・。 そこはそれ、今では貰えるものならナンでもありなんでしょう。

この左手が登山道入口になっていて、そこにも手水舎があります。
どうしようか迷ったんですが、別に山用って言う服装も装備もないんで、普通の街中のカッコなんで頂上アタックは即断でヤメです。 スピード感が売りですからね。
「さーんげ さんげ 六根清浄」はまたの機会に。
帰りはケーブルに乗らず、女坂を下って大山寺経由でケーブル駅に戻ろうと思います。
男坂、女坂とあるんですが女坂のほうが楽だと思い下ったんですが、最初のうちは傾斜もあり、自然石の石段の上、苔で滑りそうで結構疲れました。 頂上目指すんだったら初心者だからこそ靴くらいはハイキング用くらいは履いていたほうがいいかも。
まだ続きます。


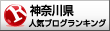

丹沢、大山周辺では去年あたりから麓の住宅地でも熊の目撃情報があり、小学校では保護者同伴の登下校をしていたりしたようです。
その割には鈴を付けた登山者は見かけませんでした。
大山阿夫利神社 下社

あふりじんじゃと読みます。
江戸期から大山講として庶民の信仰を受け、山岳信仰の霊山としても崇拝されてきたようです。
そういったところからか社殿なども比較的地味ですね。
数年前の本殿建替えで全てが新しいです。

階段を上がった所にはカエル。

別に神使がカエルってわけではなく、お山から「安全に帰る」の語呂合わせのようです。

南の海方面はこんなにいい天気なんですが。

お山の方はというと。 上のほうは雲の中で、もしかすると雨が降ってるかもしれません。 さすがに阿夫利山(雨降り山)です。

階段の両側にある石の欄干?は全て奉納されたもので名前が刻印されています。 日本以外からの物もありました。
厳密に言うと神道は民族宗教なんで信者になれるのは日本人のみのはずなんですが・・・。 そこはそれ、今では貰えるものならナンでもありなんでしょう。

この左手が登山道入口になっていて、そこにも手水舎があります。
どうしようか迷ったんですが、別に山用って言う服装も装備もないんで、普通の街中のカッコなんで頂上アタックは即断でヤメです。 スピード感が売りですからね。

「さーんげ さんげ 六根清浄」はまたの機会に。
帰りはケーブルに乗らず、女坂を下って大山寺経由でケーブル駅に戻ろうと思います。
男坂、女坂とあるんですが女坂のほうが楽だと思い下ったんですが、最初のうちは傾斜もあり、自然石の石段の上、苔で滑りそうで結構疲れました。 頂上目指すんだったら初心者だからこそ靴くらいはハイキング用くらいは履いていたほうがいいかも。
まだ続きます。


















