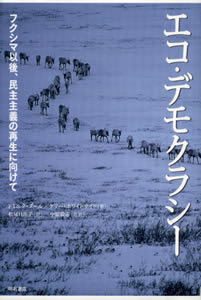
ドミニク・ブールとケリー・ホワイトサイドによる本書は、サブタイトルに「フクシマ以後、民主主義の再生に向けて」とあるが、原著は2010年に刊行されていて、〈3・11〉以降に日本で出版された。「日本の読者に向けての序文」に次のようにある。
そして忘れてならないことは、フクシマは、世界でもつとも高度なテクノロジーをもつ国の一つ、また主要な近代民主主義の国の一つで起きたという事実である。
フクシマはわたしたちに新しい世紀への入り口を示している。それは、経済の根底を支える資源(エネルギー、鉱物、生物)の有限性と、生物圏の調整メカニズムそのものの有限性という二重の有限性を前に、わたしたちの社会が信じがたいほどの脆さを露呈しつつあることが徐々にではあるが、ようやくわかってきたことを意味する。それなのに、わたしたちの代表制民主主義はこの現実に向きあおうとしない。この制度が目指すものはGDPの成長以外にないからである。 (p. 12)
本書は、①人間の(資本主義的)活動による地球生物圏の避けがたい危機の現状、②私たちが持つ政治体制としての代表制民主主義は原理的にその危機を解決することは不可能なシステムであること、③危機の克服のためのエコ・デモクラシーの提言、という構成となっている。
私たちは、人類が極めて危険な環境問題を抱えていること自体を何かにつけて知らされており、憂えてもいる。しかし、何か工夫すれば、科学技術が進展しさえすれば環境問題は解決するのではないかと漠然と考えているのではなかったか。
この本が示すのは、環境問題はそれ自体として回復不可能なことがらを内包しているばかりではなく、対処すべき人間の政治システムにその能力がないということも事態を非常に困難にしている、ということである。
著者は、環境問題の五つの特性を上げている。
一つ目の特性は、「環境問題は国境を越える」 (p. 18) という地理的広がりを持つことである。その広がりがもたらすのは地域間の利害背反であって、そのいがみ合いが解決を不可能にする。
東京電力の福島第1原発の溶融事故を日本政府は国内問題として処理したがっている。しかし、2年後の現在もまったく収束処理ができずに放射性物質を放出し続けている。とくに太平洋に垂れ流しになっている大量の放射能による海洋汚染については、現時点ではまったく手の施しようがなく、将来的には太平洋を共同利益海域と見なす国家間の政治問題となるに違いない。
二つ目の特性は、環境問題の不可視性、「環境問題は目に見えない」 (p. 21) ということである。福島原発から空中にばらまかれ、福島県ばかりではなく近隣諸県も放射性物質によってひどく汚染されたが、その汚染は目には見えない。もちろん、測定機器によって確認することは可能であるが、目に見えないことを良いことにして、県全域の放射能測定はしないと決めた県がある。測定しないことでデータがない、データがないことで放射能汚染はないと強弁したいのだ。
著者が例示するように、「交通量の多い幹線道路近くの住民たちは、一般的に自分の子供が癌になる確率が平均よりかなり高いということを知らない」 (p. 22) ということからも分るように、不可視性は意図的な情報遮断の問題でもある。福島原発事故は、情報遮断、情報隠蔽がてんこ盛りの事例である。
予知不可能性もまた重要な環境問題の特性である。「環境問題は予測できない」 (p. 23) ことが三つ目である。
放射能による健康被害、人間の活動に起因する気候変動、オゾン層の破壊、DDT 〔有機塩素系殺虫剤〕の影響、一定の動物の生殖システムにかかわる偽ホルモンの問題など、どれもがわたしたちに不意打ちを食らわせるような形であらわれた。これは単なる偶然ではない。 (p. 23)
「環境問題は世代を超える」 (p. 24) というのが四つ目の特性である。これもまた原発問題がいい例になる。被爆の問題は世代を超える。これは放射能被爆、とくに広範な地域で起きている低線量被爆が抱える最大の問題である。原発を推進したい人々は現時点での被爆被害だけを取り上げ、可能な限り過小評価をしようとしているが、被害はこれから長いスパンをかけて現われてくることは間違いない。
しかも、原発が日々生産し続けている大量の放射性廃棄物を10万年のスパンで管理し続けなければならない。ホモ・サピエンスが地球上に現われたのが15~20万年前であることを考えると、10万年後のホモ・サピエンスがどうなっているか、確かな予想は難しい。どのように言いつくろうとも、原発は未来への責任を完全に無視するか、ないしは責任を放棄することを前提としているエネルギー技術なのである。
環境問題の五つ目の特性は、「環境問題は汚染の問題」という私たちの認識の中にある。
今日わたしたちが抱えている最重要課題は、もはや汚染そのものではなく、自然環境にかかる過剰な負荷とその限界の問題である。一九五〇年代以降、爆発的に増加した人類の活動はさまざまな分野で危険限界域を越える勢いを示している。気候変動、生物多様性の損失率、人間の活動とリン・窒素循環との競合、成層圏のオゾン減少、海水の酸性化、淡水および土地の使用、化学汚染の量と質、大気中のエアゾ—ルの影響。 (p. 27-8)
著者は、この五つを環境問題における特性としてあげているが、6番目として「不可逆性」を加えてもいいのではないか。使われてしまった化石燃料は人類が生存するスパンで再生産されることはない。地球上に拡散されてしまった有毒な化学物質を回収するすべはない。ただいまこの瞬間も空中や海水へ垂れ流している福島第1原発からの放射性物質も回収することができない。「取り返しが付かない」のである。
拡散していない有毒化学物質なら中和・無毒化も可能だろうが、原発で作り出された大量の放射性物質を消すことは不可能である。それを支配しているのは人間の知恵や技術を超えた「物理学的半減期」という厳然たる物理事象だけである。科学を知らない無知な人間ほど、いずれ何とかなる、未来の技術が解決するなどと思っているようだが、冷徹な「不可逆性」を人類はひっくり返すことはできない。
生物圏への過剰な負荷は、自然からの略奪として「近代」の宿痾のように始まった。かつて古代ギリシャ的世界観では、「永遠不変の天界(アリストテレスが言う月の上の世界)によって支配される人間」の技術は、「世界を変えるようないかなる使命も与えられず、単に生活を便利にするために世界を整備するだけの手段でしか」 (p. 38) なかったのである。ところが、ガリレィ物理学に見られるような自然観と、個人の幸福を追求する自由を認める近代においては、「自然はかつての秩序と美の宇宙世界(コスモス)とは無縁なものとなり、開発され加工される資源の供給源にまでおとしめられ」 (p. 40) たのだ。
ケインズは一九三〇年に著したエッセイのなかでこう定義する。ある種の需要は「他人の状況に関係なく必要だと感じるとき」絶対的である。そして、「その充足が他人にたいする優越感を生むことから必要だと感じるとき」その需要は相対的である。
この越境と追い越しの体系的プログラムは科学、技術、政治の分野に限ったものではない。規範にたいする漠然とした蔑視は、近代社会の特徴の一つである。美術やスポーツに限らず、経済の分野でも、競争は際限のない違反の連鎖を生む。あふれるような追い越しの欲求が、無限の発展プロセスとしてあらわれた経済成長、すなわちGDP競争にエネルギーを供給してきたし、いまでも供給しつづけている。 (p. 42)
際限のない(経済的)自由の欲するままに動いてきた近代は、当然の報いのように、「エネルギー資源の枯渇の危機」、「鉱物資源の限界が生み出す技術的かつ地政学的危機」、「生物多様性の危機」が意味する「人類生存のための食糧危機」、そしていまや「淡水の有限性による危機」にまで及ぶようになってきた。
このような危機の詳細は、さすがにマスコミ・ジャーナリズムも頻繁に取り上げてきたし、政治家もしばしば政治的課題であるかのように口の端の上らせることは多い。しかし、決定的な困難が存在する、と著者は主張する。それは、地球規模の環境問題の解決にとって、現代世界のマジョリティが最良の政治システムと認めている代表制民主主義はふさわしくないということだ。
〔バンジャマン・〕コンスタンは言う。「近代人の目的は個人の利益を安全に享受することであり、それぞれの利益を制度が保障してくれることをもって彼らは自由と名づけた」。 (p. 34-5)
コンスタンによれば、代表制度は市民の日常生活に干渉すればするほど、みずからの正当性を失うことになる。近代人は自分の職業を、所属する社会集団を、自分の富を享受する方法を自分だけで選択する。近代の代表制は本質的にこの自由の概念によって規定され、そこでは、ほとんど無制限と見なされる生産と消費とが個人の幸福の主要な手段と考えられてきた。 (p. 37)
代表制民主主義は、いわば民主主義の実行システムとして確かに個人の自由と利益を守るために極めて重要な役割を担ってきた。しかし、現在の代表制民主主義は国家の枠を超えられないし、現在の選挙民の利益を守ろうとするため、何世代も先の未来に関わる問題には目を瞑らざるを得ない。
代表制が、地理的に限定された国家への市民のアイデンティティを強化すると考えられないことはないのである。むしろ、これこそが主要な役割の一つだともいえる。ここ数年に限ってみても、アメリカの上院が京都議定書の承認を拒否し、日本の議会が捕鯨の権利を擁護するところを見れば、政治家が一七世紀以降彼らに割り振られてきた役割をしっかりと果たしていることを認めざるをえない――国境によって限定された土地に住む住民の生活様式を法律で守るという役割を。 (p. 94)
代表制の理論家が提示する選挙区の規模に関する基準は、国土の生物物理学的条件をほとんど無視している。ミシェル・フーコ—が指摘したように、主権は伝統的に特定の地或の住民に法律を課すことにかかわってきたというのに、その地域の肥沃度、気候、人口密度などは、政治的議論における「変数」の一つにすぎなかったのである。実際のところ、選挙区の線引きはさまざまな歴史的、政治的偶然の結果である。 (p. 95-6)
代表制政府は、責任の時間的長さの問題に適切に応えることができない。なぜなら、近代民主主義は一種の「近視眼」的症状をわずらってきたからだ。貴族階級にたいする反抗から生まれた近代民主主義は、「現在の権利」に価値をおく。そして「予め決められた時間性のなかに閉じこめられる」ことを拒否する。あからさまな言い方になるが、選挙の投票日という切迫した時間制限を弱みにもつ政治家は、政治的なリスクをはらむ変化を、それも将来の有権者のためだけに検討することにはしりごみをする。なぜ将来の世代や動物の利益のことを考えないのかと問われたある政治家は、ためらいもなくこう答えた「彼らは投票してくれないからね」。 (p. 101)
それは代表制民主主義という制度の問題とのみ考えることはできない。たとえば、「政党のプログラムを通じて代表制のシステムのなかに未来を組みこむ」ような「長期的な視野をもっとも鮮明に打ち出している党」 (p. 102) として緑の党がある。その緑の党は必ずしも望まれたような状況にあるわけではない。
どの国でも国政選挙で緑の党の得票が二〇%を超えたことはない。この党の知名度が高い国でも、得票率はせいぜい五%から一二%である。どこでも「現在主義」の票とバランスを取るほどの人気を得るレベルにはいたっていない。つまり、四〇年かかつて緑の党のプログラムは大衆のほんの限られた反応しか得られていないことになる。 (p. 102)
代表制度で政権を目指すとなると、当然のことながらそのほかの教育、防衛、社会保障の改革などの大きなテーマについても政策決定を迫られる、という点である。そこには代表制システムの「近視眼」的わなが待ち受けており、「現在」優先の手法にからめとられてしまう。連立内閣の閣僚は連立の最重要課題を守らなければならない。戦争が勃発する、失業率が急上昇するといった現在の問題には緊急性がある。こうした問題は、組織が結びつきより分裂に走りやすい緑の党の内部に亀裂を引き起こすことになる。 (p. 104)
緑の党が掲げるような「未来における人類の利益」は、近代民主主義の政治システムが保証すると称する「個人の自由と利益の追求」とは折り合いが悪い。近代民主主義イデオロギーをマジョリティが信じている限り、緑の党が支持を広げることは困難に見える。近代イデオロギーが個人の利益の無限の拡大を保証するためには、地球上の生物圏の消失に対しては手をこまねいているしかできないのである。
著者は、こうした深刻な環境問題を解決するため「エコ・デモクラシー」なるものを提案しているが、これは代表制民主主義に取って代わるべき新しい民主主義を提案しているというわけではない。
アントニオ・ネグリとマイケル・ハートは、こうした「近代性(モダニティ)」が抱える根源的な問題に対して、マルチチュードの反乱を通じて「反近代性」を乗りこえて「他の近代性(オルター・モダニティ)」を模索しようとしている [1] が、エコ・デモクラシーは、そのような「他の民主主義(オルター・デモクラシー)」ではけっしてない。
1 エコ・デモクラシーは自然を非還元的な問題としてとりあつかう。環境現象のアイデンティティそのものを重視し、その現象を尊重する必要性を説く行動主体(アクター)に発言権を与える。
2 理想的には、こうしたグル—プの活動領域は環境問題の地域的規模に合った順応性が求められる。
3 未来の世代および国境の外にいる人びとにたいして機能しにくい代表制にかわり、エコ・デモクラシーは、すでに国際的な視野をもち「世代を超えて協力しあえる取り組み」に貢献できる活動を展開するアクターを活用する。 (p.106)
現在の民主主義に長期的視野をとりもどすための仕組みを一覧にまとめることは可能だが、まずは、代表制度の短期的視野を修正するための措置を四つのタイプに大別してみよう。①憲法に環境上の配慮を導人すること、②国家の定義とその国有財産管理機能の拡大、③「未来アカデミー」の創設、④参加型プロセスの展開。国家の国有財産管理機能、「未来アカデミー」の創設、参加型プロセスの導入を柱とする憲法の再検討というアプローチも可能である。さらにそこに、「新しい上院」の創設もつけ加えたい。 (p. 124)
アクターとして環境問題を知悉する環境NGOを利用する「熟議民主主義」を提案しているのである。つまり、代表制民主主義を温存しつつ、そこに環境NGOが主体となるような「未来アカデミー」を創設して視野狭窄的な代表制民主主義を補佐しようというのである。新しい上院は、未来アカデミーの提案の実現を保証するためのものだが、ここで想定されているのは「環境の世界共有財産」 (p. 125) に敵対するような法案に対して拒否権を持つというようなことである。
ユルゲン・ハーバーマス流の熟議民主主義がどれほど有効であるのかは、なかなかに判定は難しい。ネグリ&ハートの思想に比べれば、それは明らかに現在の政治状況にとって受け入れやすい改良主義のように見える。
京都議定書をけっして受け入れないアメリカ合州国が、京都議定書を超える要求をするに違いない「エコ・デモクラシー」に基づく諸制度を受け入れる国家になるとは考えにくいし、多くの工業後進国家は、先進国同様の自然略奪の権限を主張して憚らない状況もある。
とはいえ、私たちは代表制民主主義に代わるべきオルター・デモクラシーのモデルをまだ持ってはいない。多くの困難が自明であっても、「エコ・デモクラシー」の実現に向うしか、さしあたっての道はないようだ。
環境問題は、地球という自然観の問題そのものであり、近代性が否応なく抱えた政治システムの問題そのものでもあるが、一方で個々人の生き方というミクロなレベルの問題とも直結している。
自然なものの美と完全さへの感性を保ちつづければ、そうした自然を消費したり変貌させたりすることに抵抗すべき理由はおのずと見えてくると考える。……限りなく欲望を追求するのではなく、抑制、節度、簡潔さといった価値観こそが、好ましく優れた人間の生活の基礎になるべきだと真剣に考える。彼らの自由の概念は、利己主義やわがままとは無縁である。 (p. 143)
気候、生物多様性といった新しい公共財産――実際には手に取ることのできないものだが――を個人の自由裁おと競争原理から断ち切り、市場に依存しない、集団的で共通の新たな論理を見出さないかぎり、富を長期にわたって生産し、その恩恵に浴しつづけることは不可能である。資源の希少化は遠からず、国際協調か、それとも全人類を巻こむ戦争か、という選択肢を突きつけることになるだろう。 (p. 146-7)
[1] アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート(水嶋一憲監訳、幾島幸子、古賀祥子訳)『コモンウェルス』(NHK出版、2012年)。










