
マーケティング研究 他社事例 409 「減る人手の解消に、AIが本当になるのか?1」 ~AIが奪う仕事!?~
結論から申し上げて、AIによる自動化の実現=社会全体の人手不足の解消にはならないという事です。
自動化出来たとしても、その影響で新たな仕事が生まれる場合があるからです。
例えば、エレベーターガールの仕事は今でも時折デパートで目にするものの、基本的には無くなる仕事と言えます。
これは自動化の犠牲とも言えると思います。
一方で、エレベーターの自動運転化により、エレベーター運行システムの開発や管理のような仕事が新たに生まれたというのも事実です。
ただし、新たな仕事はデパートの中では無く、エレベーター製造会社や保守点検会社といった別の場所で生まれているのです。
広い範囲における自動化のインパクトを知るには、その自動化技術により「奪う仕事」と「生む仕事」の両面があることを、業界にとらわれない視点で幅広く見なければなりません。
つまり、AIによる自動化が進展しても、それが直ちに「社会全体の仕事の減少」とは言えない訳です。
もしAIに奪われる仕事の数を、新たに生まれる仕事の数が上回れば、世間のAI脅威論は「脅威」ではなくなるという考え方です。
この考え方は、少々乱暴な所もありますが、仕事の量の総数と考えれば、理解できるところであり、仕事の種類といった観点から考えれば、歓迎される仕事となっていないかもしれません。
国の発展段階による制度や統治スタイルなどの変化を分析した「国家はなぜ衰退するのか」を著したマサチューセッツ工科大学(MIT)のダロン・アセモグル教授は「消える仕事と新たな仕事」という視点を重視して過去のアメリカ経済を分析しました。
アセモグル教授らは、過去30年間のアメリカデータを分析した結果、「自動化(具体的には、工場への産業用ロボット導入)により生まれる仕事より、消える仕事の方が多かった」と結論づけたのでした。
ところが、ドイツについて同様の分析をしたヴィルツブルグ大学助教授のウォルフガング・ダースらの論文(ロボットに適応する)では、アメリカとは対照的な結果が報告されているようです。
ダース助教授の論文では「ドイツでは1994年~2014年の20年間、労働者1000人あたりのロボット導入数がヨーロッパ平均の2倍、アメリカの4倍多かったにもかかわらず、製造業の雇用はアメリカほど減少せず依然として25%のシェアがあった」と記されています。
上記を受けて、アメリカエール大学の伊神准教授は以下の様に解説しています。
これらの分析は、扱う対象やマクロデータの性質上、因果関係の識別でツメが甘い傾向があります。
そのため、「過去30年間のアメリカのデータに見られた相関関係が、同時期のドイツのデータでは見られなかった」という程度に理解しておく方が安全である事。
ロボットの導入と仕事の増減のどちらかが原因でどちらが結果なのかが厳密に証明できたわけではなく、単に2つがほぼ同時に起こったことを示したに過ぎません。
それでも、2つの検証が「自動化の進展はすべからく人間から仕事を奪うわけではなく、消える仕事が、新たに生まれた仕事より多い場合もあれば、その逆もある」という事実を示している事になります。
(続く)
「リーダーシップ研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。
経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。
彩りプロジェクトでは、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。
研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。
保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。
また、貴社に伺って行う研修を40,000円(1h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、金融支援を必要とする企業の経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
また、「早期経営改善計画策定支援事業」は、同様に策定する際の費用の2/3補助があり、上限は20万円です。
こちらの「早期経営改善計画策定支援制度」は金融支援を要しないものですので、容易に取得しやすいのが特徴です。
メリットとして、金融機関との信頼関係を構築する為の制度としては有用です。
なぜなら、経営内容を開示する事、計画進捗のモニタリングを金融機関に報告する事は、金融機関が企業を評価する際に「事業性の評価」をしやすくなります。
金融機関は担保に頼らずに融資するには、「事業性の評価」が不可欠です。
「事業性の評価」とは、金融機関がその企業の事業を理解する事です。
「事業性の評価」に積極的な金融機関とそうではない金融機関がありますが、これからの金融機関とのお付き合いの仕方として、有用な制度となりますので是非ご利用下さい。
※このような方(会社)におすすめです。(中小企業庁資料より)
・ここのところ、資金繰りが不安定だ
・よくわからないが売上げが減少している
・自社の状況を客観的に把握したい
・専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい
・経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
→ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。
結論から申し上げて、AIによる自動化の実現=社会全体の人手不足の解消にはならないという事です。
自動化出来たとしても、その影響で新たな仕事が生まれる場合があるからです。
例えば、エレベーターガールの仕事は今でも時折デパートで目にするものの、基本的には無くなる仕事と言えます。
これは自動化の犠牲とも言えると思います。
一方で、エレベーターの自動運転化により、エレベーター運行システムの開発や管理のような仕事が新たに生まれたというのも事実です。
ただし、新たな仕事はデパートの中では無く、エレベーター製造会社や保守点検会社といった別の場所で生まれているのです。
広い範囲における自動化のインパクトを知るには、その自動化技術により「奪う仕事」と「生む仕事」の両面があることを、業界にとらわれない視点で幅広く見なければなりません。
つまり、AIによる自動化が進展しても、それが直ちに「社会全体の仕事の減少」とは言えない訳です。
もしAIに奪われる仕事の数を、新たに生まれる仕事の数が上回れば、世間のAI脅威論は「脅威」ではなくなるという考え方です。
この考え方は、少々乱暴な所もありますが、仕事の量の総数と考えれば、理解できるところであり、仕事の種類といった観点から考えれば、歓迎される仕事となっていないかもしれません。
国の発展段階による制度や統治スタイルなどの変化を分析した「国家はなぜ衰退するのか」を著したマサチューセッツ工科大学(MIT)のダロン・アセモグル教授は「消える仕事と新たな仕事」という視点を重視して過去のアメリカ経済を分析しました。
アセモグル教授らは、過去30年間のアメリカデータを分析した結果、「自動化(具体的には、工場への産業用ロボット導入)により生まれる仕事より、消える仕事の方が多かった」と結論づけたのでした。
ところが、ドイツについて同様の分析をしたヴィルツブルグ大学助教授のウォルフガング・ダースらの論文(ロボットに適応する)では、アメリカとは対照的な結果が報告されているようです。
ダース助教授の論文では「ドイツでは1994年~2014年の20年間、労働者1000人あたりのロボット導入数がヨーロッパ平均の2倍、アメリカの4倍多かったにもかかわらず、製造業の雇用はアメリカほど減少せず依然として25%のシェアがあった」と記されています。
上記を受けて、アメリカエール大学の伊神准教授は以下の様に解説しています。
これらの分析は、扱う対象やマクロデータの性質上、因果関係の識別でツメが甘い傾向があります。
そのため、「過去30年間のアメリカのデータに見られた相関関係が、同時期のドイツのデータでは見られなかった」という程度に理解しておく方が安全である事。
ロボットの導入と仕事の増減のどちらかが原因でどちらが結果なのかが厳密に証明できたわけではなく、単に2つがほぼ同時に起こったことを示したに過ぎません。
それでも、2つの検証が「自動化の進展はすべからく人間から仕事を奪うわけではなく、消える仕事が、新たに生まれた仕事より多い場合もあれば、その逆もある」という事実を示している事になります。
(続く)
「リーダーシップ研修」、「未来を創るワークショップ研修」等、各企業の課題に合わせた研修をご提案差し上げます。
経営の根幹は「人」です。働く人次第で成果が変わります。自分事で働く社員を増やし、価値観を同じくし働く事で働きがいも増します。
彩りプロジェクトでは、製造メーカー、商社、小売業者、社会福祉法人、NPO法人等での研修実績があります。
研修と一言と言っても、こちらの考え方を一方的に押し付ける事はしません。実感いただき、改善課題を各自が見つけられる様な研修をカスタマイズしご提案しているのが、彩りプロジェクトの特徴です。
保育園・幼稚園へご提供している研修【私の保育園】【私の幼稚園】は大変ご好評をいただいています。
また、貴社に伺って行う研修を40,000円(1h)からご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣
現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、金融支援を必要とする企業の経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。
また、「早期経営改善計画策定支援事業」は、同様に策定する際の費用の2/3補助があり、上限は20万円です。
こちらの「早期経営改善計画策定支援制度」は金融支援を要しないものですので、容易に取得しやすいのが特徴です。
メリットとして、金融機関との信頼関係を構築する為の制度としては有用です。
なぜなら、経営内容を開示する事、計画進捗のモニタリングを金融機関に報告する事は、金融機関が企業を評価する際に「事業性の評価」をしやすくなります。
金融機関は担保に頼らずに融資するには、「事業性の評価」が不可欠です。
「事業性の評価」とは、金融機関がその企業の事業を理解する事です。
「事業性の評価」に積極的な金融機関とそうではない金融機関がありますが、これからの金融機関とのお付き合いの仕方として、有用な制度となりますので是非ご利用下さい。
※このような方(会社)におすすめです。(中小企業庁資料より)
・ここのところ、資金繰りが不安定だ
・よくわからないが売上げが減少している
・自社の状況を客観的に把握したい
・専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい
・経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。
彩りプロジェクトは認定支援機関です(関財金1第492号)
経営革新等支援機関とは、「経営改善、事業計画を策定したい」「自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい」「取引先、販路を増やしたい」「返済猶予、銀行交渉のことを知りたい」
「事業承継に関して、代表者の個人補償をどうにかしたいんだけど・・・」
というお悩みを始め、中小企業経営者を支援するために国が認定した公的な支援機関の事です。
お気軽にご相談下さい。
当、彩りプロジェクトでは30分無料相談を実施しています。
どのような支援が受けられるのかだけでも、一度お聞きになって下さい。
→ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
HPの申込フォームから(こちらから)どうぞ。










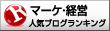

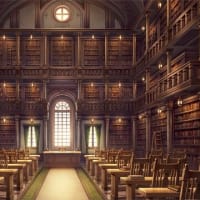






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます