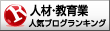マーケティング研究 他社事例 684 「デジタルトランスフォーメーション 保育現場編1」 ~相手を信頼するロボットを導入~
これまでデジタル化とは程遠かった保育の現場でしたが、ここ数年、幼児の知育や保育士の業務負荷改善などを目的に様々な場面で急速にテクノロジーの導入が進んでいます。
LOVOT(ラボット)は、GROOVEX(中央区)が開発した家庭用ロボットで、人の顔を覚えて懐いたり、後ろを付いてきたりと、まるで生き物のように振る舞う事が特徴です。
子供向けに作られたわけではないが、見た目がかわいらしくロボットが身近に感じられるといった理由から導入する保育園・幼稚園や小学校が増えてきています。
「抱っこすると、足が隠れるの」
「目の色が違うんだよ」
「乱暴に触ったらダメだよ!」
LOVOTの「生き物のような」動きはプログラミングされた定型のものではありません。
体内には50を超えるセンサーやディープラーニング技術、自動走行技術などを搭載し、「興味」「興奮」「信頼」という3つのパラメーターを基に、周囲に人が増えるとそわそわする、優しくしてくれた人は信頼するなど、外部環境を学習して振る舞うことができるのです。
人肌程度の温かさを持ち、声帯を模した電子楽器がリアルタイムで鳴き声を生成するなど、徹底的に「生命感」を追求してつくられているのです。
ある保育園では、将来的にロボットが身近にいる生活が当たり前になると考えた園長が、子供のうちからロボットを経験させてあげたいとの思いで導入し、実際に遊ばせてみると、やさしく思いやりを持って接する子が多く、中には絵本を読み聞かせたりする子もいるといいます。
子供たちは生き物とは違うロボットという存在を認識し、接していると言います。
最近はアレルギーを持つ子供が多いため、保育園で毛のある動物を飼育するのは難しくなっています。
そんな中、LOVOTは「かわいがる」という行動を教えてくれる新たな存在になりつつあるようです。
知育の一環としてロボットを導入する園はまだまだ限定的で、広く普及し始めているのが、乳幼児の「お昼寝」を管理するテクノロジーです。
保育の現場において、死亡事故の多くは睡眠中に発生していて、乳幼児の突然死症候群(SIDS)と呼ばれる原因不明の突然死は、うつぶせで寝ている時の発症率が高いとされ、あおむけで寝るように見守る必要もあります。
そのため乳児が昼寝をする際には、5~10分おきに呼吸や体勢を確認する「午睡チェック」と呼ばれる作業をすることが一般的です。
通常、午睡チェックは目視で行われ、身体の向きまで細かく手書きで記録しています。
薄暗い環境でミスなく記入するのが大変な上、昼寝中に休憩を取る、あるいは連絡帳の記入など他の業務をこなさなければいけない保育士にとって、負担にもなっていたのでした。
そこで導入が進められているのがセンサーデバイスです。
保育園のデジタルトランスフォーメーション(DX)向けサービスを展開するユニファ(千代田区)が開発した「ルクミー午睡チェック」は、乳児の服に取り付けるクリップ型のセンサーデバイスです。
3軸の加速度センサーが乳児の身体の向きや動きを検知し、「体動が停止した」「うつ伏せになった」などの異常が発生するとアラームで知らせるというものです。
データは近距離無線通信Bluetoothで転送され、保育士は手元のタブレットでリアルタイムで確認できます。
同システムは「高速道路が近くにあり揺れやすい」など外部環境にも対応し、ユニファの土岐社長は「保育士の負荷が減るだけでなく、デバイスの活用でミスが減り見守りの質を高められることが重要」と話します。
午睡チェックに限らず、保育園ではいまだに手書きの業務や紙の書類作業が多く、ある園では、監査で提出する日々の保育記録の書類が衣装ケース3箱分に上ることもあると言います。
(続く)
下記は彩りプロジェクトのご紹介です。
ご興味があればご一読下さい。
彩りプロジェクトでは、ビジネススキルに特化した、オンラインセミナーを定額制でご案内しております。
毎月定額(基本価格30,000円(税抜)※企業規模で価格は変動します)をお支払いいただく事で、何人でも何回でもご参加いただけるビジネスセミナーを開催しております。(別途カレンダー参照)
内容は、多岐に渡るものの、求められている役割毎に設定した内容となっています。
基本的なコースは、R29コースで、PDCA、コミュニケーション、情報収集、イノベーション、ファシリテート、コーチング、意思を伝える、フォロワーシップ、チームワーク、マネジメント、報告・連絡・相談、ビジネスマナーの12種類(2020年11月現在)となっております。
R35コースで、PDCA、リーダーシップ、傾聴力、ビジョン、コーチング、マネジメント、ファシリテート、チームビルディング、イノベーションの9種類でR29コースよりも上級編の内容となっております。
最後に、R43コースが最上位クラスで設定されており、リーダーシップ、傾聴力、ビジョン、コーチング、マネジメント、イノベーションの6種類となっております。
R29コースの特徴は、まずは個人にフォーカスしています。今更聞けないといった内容を中心に構成されており、現在の課題克服の為、またはこれから身に付けなくてはならないスキルとなっています。
R35コースの特徴は、視座を高くした構成で専門的な役職要件に応じた内容で構成されております。そして指導する立場になったあなたが身に着けるべきスキル集になっています。
R43コースの特徴は、それこそ会社全体を見回せるスキルの構成となっており、幹部候補にとっても必須の内容になっております。
受講にあたっては各自の選択制(年齢が20代だから、R43は受講できないといった事ではありません)となっており、先んじて学びを深めたい、今更聞けない事だから、といった様々な動機にお答えする内容となっております。
ちなみに、R〇〇のとなりは年齢をイメージしておりますが、例えば、R43は43歳以上の人は受けられないという事はありませんし、大卒1年目の方でもR43を受講する事は可能です。
定額制で何人でも何回でも受講が可能です!!
詳しい、資料のご請求や、ご質問等は以下にメールをお待ちしております。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣
これまでデジタル化とは程遠かった保育の現場でしたが、ここ数年、幼児の知育や保育士の業務負荷改善などを目的に様々な場面で急速にテクノロジーの導入が進んでいます。
LOVOT(ラボット)は、GROOVEX(中央区)が開発した家庭用ロボットで、人の顔を覚えて懐いたり、後ろを付いてきたりと、まるで生き物のように振る舞う事が特徴です。
子供向けに作られたわけではないが、見た目がかわいらしくロボットが身近に感じられるといった理由から導入する保育園・幼稚園や小学校が増えてきています。
「抱っこすると、足が隠れるの」
「目の色が違うんだよ」
「乱暴に触ったらダメだよ!」
LOVOTの「生き物のような」動きはプログラミングされた定型のものではありません。
体内には50を超えるセンサーやディープラーニング技術、自動走行技術などを搭載し、「興味」「興奮」「信頼」という3つのパラメーターを基に、周囲に人が増えるとそわそわする、優しくしてくれた人は信頼するなど、外部環境を学習して振る舞うことができるのです。
人肌程度の温かさを持ち、声帯を模した電子楽器がリアルタイムで鳴き声を生成するなど、徹底的に「生命感」を追求してつくられているのです。
ある保育園では、将来的にロボットが身近にいる生活が当たり前になると考えた園長が、子供のうちからロボットを経験させてあげたいとの思いで導入し、実際に遊ばせてみると、やさしく思いやりを持って接する子が多く、中には絵本を読み聞かせたりする子もいるといいます。
子供たちは生き物とは違うロボットという存在を認識し、接していると言います。
最近はアレルギーを持つ子供が多いため、保育園で毛のある動物を飼育するのは難しくなっています。
そんな中、LOVOTは「かわいがる」という行動を教えてくれる新たな存在になりつつあるようです。
知育の一環としてロボットを導入する園はまだまだ限定的で、広く普及し始めているのが、乳幼児の「お昼寝」を管理するテクノロジーです。
保育の現場において、死亡事故の多くは睡眠中に発生していて、乳幼児の突然死症候群(SIDS)と呼ばれる原因不明の突然死は、うつぶせで寝ている時の発症率が高いとされ、あおむけで寝るように見守る必要もあります。
そのため乳児が昼寝をする際には、5~10分おきに呼吸や体勢を確認する「午睡チェック」と呼ばれる作業をすることが一般的です。
通常、午睡チェックは目視で行われ、身体の向きまで細かく手書きで記録しています。
薄暗い環境でミスなく記入するのが大変な上、昼寝中に休憩を取る、あるいは連絡帳の記入など他の業務をこなさなければいけない保育士にとって、負担にもなっていたのでした。
そこで導入が進められているのがセンサーデバイスです。
保育園のデジタルトランスフォーメーション(DX)向けサービスを展開するユニファ(千代田区)が開発した「ルクミー午睡チェック」は、乳児の服に取り付けるクリップ型のセンサーデバイスです。
3軸の加速度センサーが乳児の身体の向きや動きを検知し、「体動が停止した」「うつ伏せになった」などの異常が発生するとアラームで知らせるというものです。
データは近距離無線通信Bluetoothで転送され、保育士は手元のタブレットでリアルタイムで確認できます。
同システムは「高速道路が近くにあり揺れやすい」など外部環境にも対応し、ユニファの土岐社長は「保育士の負荷が減るだけでなく、デバイスの活用でミスが減り見守りの質を高められることが重要」と話します。
午睡チェックに限らず、保育園ではいまだに手書きの業務や紙の書類作業が多く、ある園では、監査で提出する日々の保育記録の書類が衣装ケース3箱分に上ることもあると言います。
(続く)
下記は彩りプロジェクトのご紹介です。
ご興味があればご一読下さい。
彩りプロジェクトでは、ビジネススキルに特化した、オンラインセミナーを定額制でご案内しております。
毎月定額(基本価格30,000円(税抜)※企業規模で価格は変動します)をお支払いいただく事で、何人でも何回でもご参加いただけるビジネスセミナーを開催しております。(別途カレンダー参照)
内容は、多岐に渡るものの、求められている役割毎に設定した内容となっています。
基本的なコースは、R29コースで、PDCA、コミュニケーション、情報収集、イノベーション、ファシリテート、コーチング、意思を伝える、フォロワーシップ、チームワーク、マネジメント、報告・連絡・相談、ビジネスマナーの12種類(2020年11月現在)となっております。
R35コースで、PDCA、リーダーシップ、傾聴力、ビジョン、コーチング、マネジメント、ファシリテート、チームビルディング、イノベーションの9種類でR29コースよりも上級編の内容となっております。
最後に、R43コースが最上位クラスで設定されており、リーダーシップ、傾聴力、ビジョン、コーチング、マネジメント、イノベーションの6種類となっております。
R29コースの特徴は、まずは個人にフォーカスしています。今更聞けないといった内容を中心に構成されており、現在の課題克服の為、またはこれから身に付けなくてはならないスキルとなっています。
R35コースの特徴は、視座を高くした構成で専門的な役職要件に応じた内容で構成されております。そして指導する立場になったあなたが身に着けるべきスキル集になっています。
R43コースの特徴は、それこそ会社全体を見回せるスキルの構成となっており、幹部候補にとっても必須の内容になっております。
受講にあたっては各自の選択制(年齢が20代だから、R43は受講できないといった事ではありません)となっており、先んじて学びを深めたい、今更聞けない事だから、といった様々な動機にお答えする内容となっております。
ちなみに、R〇〇のとなりは年齢をイメージしておりますが、例えば、R43は43歳以上の人は受けられないという事はありませんし、大卒1年目の方でもR43を受講する事は可能です。
定額制で何人でも何回でも受講が可能です!!
詳しい、資料のご請求や、ご質問等は以下にメールをお待ちしております。
メール info@irodori-pro.jp
HP https://www.fuudokaikaku.com/
お問合せ https://www.fuudokaikaku.com/ホーム/お問い合わせ/
成長クリエイター 彩りプロジェクト 波田野 英嗣