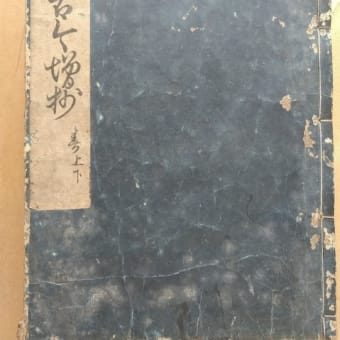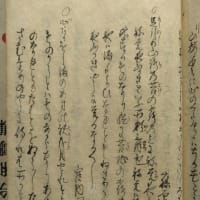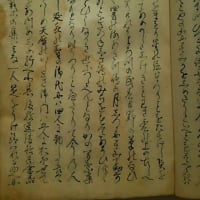をぢさせ給へる御けしきを、こゝろもなき
ことけいしてけりと思ひて、くはしくもそ
孟点によにん孟浮舟
のほどのことをばいひさしつ。其女人この
をさして僧都の詞也
たびまかり出侍つるたよりに、小野に侍
とぶら
るあまどもあひ吊ひ侍らんとて、まかり
すけ
よりたりしに、なく/\出家のこゝろざし
ふかきよし、ねんごろにかたらひ侍しかば、か
しらおろし侍りにき。なにがしがいもうと、
こ師小野尼の夫誰ともなし
故衞門のかみのめに侍し尼なん、うせにし
をんな抄中将のもとの執尼君のむすめ也
女ごのかはりにと、思よろこび侍りて、ずい
ぶんにいたはりかしづき侍けるを、かくなりに
たれば、うらみ侍なり。げにぞかたちはいと
頭注
おぢさせ給へる御けしきを
抄中宮の御氣色をいか
がと僧都の思ひて委も
申さぬ也。
うせにし女ごのかはりにと
思ひよろこび 宇治にて
浮舟をひろひてよろこ
びし事なり。
かくなりにたればうらみ
侍るなり 師手習君
の尼に成し後僧都はい
まだ小野の尼には對面

頭注
なし。傳聞たるにや。
うるはしくけうらにて、をこなひやつれん
もいとおしげになん侍しなにびとにか侍
りけんと、物よくいふ僧都にて、かたりつゞ
小宰相詞
け申給へば、いかでさる所に、よき人をしも
誰人としれんと也
とりもていきけん。さりとも今はしられ
孟僧都の詞
ぬらんなど、此宰相の君ぞとふ。しらずさ
孟さる人ならば
もやかたらひ侍らん。まことにやむごとな
きこえんにさもなきは田舎人のむすめかと也
き人ならば、なにかくれも侍らじをや。ゐ
細きはめて田舎人の中にもよき人あると也
中人゙のむすめも、さるさましたるこそは侍
らめ。りうの中より、仏むまれ給はずはこ
そ侍らめ。たゞ人にては、つみかろきさまの
人になん侍りけるなどきこえ給。その
頭注
此宰相の君ぞとふ 三ちと
思ひ合する所ありて此宰
相ノ君よく/\問る也。かくて
薫の聞傳へる也。
しらずさもや 細僧都の
詞也。宰相が詞に今はし
られぬらんといひしに
さもやあるらんとこ
へ給ふ也。
りうの中より 孟僧都
の詞。龍女成仏の事也。
師龍女成仏のためしも
あればゐ中人の女など
もさるさましたるも
有べしと也。

頭注
つみかろきさまの人 細忍辱の人端正なる人に生ると也。師名義集ニ●堤奏ニハ言
忍辱ト瞋恚憂愁疑婬欲驕慢諸ノ邪見等能忍ンテ不ル動サ是ヲ名ク法忍ト。やごとなき
人ならば勿論也。しからずばいかばかりの戒行にてかゝる形に生れけんと也。
ころかのわたりにきえうせにけんひとを
哢小宰相也 哢中君のあたりよ
おぼしいづ。この御まへなる人もあねぎみの
りきゝしと也 俄にうせしと浮舟の事をきゝし也
つたへに、あやしくてうせたる人とはきゝを
きたればそれにやあらんとは思ひけれど、さ
たしかにはさだめがたしと也 是も小宰相が心中也 孟浮舟の人に
だめなきことなり。僧都も、かゝる人世にある
しられじとすると也
ものともしられじと、よくもあらぬかた
きだちたる人もあるやうにおもむけて、か
浮舟の也
くし忍び侍るを、ことのさまのあやしけれ
僧都のいひし事を小宰相がおもふ心也
ば、けいし侍るなりとなまがくすけしき
孟明石中宮の詞也 孟浮舟に
なれば、ひとにもかたらず。みやはそれにも
頭注
その比かのわたり
細浮舟の事なるべしと
中宮の思ひより給へり。
よくもあらぬかたきだちた
る人もあるやうにおもむけ
て 師浮舟の身によから
ぬ敵やうの物もあるやう
におもむけいひて浮舟のよ
くもあらはさず隠し忍ぶを
彼宇治にて見しよりは
じめて事のさまあやしく
珍しき事なれば中宮に
物語申たると僧都のいひ
てと也。
なまがくすけしきなれ
ば 僧都のかくさまほし
げなるけしきなれば小
宰相も遠慮して人
にかたらぬ也。

やとおぼしめす也。薫也 細小宰相也
こそあれ。大将にきかせばやと、この人にぞ
中宮の心也。薫も浮舟も也
の給はすれど、いづかたにもかくすべきことを
さだめて、さならんともしらずながらはづ
薫をさしていへり
かしげなる人に、うち出の給はせんもつゝ
女一宮なり。孟御木復にて
ましくおぼしてやみにけり。姫宮をこたり
僧都歸山也 小野へ也
はてさせ給て、そうづものぼりぬ。かしこに
孟尼君の僧都をうらみ給ふ也 若き女の
より給へれば、いみじくうらみて、なか/\か
出家は末もとり給ふまじければと也 僧都の
かる御有樣にて、つみもえぬべきことを、の給
尼公に談合もし給はでと也
ひもあはせずなりにけることをなん。いとあ
細僧都の詞也。抄手習
やしきなどの給へどかひなし。いまはたゞ御
へ僧都のいふ也
をこなひをし給へ。老たるわかきさだめな
き世なり。はかなき物におぼしとりたるも
頭注
宮はそれにもこそあれ
師もしかほるのうしな
ひし人にやあるらん
きかせはやと小宰相
に仰らるゝ也。
さだめてさならんともしら
ずながら 髄に治定し
て其浮舟ならんともし
らずながらと中宮の心也。
はづかしげなる人に
抄薫の事也。明石中宮
の御心也。小宰相には仰
せらえても直にはえのた
まはぬ也。
の給ひもあはず
抄尼公の歸り給はんを
まちて談合あるべき事
と也。
はかなき物に 細すで
に宇治にてなき人と

頭注
思ひし御身なればなき
物に思ひなし給ふ理り
と也。
怖ぢさせ給へる御氣色を、心も無き事啓してけりと思ひて、委しく
もその程の事をば言ひさしつ。
「その女人、この度罷り出で侍りつる便りに、小野に侍る尼どもあ
ひ訪ひ侍らんとて、罷り寄りたりしに、泣く泣く出家の志深き由、
懇ろに語らひ侍りしかば、頭下し侍りにき。某が妹、故衞門の督の
妻(め)に侍りし尼なん、失せにし女子の代はりにと、思ひ喜び侍
りて、随分に労りかしづき侍りけるを、かくなりにたれば、怨み侍
るなり。げにぞ形姿はいと麗しくけうらにて、行ひやつれんも愛お
るなり。げにぞ形姿はいと麗しくけうらにて、行ひやつれんも愛お
しげになん侍し。何人にか侍りけん」と、物よく言ふ僧都にて、語
り続け申し給へば、
「如何でさる所に、よき人をしも取りもて行きけん。さりとも今は
知られぬらん」など、この宰相の君ぞ問ふ。
「知らず。さもや語らひ侍らん。真に止むごと無き人ならば、何隠
れも侍らじをや。田舎人の娘も、さる樣したるこそは侍らめ。龍の
中より、仏生まれ給はずはこそ侍らめ。ただ人にては、罪軽き樣の
人になん侍りける」など聞こえ給ふ。その比、彼のわたりに消え失
せにけん人をおぼし出づ。この御前なる人も姉君の伝へに、あやし
くて失せたる人とは、聞き置きたれば、それにやあらんとは思ひけ
れど、定め無き事なり。僧都も、
「かかる人、世にあるものとも知られじと、よくもあらぬ敵だちた
る人もあるやうにおもむけて、隠し忍び侍るを、事の樣のあやしけ
れば、啓し侍るなり」と、なま隠す氣色なれば、人にも語らず。宮
は、
は、
「それにもこそあれ。大将に聞かせばや」と、この人にぞ宣はすれ
ど、何方にも隠すべき事を定めて、然ならんとも知らずながら、恥
づかしげなる人に、打出で宣はせんも慎ましくおぼして止みにけり。
姫宮をこたり果てさせ給て、僧都も上りぬ。かしこに寄り給へれば、
いみじく恨みて、
「なかなか、かかる御有樣にて、罪も得ぬべき事を、宣ひも合はせ
ずなりにける事をなん。いとあやしき」など宣へど甲斐無し。
「今はただ、御行ひをし給へ。老たる若き定め無き世なり。儚き物
におぼし取りたるも、
※龍女成仏の事也
妙法蓮華経提婆達多品で、娑竭羅竜王の8歳の娘が,竜身・年少・女性という悪条件にもかかわらず,一瞬にして変成男子を遂げ,往生したこと。女人往生の根拠とされ,文学や美術のモティーフとなった。〈提婆達多品〉の載る巻5は悪人往生と女人往生の双方を説くことから,《法華経》のなかでも特に重視され,8巻を1巻ずつ講ずる〈法華八講〉の場でもその折に行道が行われたりした。
略語
※奥入 源氏奥入 藤原伊行
※孟 孟律抄 九条禅閣植通
※河 河海抄 四辻左大臣善成
※細 細流抄 西三条右大臣公条
※花 花鳥余情 一条禅閣兼良
※哢 哢花抄 牡丹花肖柏
※和 和秘抄 一条禅閣兼良
※明 明星抄 西三条右大臣公条
※珉 珉江入楚の一説 西三条実澄の説
※師 師(簑形如庵)の説
※拾 源注拾遺