精神障害を抱えた人のフットサルであるソーシャルフットボール、その第1回精神障がい者フットボールアジア大会「Dream Asia Cup」が2025年1月15~18日、大阪府堺市立大浜体育館にて開催され、4日間取材し記事を書いています。
単なる試合ではなく、人生を変える旅~ソーシャルフットボール「Dream Asia Cup」
https://www.paraphoto.org/?p=43445
精神障害を抱えた人のフットサルであるソーシャルフットボール、その第1回精神障がい者フットボールアジア大会「Dream Asia Cup」が2025年1月15~18日、大阪府堺市立大浜体育館にて開催され、4日間取材し記事を書いています。
単なる試合ではなく、人生を変える旅~ソーシャルフットボール「Dream Asia Cup」
https://www.paraphoto.org/?p=43445
先週(11月20日)、遅ればせながら「ぼくが生きてる、ふたつの世界」をやっと観た。
五十嵐大さんの原作「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」は3年ほど前に読んでおり、当然映画も観るつもりだったので映画に関する情報は極力入れないようにしていたが(観ると決めている映画に関しては先入観など持たないように情報を入れないようにしている)、漏れ聞こえる感想からも評判が良いということは伝わってきていた。
「ろう者役をろう者が演じていること」「ろう者スタッフの的確な指示と本人の努力もあって吉沢亮さんの手話もリアリティをもったものになったこと」「様々な家族を描いてきた呉美保監督が等身大の家族の話として昇華していること」等々。
実際観てもそう思ったし、付け加えるとすれば、映画全体のテンポ感が良く、母親役の忍足亜希子さんも予想以上に良かった。また夫役というか父親役の今井彰人さんとは何度か会って話したこともある(もちろん手話で)が、忍足さんとの年齢差を感じさせないよう、かなり工夫演出もされていた。
その翌々日、たまたま「名もなく貧しく美しく(1961年製作)」を再見した。高峰秀子生誕100年プロジェクトの一環として東京都写真美術館で上映されていたものだ。「ぼくが生きてる、ふたつの世界」との共通点は、ともにろう夫婦、コーダ(Children of Deaf Adults/聞こえない聞こえにくい親を持つ聴者の子ども)が描かれている点。
コーダの息子が、ろうの両親を拒絶する時期もあるが、最終的には受け入れていく様子も描かれている。その様が小学生の間に完結するので、現代から観れば少々類型的ではあるが。
「名もなく貧しく美しく」では、ろう夫婦を高峰秀子と小林桂樹が演じているが、この映画に向かって「ろう者役をろう者が演じていない」と批判してもあまり意味をなさないだろう。63年前にメジャーな映画でこの題材を取り扱ったこと自体が画期的であった。
高峰秀子の夫であり、この映画の監督・脚本松山善三は、フランスパリを訪れた際にフランス手話で会話するろう者たちを見たことが映画のきっかけになったという。私の記憶では、世界最古のろう学校であるパリ聾学校も訪れたのだと思う。
とは言え高峰秀子の口話が場面によって都合よく聞き取りやすかったり、そもそも補聴器もほぼない時代に口話があれだけ流暢であることは気になった。
ちなみにろう者を使い自主映画を作り続けた、ろう者の映画監督である深川勝三氏の第1作「楽しき日曜日」が制作されたのが前年の1960年だった。
表題にある「アイ・コンタクト」は私の監督作品。デフサッカー女子日本代表を描いたドキュメンタリー映画だ。
この3本の共通点は、聞こえない聞こえにくい人々を描いていることはもちろんだが、コーダが出ている点だ。
前2作は俳優が演じ、「アイ・コンタクト」はドキュメンタリーなので実際のコーダが出演している。
高校までろう学校に通っていたデフサッカー選手が、大学で初めて聴者の世界に触れ、その2つの世界の橋渡しをしてくれたのが、自身もサッカーをやっていたコーダの同級生だった。
コーダという言葉が、少し知られるようになったのは2009年10月刊行の「コーダの世界(澁谷智子著)」、それを読んで是非作品にも出てほしいと願い、出演してくれた。
彼は子供のときに親の通訳をするのは当たり前だったと語ってくれたが、その後出会ったコーダは親があえて手話を覚えさせず大人になって手話を学び始めたという人もおり、コーダといっても様々だ。
11月2~3日、電動車椅子サッカーの全国大会パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパンが開催され、記事を書きました。
ご一読ください。


パリパラリンピック ボッチャBC3のスケジュール。
時間はいずれも日本時間。 対戦相手、結果等書き足していきます。
( )内は国名とランキング
2位以上で準々決勝に進出。
個人戦の配信は有田、一戸選手ともに予選プール3試合は配信無し。
準々決勝はあるかも、準決勝は無し、決勝は有り、3位決定戦は男子は有り女子は無し だと思われます。
8月29日
21時~
男子個人戦 プールD 第1戦 有田正行(13位) VS CARVALHO Mateus(ブラジル・5位) Court 8
5-4 で逆転勝利(0-1, 3-0, 0-3, 2-0)
27時30分(翌3時30分)~
女子個人戦 プールD 第1戦 一戸彩音(13位) VS CALLUPE Niurka(ペルー・5位)Court 8
5-1で初戦勝利(1-0, 1-0, 3-0, 0-1)
30日
21時~
女子個人戦 プールD 第2戦 一戸彩音 VS NTENTA Anna(ギリシャ・4位) Court 5
8-0(3-0, 2-0, 1-0, 2-0)で勝利。これで2勝0敗、予選プールの2位以上が確定しベスト8進出決定!
28時40分(翌4時40分)~
男子個人戦 プールD 第2戦 有田正行 VS POLYCHRONIDIS Grigorios(ギリシャ・4位)Court 5
0-9(0-2, 0-3, 0,-3, 0-1 )の敗戦。
しかし次戦に勝てば2勝1敗で準々決勝進出決定。勝った方がベスト8。次戦も残念ながら配信無し。
31日
21時~
女子個人戦 プールD 第3戦 一戸彩音 VS FERRANDO Stefania(アルゼンチン・14位) Court 4
3-6(0-3, 3-0, 0-2, 0-1)で敗れ、プールD2勝1敗で2位通過。
24時~
男子個人戦 プールD 第3戦 有田正行 VS MENARD Jules(フランス・18位) Court 4
2-4(1-0, 0-3, 1-0, 0-1)で敗れ、プールD1勝2敗となり予選敗退。1勝2敗で並んだNTENTA Annaとの直接対決には勝っているので3位。
今後はペア戦に期待したい。
27時45分(翌3時45分)~
女子個人準々決勝 相手はプールC3連勝(7-0,6-1,7-0)で1位通過の韓国カン・スンヒ。残念ながら配信は無し
2-3(1-0, 1-0, 0-1, 0-2)と逆転で敗れ、ベスト4進出はならなかった。
以降、2人はペア戦に集中していくことになる。
9月
ペア戦の配信
1戦目あるかも、2戦目無し、準々決勝あるかも、準決勝あるかも、決勝はあり、3位決定戦もあります。
3日
24時~
ミックスペア 第1戦 有田・一戸ペア VS フランス Court 8 サブ配信あるかも
27時10分(翌3時10分)~
ミックスペア 第2戦 有田・一戸ペア VS オーストラリア Court 4 配信無し
4日
20時40分~
ミックスペア 準々決勝
27時10分(翌3時10分)~
ミックスペア 準決勝
5日
20時40分~
ミックスペア 3位決定戦
28時(翌4時)~
ミックスペア 決勝
有田正行選手、ランプオぺレーター妻の千穂さんのパリパラリンピックに至るまでの軌跡はこちらの映像をどうぞ
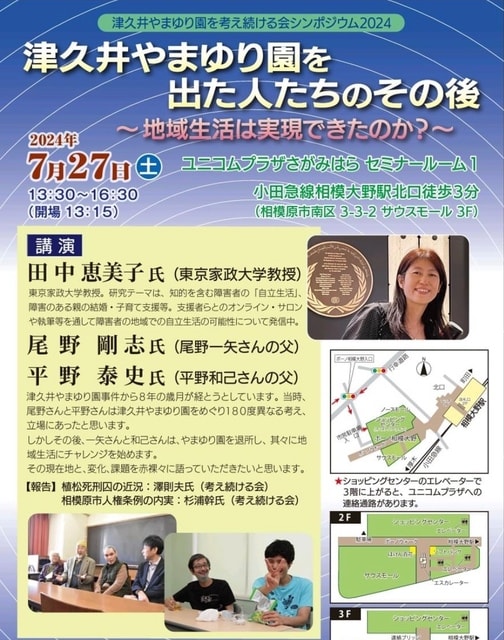

東京都の青鳥特別支援学校が、知的障害の特別支援学校としては(ろう学校は以前出場したことがある)、初の単独チームでの甲子園大会予選出場となった歴史的な一戦を生観戦した。
そもそもこの試合のことはNHKの報道で知ったのだが、映像を見た際、おそらくコールド負けするだろうなというチーム力にしか見えず、「何でいきなり硬式? 軟式じゃダメなの?」もっと言えば(元高校球児としては)「硬式なめんなよ」と疑問がわき、まずは青鳥野球部久保田監督の著書を2冊、先月出たばかりの新刊「待ってろ甲子園(日比野恭三)」を読んで久保田監督の並並なら思いを知り、とにかく歴史的な一戦を観ておこうと猛暑の中、八王子の球場まで行ってきた。
久保田監督の思いをごくごく簡単にまとめると、大学まで硬式野球をやっていた久保田監督は高校野球の監督になろうと教職についたが養護学校(現在の知的障害の特別支援学校)へ配属。失意の後、ソフトボールの強豪チームを作り上げたり、社会人野球のコーチや監督を務めたものの、退職前に甲子園へつながる硬式野球部をなんとか設立しようということで現在に至る。
14時試合開始の予定だったがプレイボールは15時20分。14時前後に比べると暑さは若干和らいだがまだまだクソ暑い。
先攻は東村山西高校。青鳥の先発は3年生首藤理仁、捕手は2年生左利きの後藤浩太。キャッチャーの人選にも苦労があったようだ。
並みの守備力のチームであれば、ライトフライ、ピッチャーゴロ、サードゴロで三者凡退となるところだったが、実際は3人終えた時点で2失点。なんとか4番の外野フライはレフト熊谷がグラブにおさめて1アウト。続く5番は岩本へのショートライナーで2アウト!観客席からは拍手喝采!
しかしその後ヒットやエラー、盗塁が続き、初回に11点を取られてしまう。しかし首藤は四球を1個も出さず、スリーアウト目はレフト熊谷への外野フライだった。
1回裏青鳥の攻撃は先頭打者岩本がライト前クリーンヒットを放つ! 塁上でのリードも大きく、1年生ながら攻走守に渡って非凡な野球センスを感じさせる。しかし2死後、けん制アウト。高校野球人生のほろ苦いスタートとなった。
応援席からは関係者の皆さんとともに、八王子実践の野球部員たちも大挙駆け付け応援。昨年は部員が少なく青鳥は合同チームで大会に出場、その際、八王子実践とは秋季大会で対戦していた。
2回表はセカンド八木が2つのフライを掴んで2アウトをもぎ取ったが、その前後、外野の間を抜けたりエラーしたり後逸したりで、ランニングホームラン5本が飛び出してしまう。
捕手後藤は「外野、後ろいったら全力で追って、全力で!」と懸命に声をかける。
この時点で首藤は打者23人に相対し17失点。既にかなりの球数を投げていた。
首藤は24人目の打者への投球後、足が攣り、いったんベンチに引き上げる。だが続投できずショートの岩本がマウンドに立ち、セカンドフライで後続を断った。
この回のアウトは全てセカンド八木へのフライだった。
2回裏、6番熊谷はセカンドゴロを放つが3者凡退。
3回表岩本は、エラーなどもあって打者14人で1アウトも取れず14失点を喫してしまう。次の打者でセカンド八木がゴロでの初めてのアウトを取ったが、次のアウトが遠い。
「はたしてこの試合は終わるのだろうか?」そんな疑問も頭に浮かぶ。
このままコールド負け(公式戦を成立させる)するための、8個のアウトが取れるとは思えない。岩本のどこかが壊れてしまうのではないかという勝手な心配もよぎる。
さらに4点を奪われ四球を与えたところで、「それしか選択肢はないだろう」と、ショートのポジションに入っていた首藤が再びマウンドに立った。
そして初の三振を奪う。次打者はセカンドへのイレギュラー気味のバウンドが右中間を抜け失点してしまったが、その後のバッターからも空振り三振!
ピッチャーが代わり、タイミングが取りづらかったのもあるだろうが、いい球がきていたようだ。
3回は21失点、3回を終えて38-0。
3回裏、青鳥の攻撃、9番三上がセカンドゴロを放つが3者凡退。
3回を終えたところでクーリングタイム。通常は5回を終えたところだが、この試合は5回までであることが明白であった。審判は投手に水分摂取を進めたり、回の途中でも選手をベンチに引き上げさせたり、臨機応変に的確に試合を進めていた。
再開後の4回表、東村山西は打者19人で15点。アウトはレフトフライ、ライトフライ、ファーストゴロだった。
ライト三上は西日のまぶしさもあり、それまでなかなか捕球できないでいたが、グラブにおさめて拍手大喝采。
この時点で53-0のスコア。
4回裏、青鳥は三者凡退。
そして5回表、首藤は残る力を振り絞って18人の打者に相対し、三振三つ(振り逃げ一つを含む)とピッチャーフライで投げ切った。
5回裏、青鳥はこれまで出番のなかった選手たちが代打に立つ。最初は3年生キャプテン白子、試合中は選手たちに声をかけ、ペットボトルをマウンドに運んだ。東村山西はエースナンバーの投手が登板、快速球を投げ込んでくる。「どうせなら見たこともない快速球で三振したほうが良いのではないか」と勝手に思っていると3ボールとなってしまう。しかしその後の3球で見事に三振。おそらく一生忘れらないボールの軌道、三振となるであろう。
その後の代打2人も三振でゲームセット。66-0で試合を終えた。試合時間は3時間を越え、照明塔にも灯がともされた。
ヒットは青鳥が1本、東村山西が55本。だが4割ほどは並のレベルの高校野球部ならアウトだっただろう。盗塁は手元の集計では30個走られた。捕手後藤はよく捕球した場面も目立ったが捕逸も多かった。
そんななか首藤は延べ62人の打者、200球近く投げただろうか(球数はカウントしていなかった)。
首藤がいなかったら試合が成立していなかったことは間違いないだろう。回復の時間を与えてくれた岩本のつなぎも貴重だっただろう。
またこの試合は東村山西高にとっても簡単な試合ではなかっただろう。バッティングのタイミングもそうだろうし、次戦につなげるためには集中力を欠いてはならないし。
この試合は野球の残虐性も感じられる試合だった。
時間制のスポーツ、サッカーやバスケット、ラグビーなら、どんなに点差をつけられても時間がくれば終わる。
逆にバレーなどのネット型スポーツなら、あっという間に終わってしまう。しかし野球は負け試合を自力で終わらせなくてならならない。
とにかくこの試合は歴史的な第一歩となる試合だったことは間違いない。青鳥野球部に続こうという学校も出てくるかもしれない。だが簡単ではないだろう。硬球を投げ、打ち、捕るのは簡単ではない。継続していくことはさらに簡単ではないだろう。
もちろん特別支援学校野球部が予選に出て、勝ったり負けたりすることが日常となるのが理想だが。
当面継続していくためには、最低でも首藤クラスのピッチャーがいないとなかなか難しい。青鳥野球部も首藤なき後の投手育成が課題となるだろう。守備力はおそらく1年後には飛躍的に進化しているだろう。
来年も是非観戦したい。
