虚脱が襲い、あとはぐずぐずと萎えていった。
何度目かの最後の言葉を読み終えた後は、ただぼんやりと虚ろな視線を、足下に落としていた。
高志は漁協事務所から出て来た後の、今日の鉄五郎さんの様子を危ぶんでいた。
どこか視線が定まらず、きちんと眼の前を見ていない気がした。
時折足元がふらついているのではと思う時もあった。
直ぐに病気がぶり返したのではと案じられ思わず「具合が悪いのでは」と声をかけたが、鉄さん
は「いや」とだけ言って、顔の前で手を振った。
それからは船の上でも眼を離さないようにしていた。
前回倒れた時も何の前ぶれもなく、突然だったので不安は増した。しかし家に着いた頃には普段
と変わらぬ様子に戻っていたので、ようやくほっとした。
御用篭を背に畑に向かった姿にも、異常は窺えないと思った。
夕暮れには間があったが、あやは夕餉の支度にかかっている。
高志は指示された延縄仕掛の鉤結びに取りかかった。
漁師の仕事はどんな作業も、始まると周りの気掛りが消えてしまい、時間の経つのを忘れてしま
う。
ようやく手元の糸が見えにくくなってから顔を上げた。
窓の外の光りは既に弱まり、茜色に染まり始めていた。
高志の動きに気付いて、あやが明かりを点けた。
「鉄さん遅いね」
高志は窓の外に視線を向けたまま言った。
その声の調子に、台所に戻りかけたあやが振り返った。










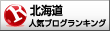

 の小説の更新もある
の小説の更新もある




