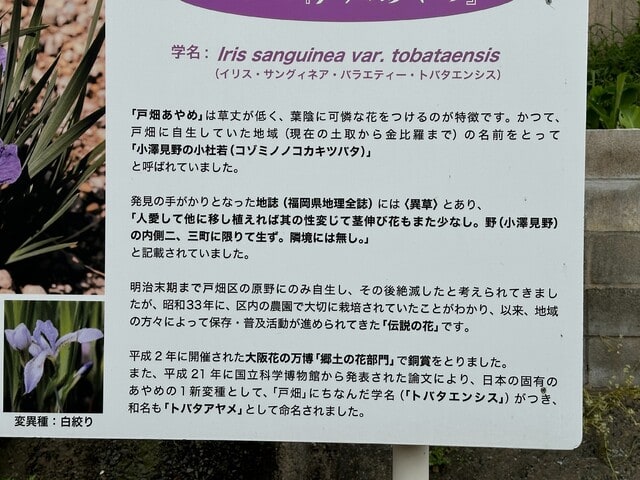6月10日です。蒸し暑くなってまいりました。来週には梅雨入りかな。
5月末の膝のMRI検査では、まだ1/5ほど影が残っていて、RUNお預けは続きます。やはり、全治3ケ月の見立て通りのようです。
ここで、武田ドクターより指示有り。『暑くなってきたから、暑熱順化のトレをやりなさい。ウオーキングなら、2時間大丈夫。暑熱順化まで3週間です。』 なるほど~! 7月からRUN、OKとなっても、夏の暑さの中ですぐにガンガン走れるわけではない。
11月初旬のフルマラソン、本命の11/22~24の「橘湾岸スーパーマラニック」(W276km)まで残り5ケ月、来月から走りだせたとして4ケ月、爺さんにしてはぎりぎりの練習期間しかありません。
わかっちゃいるけど、2ケ月も一歩も走ってないと、『もういいんじゃないのかねぇ、ふつうに年寄りやれば、、、』と囁く自分がいるのですよ。
前々回のWで、小浜木場(269,7km)で関門アウトとなったのは、雲仙地獄(260km)あたりから身体が反り返ってまともに歩けず、何度もこけてしまったからで、いったいこれの防止、対策は何なのだろうと思案してきたが、やはり筋肉を頑丈に鍛えるしかないか、、、が75歳の爺さんにそんなに有効なトレーニングがあるとは思えんし、、。そうだ、ポール歩きはどうだろうか。

(2022/11/22 ㏘16;27;53 関門時刻に18分超過)
トレッキングポールは、かっての「萩往還マラニック」に出場するにあたって購入していたが、なんか邪道のような気がしたことと、そんなに使う場面も無いのに持ち運びが面倒なのでお蔵入りしていたが、昨年の「新萩往還」で坂上り下りの楽さに気づいた。がしかし、「橘湾」に持ち込むとなると、ほとんどロードであるし、山での杖とは違うはず。先ずはポールの正しい使い方を教えてもらわんといかんなぁ。
Netで探すと、カルチャーセンターにはある。ただし1回1600円なり。う~む。で見つけました。公民館の健康教室。東区でいささか遠いけど月一回、無料。講師の名前にビックリ! 面識はないが、ここらの市民マラソンでは入賞常連の若き女性ランナーではないか。大病院の「健康運動指導士」さんとのこと。さっそく公民館に電話すると『どうぞ、どうぞ!』 ノルディックウオークである。

かくして、まずは受講。講師のTHUさんには正直に目的を話す。なにしろ受講者は”おねえさま”ばっかりで、男性歓迎だそうで、、、75歳なんですけど。
で、自分なりに、暑熱順化を兼ねて練習開始。マイコースで、犬の散歩中のかっての同僚と久しぶりの再会、シャッターをお願いする。まだまだフォームがダメですねぇ。
6月いっぱいは、この練習に励みます。


先日、ジョギング中の橘湾岸スーパーマラニック事務局の井上さんに遭遇(同じ小学校区内居住なのですよ)、呼び止めて『秋にはお世話になります。』『ダメなら(ボランティアに)入ってね。』
うんにゃ、爺さんは、走りたいのですよ。
5月末の膝のMRI検査では、まだ1/5ほど影が残っていて、RUNお預けは続きます。やはり、全治3ケ月の見立て通りのようです。
ここで、武田ドクターより指示有り。『暑くなってきたから、暑熱順化のトレをやりなさい。ウオーキングなら、2時間大丈夫。暑熱順化まで3週間です。』 なるほど~! 7月からRUN、OKとなっても、夏の暑さの中ですぐにガンガン走れるわけではない。
11月初旬のフルマラソン、本命の11/22~24の「橘湾岸スーパーマラニック」(W276km)まで残り5ケ月、来月から走りだせたとして4ケ月、爺さんにしてはぎりぎりの練習期間しかありません。
わかっちゃいるけど、2ケ月も一歩も走ってないと、『もういいんじゃないのかねぇ、ふつうに年寄りやれば、、、』と囁く自分がいるのですよ。
前々回のWで、小浜木場(269,7km)で関門アウトとなったのは、雲仙地獄(260km)あたりから身体が反り返ってまともに歩けず、何度もこけてしまったからで、いったいこれの防止、対策は何なのだろうと思案してきたが、やはり筋肉を頑丈に鍛えるしかないか、、、が75歳の爺さんにそんなに有効なトレーニングがあるとは思えんし、、。そうだ、ポール歩きはどうだろうか。

(2022/11/22 ㏘16;27;53 関門時刻に18分超過)
トレッキングポールは、かっての「萩往還マラニック」に出場するにあたって購入していたが、なんか邪道のような気がしたことと、そんなに使う場面も無いのに持ち運びが面倒なのでお蔵入りしていたが、昨年の「新萩往還」で坂上り下りの楽さに気づいた。がしかし、「橘湾」に持ち込むとなると、ほとんどロードであるし、山での杖とは違うはず。先ずはポールの正しい使い方を教えてもらわんといかんなぁ。
Netで探すと、カルチャーセンターにはある。ただし1回1600円なり。う~む。で見つけました。公民館の健康教室。東区でいささか遠いけど月一回、無料。講師の名前にビックリ! 面識はないが、ここらの市民マラソンでは入賞常連の若き女性ランナーではないか。大病院の「健康運動指導士」さんとのこと。さっそく公民館に電話すると『どうぞ、どうぞ!』 ノルディックウオークである。

かくして、まずは受講。講師のTHUさんには正直に目的を話す。なにしろ受講者は”おねえさま”ばっかりで、男性歓迎だそうで、、、75歳なんですけど。
で、自分なりに、暑熱順化を兼ねて練習開始。マイコースで、犬の散歩中のかっての同僚と久しぶりの再会、シャッターをお願いする。まだまだフォームがダメですねぇ。
6月いっぱいは、この練習に励みます。


先日、ジョギング中の橘湾岸スーパーマラニック事務局の井上さんに遭遇(同じ小学校区内居住なのですよ)、呼び止めて『秋にはお世話になります。』『ダメなら(ボランティアに)入ってね。』
うんにゃ、爺さんは、走りたいのですよ。