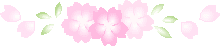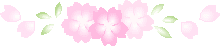【樹齢約250年の桜~親戚の家から~】
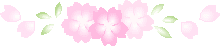
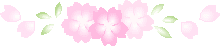
月に叢雲花に風 (つきにむらくもはなにかぜ)
好事にはとかく邪魔が入りやすく
よい 状態は長続きしないということ。
月見をすれば雲が名月を隠し
花見に行けば風が桜花 を散らす。
同意語として、 「花には嵐のさわりあり」、「花に風」、「花に嵐」
「花開いて風雨多し 」 などかあるそうです。
昔の人はうまいこと言いましたよね。
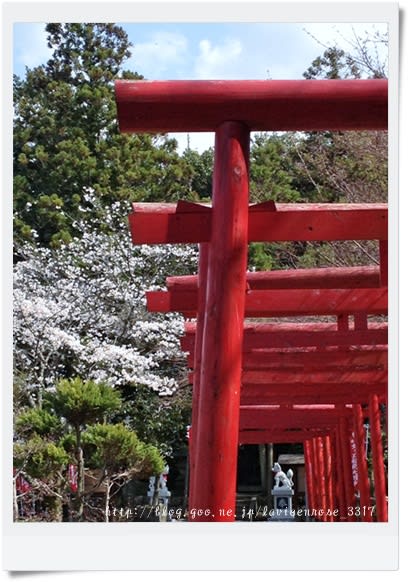
【お稲荷さんの桜】
土曜日から日曜日にかけてのの花嵐で、満開だった桜の花が随分と数を減らしてしまいました。
それでも踏ん張って残ってくれた桜たちが、入学式に花を添えてくれそうです。
花といえば、日本語には多くの花の付く言葉がありますね。
どんな言葉がお好きですか?

花明かり:桜の花が一面に咲いて、夜でもあたりが明るく見えること
花嵐:桜の花の盛りのころに吹く強い風 また、その風で桜の花が散り乱れること
花筏(はないかだ):散った花びらが川面を流れてゆくようす
花香
花霞(はながすみ):遠く咲く桜の花群
花の鏡:花の影の映る水面のようす
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花の賀:花の宴
花の雲~咲き連なる桜の花の様の例え
花曇り:桜の花が咲くころに、空が薄く曇っているようす
花心:うつろいやすい心
花の波:花の連なり、花の散り浮かぶ波
花冷え:春、桜の花が咲くころに一時的にもどってくる寒さ
花疲(はなづかれ):花見に歩いて疲れること
花の姿:美しい様
花筵:草花などが一面に咲きそろったさま、また、花の散り敷いたさまを筵にたとえていう語
花風
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花匂(はなにおい):花に美しく映える様
花笑(はなえみ):花が咲くこと また咲いた花のような華やかな笑顔
花香(はなが)
花雪:花群を雪に例えたもの
花催(はなもよい):花の咲きそうな気配
花の雫:花から滴り落ちる露
花掛水(はなかけみず)
花錦
花のふすま:花が身に降りかかる様
花恥ずかしい:ういういしい
花盗人(はなぬすびと)
花守(はなもり):花の番人
花のとざし(とぼそ):花に囲まれた家
花の浮き橋:花の水面に散り敷いた様
花見船
花風
花陰(はなかげ)
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花匂(はなにおい):花に美しく映える様
花見顔
花見鳥~うぐいすの異称
花摘(はなつみ)
花の下臥(はなのしたぶし):花の下陰に寝ること
花細し(はなぐわし):花が美しいの意
花摺衣:花摺りで染めた衣 すりごろも
・・・・いやはや、きりがありません。
こんな言葉をさらりと使える様な、花のような人でありたいものです。
ところで、桜の花が日本人に好まれるのには
散り際が潔い(いさぎよい)からだと言われています。
潔いとは、思い切りがよい。卑怯なところや未練がましいところがない。
清らかで気持ちが良い。汚れがないという意味です。
このいさぎよい という言葉を
いさぎいいとも言ったりしますが
これは大きな間違いです。
潔いとは 「いさ(いと)」 + 「清い 」から来たもので
「いさぎ」が 良いとか悪いとかいう 意味ではないのです。
とても清い・・・という意味なのだそうです。
いや~!
使ってましたよ「いさぎいい ですね!」って
間違ってたのですね。



【姪から届いた桜の写真~なばなの里にて~】
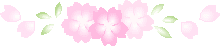
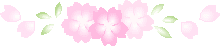

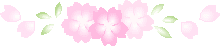
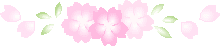
月に叢雲花に風 (つきにむらくもはなにかぜ)
好事にはとかく邪魔が入りやすく
よい 状態は長続きしないということ。
月見をすれば雲が名月を隠し
花見に行けば風が桜花 を散らす。
同意語として、 「花には嵐のさわりあり」、「花に風」、「花に嵐」
「花開いて風雨多し 」 などかあるそうです。
昔の人はうまいこと言いましたよね。
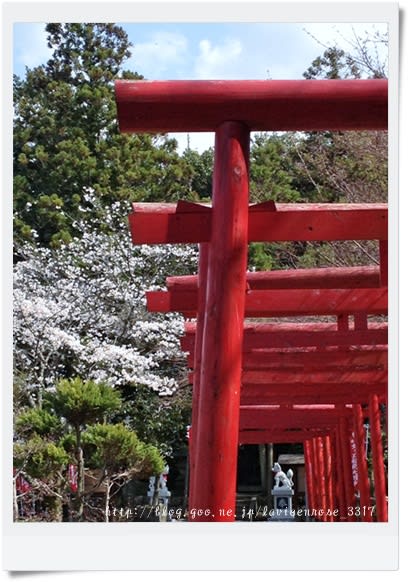
【お稲荷さんの桜】
土曜日から日曜日にかけてのの花嵐で、満開だった桜の花が随分と数を減らしてしまいました。
それでも踏ん張って残ってくれた桜たちが、入学式に花を添えてくれそうです。
花といえば、日本語には多くの花の付く言葉がありますね。
どんな言葉がお好きですか?

花明かり:桜の花が一面に咲いて、夜でもあたりが明るく見えること
花嵐:桜の花の盛りのころに吹く強い風 また、その風で桜の花が散り乱れること
花筏(はないかだ):散った花びらが川面を流れてゆくようす
花香
花霞(はながすみ):遠く咲く桜の花群
花の鏡:花の影の映る水面のようす
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花の賀:花の宴
花の雲~咲き連なる桜の花の様の例え
花曇り:桜の花が咲くころに、空が薄く曇っているようす
花心:うつろいやすい心
花の波:花の連なり、花の散り浮かぶ波
花冷え:春、桜の花が咲くころに一時的にもどってくる寒さ
花疲(はなづかれ):花見に歩いて疲れること
花の姿:美しい様
花筵:草花などが一面に咲きそろったさま、また、花の散り敷いたさまを筵にたとえていう語
花風
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花匂(はなにおい):花に美しく映える様
花笑(はなえみ):花が咲くこと また咲いた花のような華やかな笑顔
花香(はなが)
花雪:花群を雪に例えたもの
花催(はなもよい):花の咲きそうな気配
花の雫:花から滴り落ちる露
花掛水(はなかけみず)
花錦
花のふすま:花が身に降りかかる様
花恥ずかしい:ういういしい
花盗人(はなぬすびと)
花守(はなもり):花の番人
花のとざし(とぼそ):花に囲まれた家
花の浮き橋:花の水面に散り敷いた様
花見船
花風
花陰(はなかげ)
花の顔ばせ:花のように美しい顔
花匂(はなにおい):花に美しく映える様
花見顔
花見鳥~うぐいすの異称
花摘(はなつみ)
花の下臥(はなのしたぶし):花の下陰に寝ること
花細し(はなぐわし):花が美しいの意
花摺衣:花摺りで染めた衣 すりごろも
・・・・いやはや、きりがありません。
こんな言葉をさらりと使える様な、花のような人でありたいものです。
ところで、桜の花が日本人に好まれるのには
散り際が潔い(いさぎよい)からだと言われています。
潔いとは、思い切りがよい。卑怯なところや未練がましいところがない。
清らかで気持ちが良い。汚れがないという意味です。
このいさぎよい という言葉を
いさぎいいとも言ったりしますが
これは大きな間違いです。
潔いとは 「いさ(いと)」 + 「清い 」から来たもので
「いさぎ」が 良いとか悪いとかいう 意味ではないのです。
とても清い・・・という意味なのだそうです。
いや~!
使ってましたよ「いさぎいい ですね!」って
間違ってたのですね。




【姪から届いた桜の写真~なばなの里にて~】