紀元前500年頃の関西・関東(群馬・火山灰鎧兜軍人)
・先だっての群馬榛名山噴火に埋もれた鎧兜の武人は長野県伊那地域出身者と判明していた。この時代が紀元前500年前後に筆者は推定した(NHKや考古学会では紀元後500年で1000年前後の開きがある)が、その時代は世間的には弥生時代が始まった時代で赤い土器などが始まった時代と言われている。しかし私の「生活科学の目」で古代出土品を見ると①統計的には三角縁神獣鏡勢力が伊那谷飯田市辺りには北信・長野地域で多く出土する鈴鏡(鈴が付いた鏡)勢力が飯田地域で多く出土していて勢力が存在していたことが推定出来、甲冑の武人が群馬方面に偵察に派遣された家族か定住を考えた武人だったと推定できる。②また三角縁神獣鏡勢力が飯田地域に2古墳(?)から出土し群馬でも三角縁神獣鏡出土3古墳が存在していることから、三角縁神獣鏡勢力が同時代の繁栄地の飯田や群馬に偵察隊を送り込んでいた時代と推定できる。飯田地域では自然環境は不明だが鈴鏡勢力も三角縁神獣鏡勢力も他の銅鏡勢力も衰退しているので、勢力の林立で勢力争いに地域は疲弊したためにその後の繁栄は考えられなかった。③一方で東日本で勢力拡大を群馬の火山爆発や寒冷化で諦めた三角縁神獣鏡勢力が
その後勢力の主力を京都周辺の畿内に移して畿内の多くの銅鏡勢力の中で多くの三角縁神獣鏡出土古墳を残している(出土している)④では飯田の勢力文化を少し考えてみると、紀元前500前後時代は諏訪地域のお諏訪様の勢力は強いとはいえ、峠一つ越えた松本地域の黒色土器勢力は飯田地域を超えて山並み向こうの岐阜や高山地域から名古屋地域の文化の中に入り込んでいる。飯田地域は元々灰釉陶器等の文化発祥地的地域だが、諏訪人や松本人はこの地域から名古屋そして京都・奈良への文化交差地でもあり、古代の道の駅的存在で一つの勢力は鈴鏡勢力が一番長かった程度だったと推定できる。⑤ではこの時代西日本ではどんな文化だったかとみると、名古屋等は以前からの製鉄文化的色彩が強かったが、銅鐸勢力が根付いて更に三角縁神獣鏡勢力(当時三角縁神獣鏡勢力中心地は静岡磐田市から京都等畿内に中心を移してつつある)⑥畿内は銅鐸文化勢力から銅鏡勢力が台頭してきた時代で、多くの勢力が勢力争いを繰り広げていたと推定できる。奈良で有名な唐子鍵遺跡や石上神宮出土土器・纒向遺跡などで黒色土器や須恵器のような白い土器が出土している。黒色土器はルーツと思われる松本地域では縄文中期後葉頃出現した時と推定しているが、それらの土器が畿内の纒向遺跡等で出土しているが、纒向遺跡の時代設定は弥生後期紀元後3世紀頃・石上神宮出土土器・須恵器と黒色土器は紀元180以後頃という編年基準だが、黒色土器が出土している。黒色土器の時代は須恵器の時代になっているので、もっと以前の紀元0年前後頃以前ではないかと推定するが、ただ須恵器焼成技術は技術伝来によって地域により幅広い年代に使われていたことは否定できないので、断定は難しい。
・ただ黒色土器の伝来は東日本の方が早いと推定されるので、西日本での時代が紀元後の2-3世紀であっても全面否定はしない。日本の土器等編年基準は見直しもっと科学的観点で作り直す必要があることを強く要望する。
・先だっての群馬榛名山噴火に埋もれた鎧兜の武人は長野県伊那地域出身者と判明していた。この時代が紀元前500年前後に筆者は推定した(NHKや考古学会では紀元後500年で1000年前後の開きがある)が、その時代は世間的には弥生時代が始まった時代で赤い土器などが始まった時代と言われている。しかし私の「生活科学の目」で古代出土品を見ると①統計的には三角縁神獣鏡勢力が伊那谷飯田市辺りには北信・長野地域で多く出土する鈴鏡(鈴が付いた鏡)勢力が飯田地域で多く出土していて勢力が存在していたことが推定出来、甲冑の武人が群馬方面に偵察に派遣された家族か定住を考えた武人だったと推定できる。②また三角縁神獣鏡勢力が飯田地域に2古墳(?)から出土し群馬でも三角縁神獣鏡出土3古墳が存在していることから、三角縁神獣鏡勢力が同時代の繁栄地の飯田や群馬に偵察隊を送り込んでいた時代と推定できる。飯田地域では自然環境は不明だが鈴鏡勢力も三角縁神獣鏡勢力も他の銅鏡勢力も衰退しているので、勢力の林立で勢力争いに地域は疲弊したためにその後の繁栄は考えられなかった。③一方で東日本で勢力拡大を群馬の火山爆発や寒冷化で諦めた三角縁神獣鏡勢力が
その後勢力の主力を京都周辺の畿内に移して畿内の多くの銅鏡勢力の中で多くの三角縁神獣鏡出土古墳を残している(出土している)④では飯田の勢力文化を少し考えてみると、紀元前500前後時代は諏訪地域のお諏訪様の勢力は強いとはいえ、峠一つ越えた松本地域の黒色土器勢力は飯田地域を超えて山並み向こうの岐阜や高山地域から名古屋地域の文化の中に入り込んでいる。飯田地域は元々灰釉陶器等の文化発祥地的地域だが、諏訪人や松本人はこの地域から名古屋そして京都・奈良への文化交差地でもあり、古代の道の駅的存在で一つの勢力は鈴鏡勢力が一番長かった程度だったと推定できる。⑤ではこの時代西日本ではどんな文化だったかとみると、名古屋等は以前からの製鉄文化的色彩が強かったが、銅鐸勢力が根付いて更に三角縁神獣鏡勢力(当時三角縁神獣鏡勢力中心地は静岡磐田市から京都等畿内に中心を移してつつある)⑥畿内は銅鐸文化勢力から銅鏡勢力が台頭してきた時代で、多くの勢力が勢力争いを繰り広げていたと推定できる。奈良で有名な唐子鍵遺跡や石上神宮出土土器・纒向遺跡などで黒色土器や須恵器のような白い土器が出土している。黒色土器はルーツと思われる松本地域では縄文中期後葉頃出現した時と推定しているが、それらの土器が畿内の纒向遺跡等で出土しているが、纒向遺跡の時代設定は弥生後期紀元後3世紀頃・石上神宮出土土器・須恵器と黒色土器は紀元180以後頃という編年基準だが、黒色土器が出土している。黒色土器の時代は須恵器の時代になっているので、もっと以前の紀元0年前後頃以前ではないかと推定するが、ただ須恵器焼成技術は技術伝来によって地域により幅広い年代に使われていたことは否定できないので、断定は難しい。
・ただ黒色土器の伝来は東日本の方が早いと推定されるので、西日本での時代が紀元後の2-3世紀であっても全面否定はしない。日本の土器等編年基準は見直しもっと科学的観点で作り直す必要があることを強く要望する。










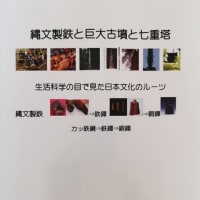




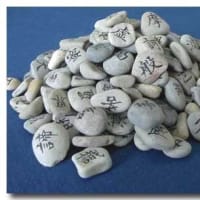


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます