埴輪の用途とルーツ
埴輪は日本の多くの古墳に飾られ日本でのみ出土する出土品の一つだが、何故円筒埴輪を飾るのかという用途や埴輪の90%以上が円筒埴輪で、人物や動物や器材埴輪と言われるものも出土するが、円筒埴輪に比較すると僅かの数で何故円筒埴輪を古墳に飾るのか現在は謎に包まれたままだ。
・さらに埴輪のルーツも不明のままだが、生活科学の目で見た古代史を検討すると、動画で検討したようにはっきり推定できる。
・結論では円筒埴輪・朝顔形埴輪は製鉄や・製銅の鋳物炉だという事。又何故古墳に多く飾られたかと言えば、この時代は魏志倭人伝で言うように日本には100を数える多くの勢力が存在し、各勢力は自己の勢力の力・文化力を他の勢力に誇示するPRとして古墳頂上などに並べたと考えられる。
・では埴輪のルーツはどこかというと、埴輪の形状や焼成方法など、検討の必要があるので断定はできないが、今埴輪のルーツとして最有力の吉備地域が言われているが、筆者としてはプレ埴輪とされる「底穿孔壷」を古墳に飾った時代に、その前方後方墳勢力に対抗して朝顔形壷を古墳に飾って、円筒埴輪に改良された経過が出土品等から見える「松本~対抗した埼玉~同じ頃群馬」等辺りではないかと推定している。群馬では円筒埴輪というより、形象埴輪の人物や馬など文化内容を表した埴輪が飾られていることから、と推定している。
・ただ未だ資料集めが不十分なために断定できない。
・生活科学の目で見た古代史の観点から製作した動画「埴輪の用途とルーツ」を見て下さい。
埴輪は日本の多くの古墳に飾られ日本でのみ出土する出土品の一つだが、何故円筒埴輪を飾るのかという用途や埴輪の90%以上が円筒埴輪で、人物や動物や器材埴輪と言われるものも出土するが、円筒埴輪に比較すると僅かの数で何故円筒埴輪を古墳に飾るのか現在は謎に包まれたままだ。
・さらに埴輪のルーツも不明のままだが、生活科学の目で見た古代史を検討すると、動画で検討したようにはっきり推定できる。
・結論では円筒埴輪・朝顔形埴輪は製鉄や・製銅の鋳物炉だという事。又何故古墳に多く飾られたかと言えば、この時代は魏志倭人伝で言うように日本には100を数える多くの勢力が存在し、各勢力は自己の勢力の力・文化力を他の勢力に誇示するPRとして古墳頂上などに並べたと考えられる。
・では埴輪のルーツはどこかというと、埴輪の形状や焼成方法など、検討の必要があるので断定はできないが、今埴輪のルーツとして最有力の吉備地域が言われているが、筆者としてはプレ埴輪とされる「底穿孔壷」を古墳に飾った時代に、その前方後方墳勢力に対抗して朝顔形壷を古墳に飾って、円筒埴輪に改良された経過が出土品等から見える「松本~対抗した埼玉~同じ頃群馬」等辺りではないかと推定している。群馬では円筒埴輪というより、形象埴輪の人物や馬など文化内容を表した埴輪が飾られていることから、と推定している。
・ただ未だ資料集めが不十分なために断定できない。
・生活科学の目で見た古代史の観点から製作した動画「埴輪の用途とルーツ」を見て下さい。










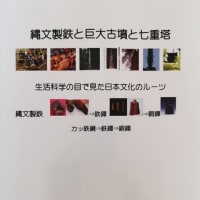




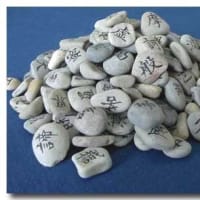


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます