先日、「ノルウェイの森」を読み直し、あぁ、こんな小説だったっけ…などと改めて思う。中学、高校、大学にかけて、村上春樹の初期三部作(「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」「羊をめぐる冒険」)を馬鹿みたいに繰り返し読み、でもそれは村上春樹の作品を読むというよりは、僕自身の痛みや感情を見つけ出す作業といってもよかったと思う。だからこそ、その当時、あるいはそれ以降も、自分自身を重ねあわせにくかった作品は1度読んで終わりにしていたというところがある。
さすがに、当時ほどのめりこみ過ぎないほどよい距離感で読みむことができるようになったので、「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」「ノルウェイの森」に引き続き読み直してみたのが「海辺のカフカ」。
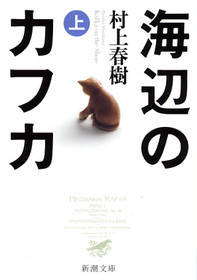
海辺のカフカ (上) (新潮文庫)
うん、でも、何だろう。うがった見方過ぎるのかもしれないけれど、村上春樹にとっては「僕」「直子」「鼠」あるいは「ワタナベノボル」「直子」「キズキ」「緑」との関係性というのは未だに終わっていないことなのだろう。この小説―「海辺のカフカ」を読み直して改めて思ったのは、これは初期三部作と「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」とに連なる物語なのだろう、ということ。
もちろんそこにはギリシア悲劇的世界観(エディプス王の物語)や心理学的な世界観が入り、初期三部作とは趣は異なる。しかし登場人物をこのようにならべてみるとどうだろう。
海辺のカフカ|ノルウェイの森|初期三部作
僕(田中カフカ)|僕(ワタナベノボル)|僕
佐伯さん|直子|直子
過去の恋人、カラスと呼ばれる少年|キズキ|鼠
さくら|小林緑|キキ(実質的には「ダンス・ダンス・ダンス」)
佐伯さんは「恋人」だけでなく「母」だという意見もあるだろうが、それを「母」という不可侵の存在の象徴として捉えるならば、「直子」というのは唯一無二の親友の恋人であり、本来、恋愛関係や肉体関係を持ってはいけない存在だったと言えるだろう。そうした存在にもかかわらず、「憧れ」や「手に入れたい」という思い(≒エディプスコンプレックス)、あるいは肉体関係―そうしたをもってしまったが故の罪悪感が常に村上春樹の奥底に存在しているような気がするのだ。
さくらの存在はそれほど登場シーンは多くないがカフカにとっては大きい存在といえるだろう。それは「姉」であったわけだけれど同時に「生きる」「ぬくもり」の象徴でもある。ノルウェイの森での緑というのはその意味でまさに同じ存在だ。彼女は「僕」「直子」「キズキ」のどこへもいけない「死」の関係とは別次元の存在として、僕を「生」の世界へと連れ戻す存在だ。ノルウェイの森のラストシーンで僕が緑に電話をかけたように、「海辺のカフカ」でも「僕」は「さくら」に電話をするのだ。
ノルウェイの森のもう1人のキーパーソン「キズキ」は「カフカ」では誰に当たるのだろうか。佐伯さんの死んだ恋人がそうではあるけれど、この「海辺のカフカ」ではそれに加えて、2つの存在を当てはめることができるのではないかと思う。1つは上記でも書いたように「カラスと呼ばれる少年」だ。彼は、カフカを通じて、佐伯さんと語り合う。あるいは関係を持つといってもいい。
それに加えて「海辺のカフカ」では、負の側面としての「父(の呪い)」も当てはまるのかもしれない。
そもそも僕とキズキの関係の中にはある種の「呪い」のようなものがある。キズキは僕にとって親友であり、ある種の憧れの対象でもあった。そのキズキが自殺をし、恋人の「直子」を僕に託すような形となった。このことは僕にとって直子を単に恋人として扱えない関係を作り出している。直子は「親友」の恋人であり、僕はその面倒を託されたのであり、直子と僕との関係は第一義的にキズキをとおしての関係であって、普通の恋人のようには接することができない。キズキをあえて超えなければ存在の「父」と見るならば、直子は「母」であり、直子と「寝る」「恋人のような関係を築く」ということは、まさに「父殺し」でしかない。しかしキズキは同時にそのことを踏まえた上で、直子を僕に託しているのだ――このことはまさに「カフカ」にとっての呪いそのものだろう。
そういう意味で、ノルウェイの森での「キズキ」の役割を「佐伯さんの過去の恋人」あるいは「カラスと呼ばれた少年」がまずは果たしつつ、同時にカフカの「父」もが果たしているのだ。
またこの小説の後半の「森」の世界観というのは「世界の終わり」と酷似している。しかしその結末は対照的だ。
「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」では、「私」は永遠の生/死に際して淡々と最期の時を過ごし眠りにつく。そしてもう一方の(「世界の終わり」の)「僕」は心の抱えた「影」を逃がしつつ、しかし自らはその世界に残って責任を果たすことを選択する。そうしたある種の受身的な態度、あるいは諦観のようなスタイルに対し、「海辺のカフカ」ではカフカはもう1度、現実の世界に戻ろうとする。
それは「ダンス・ダンス・ダンス」や「アンダーグラウンド」以降の村上春樹の変化を示すものなのだろうか。しかしそれでもこの物語を読む限り、村上春樹はまだ同じ物語(トラウマ)の真実を追い続けているように見える。
比重のある時間が、多義的な古い夢のように君にのしかかってくる。君はその時間をくぐり抜けるように移動をろつづける。たとえ世界の縁までいっても、君はそんな時間から逃れることはできないだろう。でも、もしそうだとしても、君は世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから。
東京に戻る途上、僕はカラスと呼ばれる少年と語り合う。
「でも僕にはまだ生きると言うことの意味がわからないんだ」
カラスと呼ばれる少年は応える。
「風の音を聞くんだ」
そして21歳の「僕」を舞台に「風の歌を聴け」の物語がはじまることになる。
「1973年のピンボール」 / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…
ダンス・ダンス・ダンス / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…
世界の終りとハードボイルドワンダーランド / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…
さすがに、当時ほどのめりこみ過ぎないほどよい距離感で読みむことができるようになったので、「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」「ノルウェイの森」に引き続き読み直してみたのが「海辺のカフカ」。
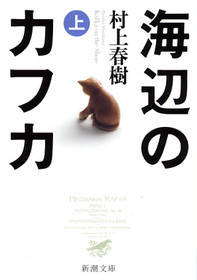
海辺のカフカ (上) (新潮文庫)
うん、でも、何だろう。うがった見方過ぎるのかもしれないけれど、村上春樹にとっては「僕」「直子」「鼠」あるいは「ワタナベノボル」「直子」「キズキ」「緑」との関係性というのは未だに終わっていないことなのだろう。この小説―「海辺のカフカ」を読み直して改めて思ったのは、これは初期三部作と「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」とに連なる物語なのだろう、ということ。
もちろんそこにはギリシア悲劇的世界観(エディプス王の物語)や心理学的な世界観が入り、初期三部作とは趣は異なる。しかし登場人物をこのようにならべてみるとどうだろう。
海辺のカフカ|ノルウェイの森|初期三部作
僕(田中カフカ)|僕(ワタナベノボル)|僕
佐伯さん|直子|直子
過去の恋人、カラスと呼ばれる少年|キズキ|鼠
さくら|小林緑|キキ(実質的には「ダンス・ダンス・ダンス」)
佐伯さんは「恋人」だけでなく「母」だという意見もあるだろうが、それを「母」という不可侵の存在の象徴として捉えるならば、「直子」というのは唯一無二の親友の恋人であり、本来、恋愛関係や肉体関係を持ってはいけない存在だったと言えるだろう。そうした存在にもかかわらず、「憧れ」や「手に入れたい」という思い(≒エディプスコンプレックス)、あるいは肉体関係―そうしたをもってしまったが故の罪悪感が常に村上春樹の奥底に存在しているような気がするのだ。
さくらの存在はそれほど登場シーンは多くないがカフカにとっては大きい存在といえるだろう。それは「姉」であったわけだけれど同時に「生きる」「ぬくもり」の象徴でもある。ノルウェイの森での緑というのはその意味でまさに同じ存在だ。彼女は「僕」「直子」「キズキ」のどこへもいけない「死」の関係とは別次元の存在として、僕を「生」の世界へと連れ戻す存在だ。ノルウェイの森のラストシーンで僕が緑に電話をかけたように、「海辺のカフカ」でも「僕」は「さくら」に電話をするのだ。
ノルウェイの森のもう1人のキーパーソン「キズキ」は「カフカ」では誰に当たるのだろうか。佐伯さんの死んだ恋人がそうではあるけれど、この「海辺のカフカ」ではそれに加えて、2つの存在を当てはめることができるのではないかと思う。1つは上記でも書いたように「カラスと呼ばれる少年」だ。彼は、カフカを通じて、佐伯さんと語り合う。あるいは関係を持つといってもいい。
それに加えて「海辺のカフカ」では、負の側面としての「父(の呪い)」も当てはまるのかもしれない。
そもそも僕とキズキの関係の中にはある種の「呪い」のようなものがある。キズキは僕にとって親友であり、ある種の憧れの対象でもあった。そのキズキが自殺をし、恋人の「直子」を僕に託すような形となった。このことは僕にとって直子を単に恋人として扱えない関係を作り出している。直子は「親友」の恋人であり、僕はその面倒を託されたのであり、直子と僕との関係は第一義的にキズキをとおしての関係であって、普通の恋人のようには接することができない。キズキをあえて超えなければ存在の「父」と見るならば、直子は「母」であり、直子と「寝る」「恋人のような関係を築く」ということは、まさに「父殺し」でしかない。しかしキズキは同時にそのことを踏まえた上で、直子を僕に託しているのだ――このことはまさに「カフカ」にとっての呪いそのものだろう。
そういう意味で、ノルウェイの森での「キズキ」の役割を「佐伯さんの過去の恋人」あるいは「カラスと呼ばれた少年」がまずは果たしつつ、同時にカフカの「父」もが果たしているのだ。
またこの小説の後半の「森」の世界観というのは「世界の終わり」と酷似している。しかしその結末は対照的だ。
「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」では、「私」は永遠の生/死に際して淡々と最期の時を過ごし眠りにつく。そしてもう一方の(「世界の終わり」の)「僕」は心の抱えた「影」を逃がしつつ、しかし自らはその世界に残って責任を果たすことを選択する。そうしたある種の受身的な態度、あるいは諦観のようなスタイルに対し、「海辺のカフカ」ではカフカはもう1度、現実の世界に戻ろうとする。
それは「ダンス・ダンス・ダンス」や「アンダーグラウンド」以降の村上春樹の変化を示すものなのだろうか。しかしそれでもこの物語を読む限り、村上春樹はまだ同じ物語(トラウマ)の真実を追い続けているように見える。
比重のある時間が、多義的な古い夢のように君にのしかかってくる。君はその時間をくぐり抜けるように移動をろつづける。たとえ世界の縁までいっても、君はそんな時間から逃れることはできないだろう。でも、もしそうだとしても、君は世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから。
東京に戻る途上、僕はカラスと呼ばれる少年と語り合う。
「でも僕にはまだ生きると言うことの意味がわからないんだ」
カラスと呼ばれる少年は応える。
「風の音を聞くんだ」
そして21歳の「僕」を舞台に「風の歌を聴け」の物語がはじまることになる。
「1973年のピンボール」 / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…
ダンス・ダンス・ダンス / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…
世界の終りとハードボイルドワンダーランド / 村上春樹 - ビールを飲みながら考えてみた…









