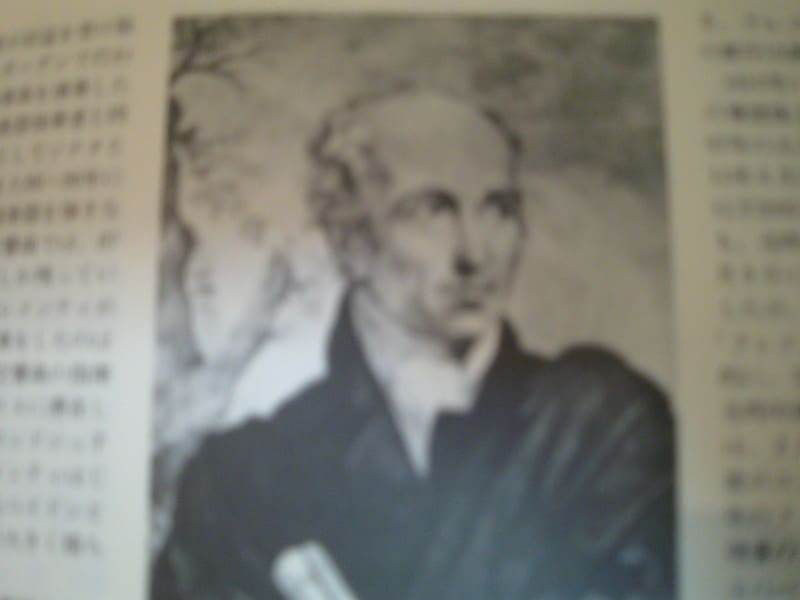1860年11月6日ポドリアのクラウフカ生、1941年ニューヨーク没
ポーランドのピアニスト、作曲家、政治家
ショパンの楽譜を買ってもらう時、
「コルトー版にして。」とか
「パデレフスキ版で。」
などと、楽譜を指定することがよくあります。
パデレフスキは、ポーランドを代表する、ピアニストで、作曲家でもありましたが、
初代ポーランド大統領でもあるのです。
彼は、ある意味、スーパースターだったとも言えるでしょう。
裕福な家柄に生まれたパデレフスキでしたが、生まれて間もなく母親は亡くなりました。
そういう意味では、何事も欠けたところのない幸福・・・というより、孤独も感じていたのではないでしょうか?
しかし、幼い頃から、音楽の才能を認められ、高名な音楽教師を家庭教師として雇い、
次いで12歳の時には、ワルシャワ音楽院に学ぶこととなりました。
多くの著名な教師から、ピアノ、音楽理論、和声、対位法などを学び、
18歳でここを卒業するとともに、同音楽院のピアノ科の教師になりました。
その後も、作曲、ピアノの研鑚を積み、当時の高名なピアノ教師レシェティツキーのもとで、
ピアノを学び続けました。
レシェティツキーは、パデレフスキの奏法に技術的な根の深い問題が多すぎるのを見て、
ピアニストの道を断念するように助言しましたが、1年間ストラスブール音楽院で教師を務める傍ら、
熱心に練習を積み、再びレシェティツキーに師事することが許されました。
パデレフスキは、自身のピアニスト生活は1888年ウィーンがデビューの地であるとみなしていましたが、
1883年パリで最初の演奏会をした時から、すでに巨匠への階段を昇り始めていました。
世界中で殺人的な演奏会スケジュールをこなす傍ら、夏休みには1889年以来永住の地となった
スイスのモルジュ市にある、ヴィラ・リオン‐ボソンで作曲にも没頭しました。
第1次世界大戦勃発後、彼はポーランド国民の為に、援助委員会や救済基金を設立しました。
同時にアメリカ合衆国を中心とした演奏活動を行い、ポーランド独立を訴えました。
1918~21年には、一時演奏・作曲活動を中止し、政治活動に専念しました。
1919年、独立を回復したポーランド共和国の首相兼外相に就任し、
国を代表してヴェルサイユ条約に署名しています。
1922年には、再び演奏活動と夏期講座の教授活動に復帰しました。
また1936年にはイギリス映画「ムーンライト・ソナタ」にも出演しています。
1937年、新ショパン全集の編集に着手しましたが、実際に出版されたのは大2次大戦後となりました。
ナチのポーランド侵攻後は、アメリカに渡り祖国支援のための大々的なキャンペーンを行いましたが、
これが彼の最後の旅となりました。
彼はニューヨークで客死し、アーリントン国立墓地で国葬が行われました。
彼の演奏は、「レシェティツキー・タッチ」でしたが、時には華麗であるが、あまりに誇張され飾られ過ぎている・・・
と、批判もしています。
彼自身は、見かけの派手な効果以前に、楽譜に忠実な演奏解釈と、音楽感情の移入を心がけました。
その天分、音楽性、直感、たゆまぬ努力によって、彼は独自の演奏様式を作り上げました。
パデレフスキーのレパートリーの中心は、ショパン、リストといったロマン派のものが中心ですが、
ほとんどすべてのリサイタルで、1曲目にベートーヴェンのソナタをおいたということです。
80年の彼の人生は、全く非の打ちようがないほど充実していますが、やるべき時に、全精力を傾け、
音楽活動だけでなく、政治にも大きな役割を果たし、素晴らしい人生を全うしたといえるでしょう。
しかし、それは彼のたゆまぬ努力の結果であり、正しい考えを持ち、現実に甘んじることなく、
常に誠心誠意、仕事をしてきた結果だと思うのです。
何気なく手にとっている、ショパンの楽譜ですが、このような素晴らしい仕事の結集とも言えるでしょう。