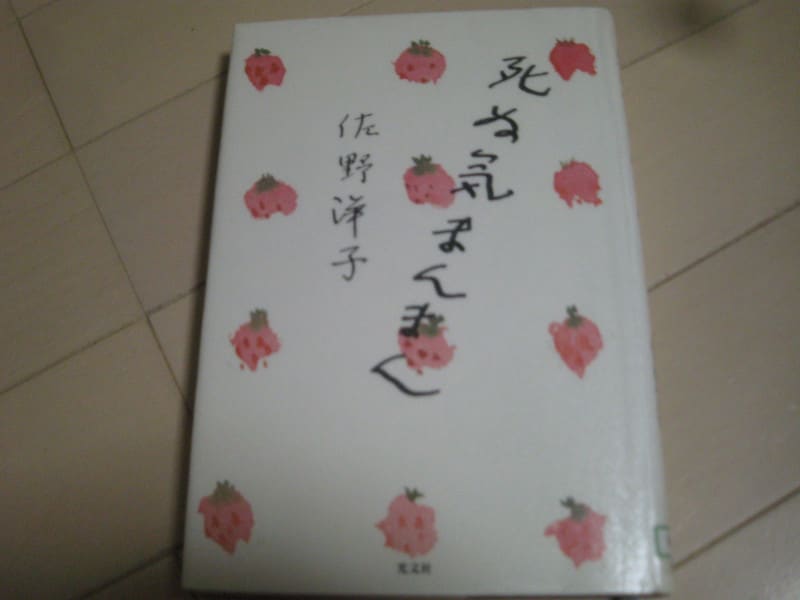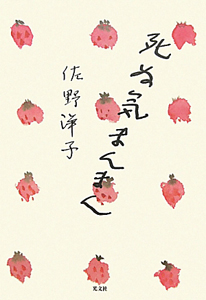最近の読書・・・いつものように乱読です

ほしい本が何冊かあったので、いつも行く錦町の今井書店ではなくケヤキ通りにある本の学校(これも今井書店ですが…)に行ってみました。
2冊ほど買う予定だったのですが、ついつい買い込んでしまい、またまた予算オーバー

年末年始にかけてこれを3度もやってしまいました

今日はその中より2冊ほどご紹介したいと思います


『ハーバード大学は「音楽」で人を育てる』菅野恵理子
『アートは資本主義の行方を予言する』山本豊津(ほづ)
どうしても音楽やアートはエンターテイメント・娯楽・嗜好品のようなもの・・と思われがちですが、ある意味学問でもあるわけです。
ピアノを弾く人はみなピアニストですが、プロのピアニストになる人は一握り。
もちろんそういう方々をとても尊敬していますが、皆が皆なる必要はありませんよね。
それぞれの分野でそれぞれの道を極めれば良いわけですから。。
ただ、聴衆としては、鋭く研ぎ澄まされた感覚を持っていたいものですよね









『ハーバード大学は「音楽」で人を育てる』菅野恵理子――の中からすこーしだけ抜粋したもの
~音楽院でも高まるリベラル・アーツ教育の需要~
―――ジュリアード音楽院副学長の言葉
音楽院なのでやはりパフォーマンス(オーケストラ・室内楽・ソロ・作曲など)が、カリキュラムの主要な部分を占めています。
ただそれだけではなく「アーティストの
人格を形成すること」というのがモットーであり、音楽史、音楽理論、ソルフェージュ、ハーモニーなどの音楽科目以外にもリベラル・アーツの学びを広げてほしいと考えています。他の音楽院と比べると、少し多いかも知れませんね。音楽博士号を取得する為には、例えば
シェイクスピア、ローマ史、中国史、日本史、文学、哲学、心理学…と言った勉強が必要になります。こうしたリベラル・アーツは演奏家としての芸術性を高め、思想を深めてくれます。これまで受け継がれてきた偉大な歴史遺産の解釈者となり、想像力を働かせてそれを新しい方向へ導くこと、それが“主張ある音楽家(
Artist who has something to say)”なのです。
~違う視点から音楽を見るリベラル・アーツの学び~
―――諏訪内晶子(ヴァイオリニスト)
私の場合は江藤俊哉先生がいらしたおかげで、日本にいながらにして世界と同等に競うレベルにいられたと思います。ソルフェージュ、ピアノを幼少から訓練しておりましたので、ヴァイオリンのパートだけでなく全体を見ながら、苦労なく現代曲にも取り組むことが出来ました。ソルフェージュ、テクニック、ピアノ、読譜力…
総合的な力を初期の段階でまんべんなく身に付けておくことが大事ですね。――略――
哲学、文学、宗教などの一般的な教養は、ジュリアード音楽院本科では人文科学という教科が必須科目としてあり、その他、
美学の授業もありました。しかし、政治思想史の授業は、ジュリアード音楽院にはありませんでした。
エリザベート(コンクール)を受けた時、ソ連(現在ロシア)の参加者がペレストロイカの話をしていました。ロストロポーヴィチなどがショスタコーヴィチやプロコフィエフの話をするときも、必ずそこには政治の話が関わってきます。
音楽も美術も政治も、人間社会が必ず反映されています。ですから政治思想史ではまず歴史を学び、その中で政治家たちがどういう哲学を持って国家を治めてきたのかという勉強をします。たとえばバッハの時代背景を全く違った視点から見ることで、より深い理解につながってゆくと思います。
~音楽と多科目を繋げる―――新しい学際的教育プログラム~
「音楽
を学ぶ」は、音楽そのものを如何に学ぶかという考え方である。いっぽう、「音楽
で学ぶ」とは、音楽を通して人間や世界をどう学ぶかという考え方である。従来主流だった前者に加え、後者の研究は21世紀という現代社会の中で、音楽を見つめ直し、新しいフレームワークの中で再構築する試みである。それは音楽の持つ文化的資源をより幅広く生かす、ということに他ならない。音楽はそれだけ、社会に多様性をもたらすものとして期待されているのだ。―――
アメリカでは「音楽や芸術の潜在的価値とは何か」という問題提起や、それに基づく研究調査や政策提言が活発に行われているそうです。
音楽を軸として、
言語・算数・科学・社会学・人文学を組み合わせたアクティヴィティーが提言され、人間のさまざまな
スキルや能力を高めるための手段として芸術を活用している学校もあるようです。
まだまだご紹介したいことはありますが…
目次よりほんの一部分だけ示しておきます。
かなり興味深いですね。
目次より――
☆音楽で「多様な価値観を理解する力」を育む―――ハーバード大学
☆音楽で「人間の思想力」を学ぶ―――コロンビア大学では全員必須?
☆音楽で「歴史を捉える力」を学ぶ―――ニューヨーク大学
☆音楽で「創造的な思考力」を高める―――マサチューセッツ工科大学
☆音楽で「心理に迫る質問力」を高める―――スタンフォード大学
☆大学入試にも重視される芸術活動 etc.






『アートは資本主義の行方を予言する』山本豊津(ほづ)――
目次より――
☆権力や体制が芸術家を恐れる理由
☆有用性ばかり求めると男性は力を失う
☆近代で断絶している日本の文化
☆室町時代と様変わりした日本の埴生
☆美しかった江戸時代へもう一度還ってみる
☆芸術が神やイデオロギーにとって代わる
☆美は「距離感」から生まれる
☆自然との関係を再び見直す時代に
☆アートの力が新しい時代の価値を生み出す
これもほんの一部ですが…。
文章の中の一部を載せておきます。
これからの社会、これからの子供たちのことに関心がおありの方は読んで頂ければと思います。
―――(本文より)これからの日本、これからの世界を考えた時、アートの力が大きな意味を持つのではないかと考えています。激動の時代、閉塞した時代だからこそ、これまでの価値に捕らわれない自由な視点が大切なのです。
その意味で私は芸術教育、美術教育にもっと力を入れてほしいと思います。ところが国はなかなかそれをしないでしょう。何故なら権力や体制がもっとも恐れるのは、自由に「感じ」「考え」そして「表現する」人間が増えることだからです。
彼らが推奨する教育とはどんな教育か?要は全員が同じような考え方をするようになる教育です。
答えが決まっていて、皆がその正解を導くように指導される教育では、新しい時代を切り開くのは不可能です。明治開闢以来日本の教育の目的は一貫しています。それは画一的な人間を作り出し、そのヒエラルキーの中で最も優秀な人間を国家が独占することで、体制強化を図ろうとすることです。
ところが芸術や美術教育は違います。人と同じようなことをやってもダメなのです。自分なりの感性や物の見方を身に付け、自分なりの表現をすることが芸術の世界です。そこでは他者と同じになることでは無く、違いを作り出すことが求められます。
そしてその違いをお互いが認め合うことに価値を置くのです。
芸術のこの価値観があれば、今学校で起きているような陰湿ないじめはなくなるのではないかと思います。
いじめの本質は、他者の違いを認めない、異質なものを排除するという偏狭さからきているからです。ついでに美術教育で言うならば、現在の教育は絵画にしても何にしても、作ることに主眼が置かれています。しかし私に言わせれば、もっと
作品を見ること、鑑賞することに力を入れてほしい。






本文中の・・・作品を見ること鑑賞すること・・・というのは音楽ではそのまま「演奏を聴くこと味わうこと」と言えると思います。
質の良いインプットが出来る機会を与えてあげて下さい。
必ず良いものがアウトプットされる時が来ます。
じっくり時間をかけて見守ってあげてほしいと思います。
引用が長くなってしまいました~

ふ~む・・・と思うことばかりで。。
著者の山本豊津さんは、日本で初めて現代アートを扱う画廊の家の方ですが、美大出身でありながら、はじめは大蔵省の秘書・・と言う政治の世界に身を置いていた方です。
ですから政治的な側面からの洞察も鋭く、考えさせられることだらけです。
そして芸術の価値について最後に語られています。
それは「品格」だ・・と。
―――「品格」とは、何事にもおもねらず、はったりを利かせたり、ごまかそうとしたりすることが全くなく、それにより利益を上げたりことさらよく見せようという気持ちもないものだ、と書かれています。
おもねったり、取り入ったりしようとしない。その態度を維持するためには、自由であること。自分の価値と感覚で「自立していること」が必要です。何かの価値や権威に依存していたり頼っていたりするうちは、その自立性は生まれて来ないのです。品とか品格というのは、そういうところからおのずとにおいたってくるものなのではないかと思います。






たまたま音楽ということに関わることになった自分のライフスタイルですが、とても意味深いものを感じます

殊に最近、考えれば考えるほど、やはり音楽をすることには大きな意味があるなぁ~と思ってしまいます





より豊かで才気溢れる人材を育成する為にも、音楽を始めとする芸術は重要です。
これからの人たちは、激動の現代社会、世界的な視野を持たなければならないと感じます。
情勢の変化は加速度化しています。
良い方向へ舵を切るのは、大人たちの考え方にかかっているのではないでしょうか?
私の世代はおろか、若いご両親の受けた教育と同じ・・と言う視点を打ち破っていく必要がありそうです。
そして、学びは「喜び」と「感動」が必要です。
愛や喜びや感動のない学びは、本当の力になりません。
アート=「自由」「品格」
物事に捕らわれず、Artist(=Person) who has something to say・・・語るべきことを持っている人、そういう人が世界と繋がれるのだと思います。
親子で楽しむ

というスタンスで、音楽やアートとともに自由に日常を豊かにお過ごしくださいませ


今日の語り口はちょっと熱かったかなぁ~~









 :in addition
:in addition :for your information
:for your information












































































 ・・・あとちょっとだけ・・
・・・あとちょっとだけ・・