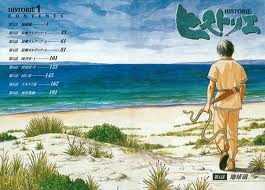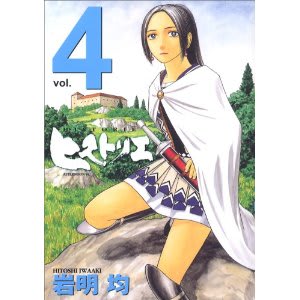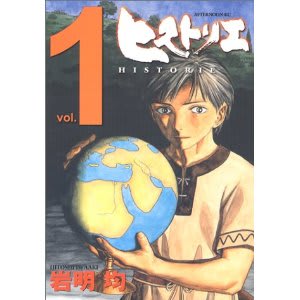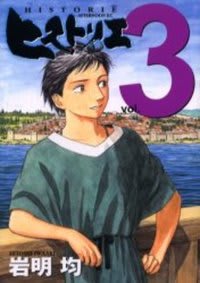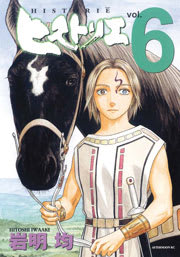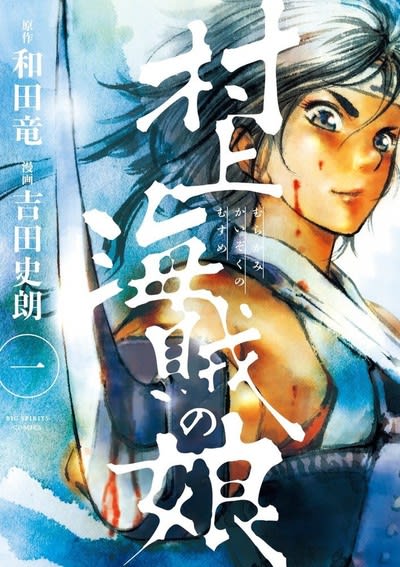
村上海賊の娘
『のぼうの城』の和田竜先生の
最新作『村上海賊の娘』をお送りします。
↑の絵が『村上海賊の娘』こと
主人公の村上景です。

マンガ連載も始まりました。

「さぁ、海賊の時間だ!」
海賊つながりということで・・・(^-^;)

第一次木津川口の戦い
『村上海賊の娘』は、
毛利と織田信長の戦(いくさ)である
「第一次木津川口の戦い」を
描きます。
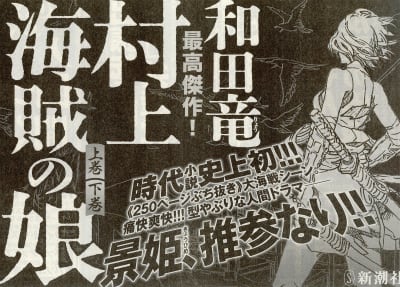
作者の和田竜先生は『マッドマックス』(古い方)
などのアクション映画がお好きで
『村上海賊の娘』は海戦のシーンが
長いです。
↑250ページと宣伝されていますし。
実は『村上海賊の娘』は主人公の村上景が
出るまでちょっとページの枚数が
かかります。
それで時代背景などが語られますが、
『信長の忍び』の重野なおき先生が
大河ドラマ『軍師・官兵衛』を見て
描いた絵や、『修羅の刻』などの絵で、
『村上海賊の娘』の登場人物を紹介
したいと思います。
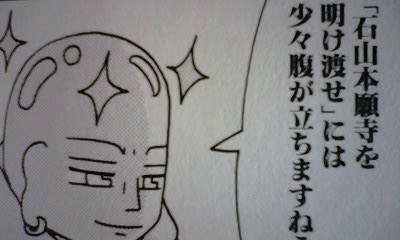
本願寺顕如

鈴木孫一

小早川隆景と吉川元春
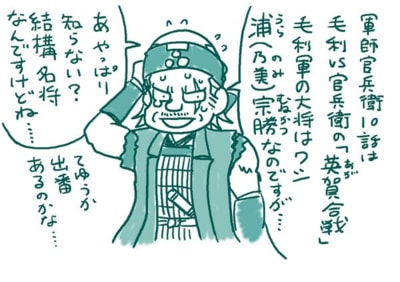
乃美宗勝

↑『村上海賊の娘』は、こんな感じで
大変な戦況となっています。
(これはもう少し後のことですが・・・)
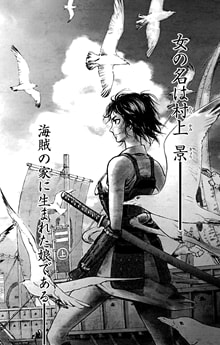
村上景
村上景は『村上海賊の娘』のタイトル通り
海賊の頭領の娘なんですよ。
もちろん海賊の娘だから(?)とても強い
のです。
だけど村上景の魅力はそれだけでは
ありません。

村上景は作中でブサイク、ブサイク
言われるんですが、現代の美的感覚から
すれば美人なのはお約束です♪(笑)
村上景が美人と言われて喜んでいるのが
どこかかわいらしいのです♪
あと和田竜先生はナウシカがお好きなようで
村上景にも、ちょっとナウシカが入ってる気が
します。
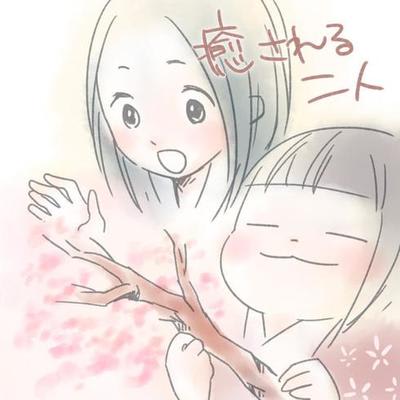
そしてお約束のように平安時代的な美人の
琴姫が登場し、村上景とちょっと張り合うのです
が・・・村上景の方がキレイになってるのも
お約束です☆(笑)
なんとなく琴姫は高畑勲の『かぐや姫』に
出てきた女官のイメージがあります。
あの女官も可愛かったですが♪
そして 出番は少ないながら、琴姫の一言が
村上景を突き動かすのです。

村上景は、とある事件から
戦うこと、そのものを忌避するように
なります。
読んでる方からすれば、あれだけ強い
村上景の初めて見せる弱さに驚き、そして
ギャップに萌えることになります♪

そこから村上景が復活するのですが、
恵まれてるというか、良い人が多いというか
みんな、どこか村上景のことが好き
なんですよ、お父さんとか弟とか(笑)
いい味だしてるキャラが多いのですが
ちょっと人数が多いので、書くのを
あえて村上景1人に絞りました。
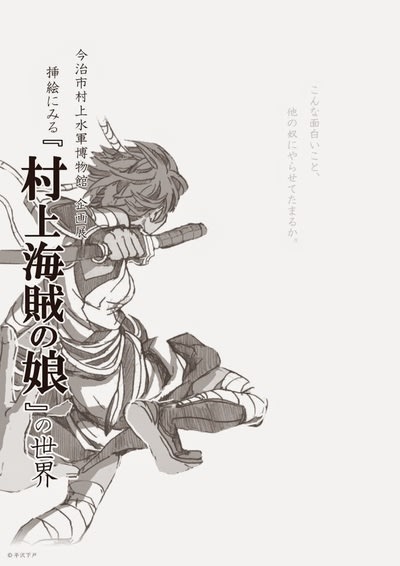
『村上海賊の娘』は村上景という
1人の少女を描き切った話だと思います。
私は、この小説を読んで、
『アルスラーン戦記』の田中芳樹が書いた
初の歴史小説、『風よ、万里を翔けよ』を
思い出しました。
そして『村上海賊の娘』は終章で
登場人物の、その後を書くのですが
どこか不思議な余韻が残りました。
あと海賊たちの戦いに対する考え方。
譜代の臣とかなら忠義や忠誠が
戦う理由になりますが、海賊たちの考えは
まず生き残ることで忠義は二の次で、
だからこそ仲間や身内、家族を大事にするん
だなぁ、と思いました。