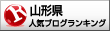米沢新聞の21日の一面に、舘山城跡が国の重要な史跡として答申されたことが載っていた。昨年の9月末に史跡を見学したことがあったので、改めて地元米沢の人間として大変誇らしく思えることである。
今年の5月半ば、斜平山の麓にある伊達家の重臣、片倉小十郎の居城跡(現在発掘調査中)のある片倉山を経由して愛宕山に登った時、史跡解説に同行した米沢市の文化財の担当者が、今回の答申の動きについて話していた。
↓ 以下の記事は、やまがたニュースオンラインからコピーしたものです。
文化審議会、県内2史跡を答申 舘山城跡(米沢)は新規、嶋遺跡(山形)は追加

嶋遺跡(山形市)のほか戦時中に首相を務めた近衛文麿が住み、日米
開戦前の重要な会議の舞台になった「荻外荘(てきがいそう)」(東
京都)など9件を史跡に、巨大で優美な樹形で知られる伊平屋島の念
頭平松(ねんとうひらまつ)(沖縄県)など5件を天然記念物に指定
するよう馳浩文部科学相に答申した。名勝2件の指定も求めた。近く
答申通り告示され、史跡は1759件、名勝は398件、天然記念物は
1021件になる。
県文化財・生涯学習課によると、舘山城跡は、伊達家が勢力を拡大した1587(天正15)~91年、政治的・軍事的拠点となった城館跡。小樽川と大樽川の合流地点付近の標高310~330メートルの丘陵に立地する。山城と住まいの跡が良好な状態で残り、面積は約6万3千平方メートル。米沢市教委の発掘調査の結果、伊達家が治世に当たった16世紀代と、上杉家の米沢入封直後の17世紀前半の遺構があることが判明している。

史跡指定を受けた。現在は山形市が「嶋遺跡公園」として整備中。住
居跡や高床式の倉庫跡をはじめ、多数の土器が出土している。
2010年の追加指定によって計約1万2千平方メートルが史跡面積と
なっており、今回新たに約8845平方メートルが追加される見込みと
なった。同エリアからは脱穀農具などの木製品が多く出土している。
正式に決定すれば本県の史跡、名勝、天然記念物は合計53件となる。史跡
以外では、名勝9件、天然記念物16件。 嶋遺跡(山形市教育委員会提供)
きのうの雨も上がり、今日は秋晴れの行楽日和になった。午後から、「置賜退教協」主催の『舘山城跡発掘現場見学会』に参加した。参加者の3人にひとりは顔見知りで、かつて勤務した職場の先輩や同僚、部活動の顧問として大会などで顔を合わせた人たちである。
米沢市の西部、舘山発電所のある山の中腹に、伊達氏の城跡があり、現在も発掘調査が進んでいる。歴史とロマンを感じさせる場所である。上杉氏の景勝公の時代にも、家臣がこの城を使っていいたらしいが、江戸時代の初期の段階で使われなくなったとのことである。市の教育委員会の発掘調査を担当している人から、詳しい説明をしてもらい、大変有意義な見学会になった。
ところで、今年の7月初めに、上越市にある上杉氏の春日山の城跡を見学したが、同じ山城と言うこともあり、険しい山道を歩いてたどり着くという点や、眺望が大変いい所など、いろいろと共通点があった。ただ、上越の春日山には舘山城跡程広い平地の部分は少なかった。舘山の城跡には広葉樹の自然林の中に、杉の大木が生い茂り、昔の面影が薄れてしまうところがあるが、春日山はほとんどが広葉樹で昔の面影が強く残っていた。
見学会の後、米沢市街の紹湯苑に場所を移動して、懇親会が開催された。久し振りの美味しいビールや日本酒を飲みながら、旧交を温めることが出来た。




↑ この一枚は今回追加したものです。(昨年のブログには載っていません)

↓ 以下の2枚の写真は、オリジナル写真を見易く拡大しています。(昨年のブログ写真をトリミング)


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ブログをご覧いただき、ありがとうございました。 (*^-^*) 
 「ポチッ!」 思いがけないブログに巡り合うことが出来ます。
「ポチッ!」 思いがけないブログに巡り合うことが出来ます。  「ポチッ!」
「ポチッ!」