青春18きっぷ・・・乗り鉄、駅鉄の旅です。
青春18きっぷ・・・JR全国各社がが売り出している
特別企画乗車券。JRの各駅列車、快速列車に1日乗り放題、5回使用可、12050円。
今回は
JR東海道線から
JR飯田線、JR中央線を・・・コロナ禍戒厳令の出る前の三日間の急ぎ旅・・・
今日で3日目、最終日、豊橋から飯田線で195㎞の辰野駅まで、辰野駅から中央本線で209.8㎞の新宿まで、合計500㎞に及ぶロングトラベル。
飯田線始発駅の豊橋から豊川に沿って新城駅っ三河川合駅。峠を越えて相川、大千世川の天竜川水系の東栄駅、出馬駅、天竜川沿いの中部天竜駅、そしてトンネルを潜って水窪川沿いの水窪駅に。ここからは秘境駅ゾーンに入ります。
飯田線の静岡県最北端の駅「
小和田」・・・静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家・・・車窓から駅名標をパチリ。
集落無し、車道無し、乗降客無し、1日上り列車8本、下り列車9本、
秘境中の秘境駅・・・
1936年開業、1面1線の無人駅、佐久間ダムの完成で
小和田集落は湖底に。

※撮影日は3月27日。
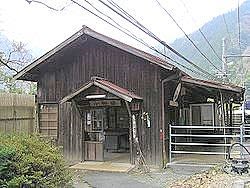
★
小和田駅舎(
写真はWikipediaから)・・・中部天竜駅管理の無人駅。数年前までトイレもあったが撤去。人家がないので郵便業務、新聞輸送もなし。対岸は愛知県豊根村富山地区、県道1号線が走っているが人家はない。長野県境に駅から約1㎞。愛知県への橋、長野県に通じる車道はない。
★
1日の乗客数・・・1990年代まで10人以上、2000年代に入り5~6人に、最近は鉄ちゃん、秘境マニアが3人程度、生活路線としての乗客は?
★
人家は・・・人道を4~5㎞、急傾斜の山道を約1時間、標高650m(
小和田駅との標高差350m)の塩沢集落。4世帯ほど?集落からは車道で山道を20㎞ほどで長野県天竜村平岡、静岡県水窪へ。
★1993年
皇太子(
現天皇)成婚のとき、皇太子妃
雅子さんの旧姓
小和田にちなんで訪れる人で賑わったとか。
★
小和田の地名由来は・・・川の作った曲がった小さな沖積地・・・小輪田・・・であろうか?
※コメント欄オープンしています。
・URL無記入のコメントは削除します。
・当ブログ無関係のコメントは削除。
















 }
}

 名古屋駅到着・・・まずは駅名標をパチリ。
名古屋駅到着・・・まずは駅名標をパチリ。





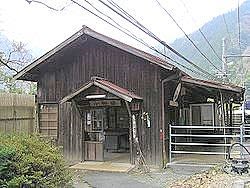 ★小和田駅舎(
★小和田駅舎(
 ★大嵐駅(
★大嵐駅(










