コロナ禍で蟄居城消ための外に出てウォーキング…近くの近郊鉄道の駅と駅の間、片道は電車に乗って。
今日は秩父鉄道
行田市駅から出発して、東行田駅、武州荒木駅、新郷駅、西羽生駅と秩父鉄道沿線を経由して羽生駅までウォーキング。
その前に映画「
のぼうの城」でお馴染みの「
忍城」へ。

現在の行田市あたりはむかし武蔵国さきたま郷・・・5世紀から7世紀に作られたと推定される9基の大型古墳群、平安時代から豪族成田氏を中心として栄え戦国時代の1478年忍城が築城されたといわれます。1590年豊臣秀吉の小田原城攻めのとき,小田原北条氏の支城である忍城は秀吉家臣の石田三成を大将とする豊臣軍に攻められたがよく持ちこたえ小田原城が陥落後に開城。江戸時代に入り、徳川家親藩の忍藩領となり東条松平氏、阿部氏、奥平松平氏と藩主が変わって幕末を迎えます。城としての縄張り、天守三層櫓は阿部氏の代の1702年のころ形成されといいます。1871年廃城に。ほとんどすべてが撤去。現在の天守三層櫓は1988年建造の鉄筋コンクリート製の模擬城です。

忍城攻防を描いた物語り・・・「のぼうの城」の舞台です。
和田竜が2003年オリジナル脚本「忍ぶの城」として発表、2007年ノベライズ化して小説「のぼうの城」を発刊、2008年コミカライズ「のぼうの城」がビックコミックで連載。2012年映画「のぼうの城」が公開されました。


水城公園・・・
忍城攻めの豊臣方の本陣は現在の
さきたま古墳の
丸墓山古墳の上、忍城との距離は約1㎞、湿地で囲まれた
忍城は
浮き城と呼ばれました。

※撮影日は3月26日。
《「
のぼうの城」の大まかなストーリー》
ときは1590年6月、豊臣秀吉の天下統一の最終章「
関東の北条氏征伐」。本城の「
小田原城」を攻め、同時進行で関東一円の支城を攻め落としていく。支城の一つ「
忍城」(
現在の行田市)攻防の歴史的事実にそって物語は進行する。
「
のぼうの城」の「
のぼう」とは「
でくのぼう」の略、役に立たない、頼りにならないもののことをいい…城主成田氏の従弟、城代の子、
成田長親のこと。城主は小田原城に出仕、後を任された城代が急死、「
のぼう」が城の総責任者になります。
戦いは約40日間、石田三成を総大将とする豊臣軍20000、忍城の武士500、百姓が加わり約3000に。あっという間に踏みつぶされそうなものですが、この「
でくのぼう」…奇策をもって耐えます。忍城の周りはいまは市街地と田畑しか見えませんが当時は荒川(
現在は元荒川)と利根川に囲まれた扇状地の伏流水の湧く湿泥地だったといわれます。城に至る道は一本道、沼沢地の中に浮く
浮城といわれました。
石田三成は水攻めの策をとります(
秀吉の策とも言われますが定かではありません)。城の周りに堤を作り(
作ったのは石田軍の軍費により土方仕事をした地元の百姓です)。、荒川、利根川の水を導水して溜めます。映画ではこの策はあることで失敗します。台風による大洪水で逆に石田軍に死傷者が出たともいう説もあります。この堤は総延長28㎞といわれ現在も一部が石田堤の名前で残り史跡公園になっています。
この「
でくのぼう」成田長親は百姓に人気があります。最後は百姓に助けられます。なぜでしょう。
開城後、藩主成田氏長は蒲生氏預かりになり会津に、のちに野州烏山城主に、長親は氏長に従ったがのちに出家。烏山を去って長子長季が仕官した東条松平家の領地尾張清州にて死去と伝えられます。
★詳しくは小説、コミックで・・・
※コメント欄オープン。





















 NHK大河ドラマ「
NHK大河ドラマ「

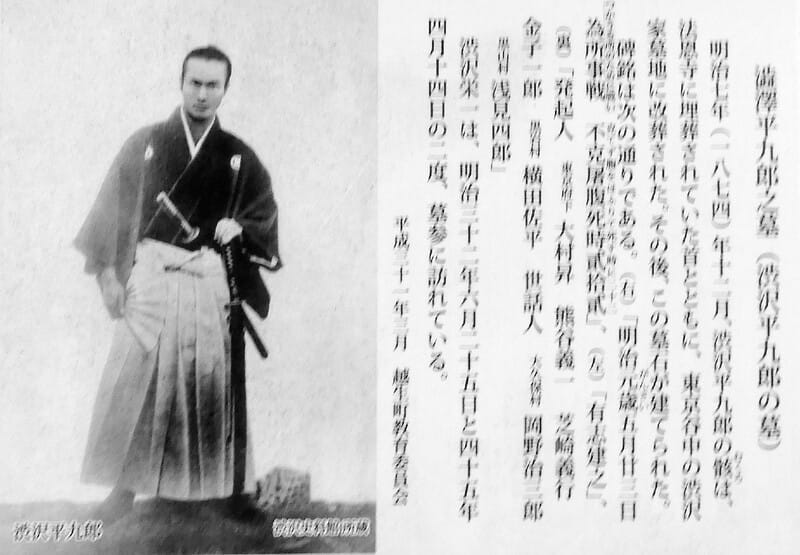







 3月27日、晴天。久しぶりの外出、熊谷市大麻生の桜堤で・・・サクラと菜花と秩父鉄道SLパレオエクスプレス号のコラボレーションを堪能。
3月27日、晴天。久しぶりの外出、熊谷市大麻生の桜堤で・・・サクラと菜花と秩父鉄道SLパレオエクスプレス号のコラボレーションを堪能。















 さて渋沢栄一(
さて渋沢栄一(


