1月14日、久しぶりに渡良瀬遊水地を歩きました。寒いのですが風のない日、旧谷中村跡・・・(といっても一面の葦の原とところどころにある屋敷のあったという標柱だけですが)・・・を8X双眼鏡と10Xデジカメを持ってブラブラと鳥見散歩です。

1741年鋳造の梵鐘。
久喜市の火の見櫓に使われていたものが里帰り。
実物は藤岡町(現栃木市)の歴史資料館に。これはレプリカです。

渡良瀬川の最上流の足尾銅山、そしてこの谷中村をつなぐ線が近代日本の公害の原点です。
谷中村に関する過去ログです。
2008年5月22日・・・「渡良瀬遊水地・・・延命院の鐘」
2008年5月27日・・・「渡良瀬遊水地・・・谷中村(終章)・・・墳墓の丘」
2008年3月20日・・・「渡良瀬遊水地・・・野焼き(終章)・・・谷中湖」
延命院の赤い鉄の箱の中にある谷中村たよりを持って帰り読んでいます。ラムサール条約登録(湿地の動植物保護の国際条約)を申請してるそうです。次回の開催は2012年5月のようです。日本では37の登録地があります(尾瀬、奥日光の湿原、琵琶湖などですが有名でないところもいっぱいあります)。渡良瀬川の鉱毒の集積地として作られた人工的な湿地であり国際空港とか演習地とかそういう計画もあるようですが、今は貴重な動植物の宝庫のような自然湿地になりました。ぜひ条約登録が実現してほしいです。連絡ノートの抜粋も載せられています。小学生、九州から来た人、韓国姓、中国姓の人も書かれています。
ゆっくりと歩いても30分も歩けば一回りですが、帰りに高い木の枝の中にトンビが・・・さらに少し歩くとノスリもいました。いちおう猛禽ですから写真を撮ろうと車に戻って24Xのカメラを持ってふたたび木の下に。じっと待っていてくれました。
葦刈りの作業をする人たち。

旧谷中村の氏神様・・・雷電神社跡・・・今は小高い塚と標柱のみ。

標柱の下にお賽銭が・・・尊い。

旧谷中村の延命院跡。梵鐘と赤い鉄の箱(中に誰でも書くことのできる連絡ノートと手作りの谷中村たよりが入っています)。
旧谷中村の氏神様・・・雷電神社跡・・・今は小高い塚と標柱のみ。

標柱の下にお賽銭が・・・尊い。


1741年鋳造の梵鐘。
久喜市の火の見櫓に使われていたものが里帰り。
実物は藤岡町(現栃木市)の歴史資料館に。これはレプリカです。

延命院の鐘から振りかえると旧谷中村の村びとたちの共同墓地跡です。
廃村になったのは1906年、もう105年たっています。
・・・新しい卒塔婆とその下にお花が。

共同墓地のランドマーク・・オオクヌギです。

廃村になったのは1906年、もう105年たっています。
・・・新しい卒塔婆とその下にお花が。

共同墓地のランドマーク・・オオクヌギです。

渡良瀬川の最上流の足尾銅山、そしてこの谷中村をつなぐ線が近代日本の公害の原点です。
谷中村に関する過去ログです。
2008年5月22日・・・「渡良瀬遊水地・・・延命院の鐘」
2008年5月27日・・・「渡良瀬遊水地・・・谷中村(終章)・・・墳墓の丘」
2008年3月20日・・・「渡良瀬遊水地・・・野焼き(終章)・・・谷中湖」
延命院の赤い鉄の箱の中にある谷中村たよりを持って帰り読んでいます。ラムサール条約登録(湿地の動植物保護の国際条約)を申請してるそうです。次回の開催は2012年5月のようです。日本では37の登録地があります(尾瀬、奥日光の湿原、琵琶湖などですが有名でないところもいっぱいあります)。渡良瀬川の鉱毒の集積地として作られた人工的な湿地であり国際空港とか演習地とかそういう計画もあるようですが、今は貴重な動植物の宝庫のような自然湿地になりました。ぜひ条約登録が実現してほしいです。連絡ノートの抜粋も載せられています。小学生、九州から来た人、韓国姓、中国姓の人も書かれています。
ゆっくりと歩いても30分も歩けば一回りですが、帰りに高い木の枝の中にトンビが・・・さらに少し歩くとノスリもいました。いちおう猛禽ですから写真を撮ろうと車に戻って24Xのカメラを持ってふたたび木の下に。じっと待っていてくれました。











 神岡の町を俯瞰した神岡城址にある擬城。神岡城は戦国時代の1564年築城され、1615年一国一城の定により取り壊され石垣と堀のみが残されました。1970年三井金属鉱業100周年記念事業で模擬天主閣、模擬城門、鉱山資料館、郷土館が作られたのだそうです。
神岡の町を俯瞰した神岡城址にある擬城。神岡城は戦国時代の1564年築城され、1615年一国一城の定により取り壊され石垣と堀のみが残されました。1970年三井金属鉱業100周年記念事業で模擬天主閣、模擬城門、鉱山資料館、郷土館が作られたのだそうです。 城址を出て国道471号線を下りていき橋を渡ると廃駅の神岡鉱山前駅、ここからふたたび国道41号線で富山方面に、三井金属エンジニアリング、神岡鉱業所、道が狭く駐車するところが見つからないので、ちょっと遠いところで工場群を撮りました。
城址を出て国道471号線を下りていき橋を渡ると廃駅の神岡鉱山前駅、ここからふたたび国道41号線で富山方面に、三井金属エンジニアリング、神岡鉱業所、道が狭く駐車するところが見つからないので、ちょっと遠いところで工場群を撮りました。
 富山県婦中町の「学問もない、地位もない、バックもない」開業医萩野昇と神通川の扇状地に広がる奇病との戦いがテーマです。水質検査、ウイルスの検査、没落地主のわずかに残った田畑まで処分し自費で研究に没頭します。岡山大学理学部の小林純の協力を得てカドミュームの存在を見つけ神通川の上流高原川の三井金属鉱業㈱神岡鉱山の亜鉛鉱石の精錬によるものであることをつきとめます。いつの世でもあることですが古い学閥の体制側からや企業に与する側から誹謗・中傷、脅迫・妨害、バッシングを受けます。1967年国会参議院で証言、1968年公害病の認定。三井金属は1968年提訴され、1971年原告が勝訴しました。
富山県婦中町の「学問もない、地位もない、バックもない」開業医萩野昇と神通川の扇状地に広がる奇病との戦いがテーマです。水質検査、ウイルスの検査、没落地主のわずかに残った田畑まで処分し自費で研究に没頭します。岡山大学理学部の小林純の協力を得てカドミュームの存在を見つけ神通川の上流高原川の三井金属鉱業㈱神岡鉱山の亜鉛鉱石の精錬によるものであることをつきとめます。いつの世でもあることですが古い学閥の体制側からや企業に与する側から誹謗・中傷、脅迫・妨害、バッシングを受けます。1967年国会参議院で証言、1968年公害病の認定。三井金属は1968年提訴され、1971年原告が勝訴しました。
 ・・・谷中村共同墓苑の板塔婆。
・・・谷中村共同墓苑の板塔婆。






 ・・・谷中村についての説明板。
・・・谷中村についての説明板。





 石牟礼道子著>「苦海浄土」(講談社1968年刊)。
石牟礼道子著>「苦海浄土」(講談社1968年刊)。
 小説「神通川」は婦中町の「学問もない、地位もない、バックもない」開業医と神通川の扇状地に広がる奇病との戦いがテーマです。水質検査、ウイルスの検査、没落地主のわずかに残った田畑まで処分し自費で研究に没頭します。備州大学(岡山大学)理学部の大森教授(小林純)の協力を得てカドミュームの存在を見つけ神通川の上流
小説「神通川」は婦中町の「学問もない、地位もない、バックもない」開業医と神通川の扇状地に広がる奇病との戦いがテーマです。水質検査、ウイルスの検査、没落地主のわずかに残った田畑まで処分し自費で研究に没頭します。備州大学(岡山大学)理学部の大森教授(小林純)の協力を得てカドミュームの存在を見つけ神通川の上流 夏の思い出です。
夏の思い出です。 新田次郎・・・気象庁の元技官。敗戦の年、朝満国境にいてたいへん苦労します。奥さんが子供を連れて命からがら帰国したことは藤原てい「流れる星は生きている」(日比谷出版社、1949年刊絶版、現中央公論社刊)で知られています。
新田次郎・・・気象庁の元技官。敗戦の年、朝満国境にいてたいへん苦労します。奥さんが子供を連れて命からがら帰国したことは藤原てい「流れる星は生きている」(日比谷出版社、1949年刊絶版、現中央公論社刊)で知られています。


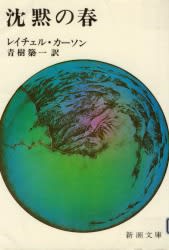 2007年5月27日、今日は何の日?
2007年5月27日、今日は何の日?