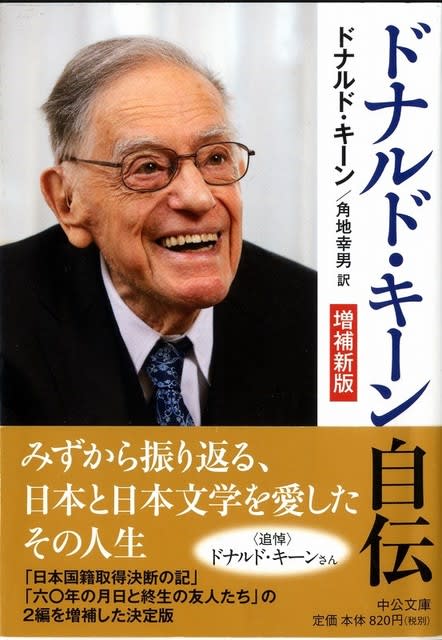
ドナルドキーン氏は、外国人から見た日本と評価されることが嫌いなようです。あくまで、個人の研究として考えていたようです。これは、多民族で個人を主張する米国の中で育ったことも大きいのではないかと思います。加藤周一氏のように、物言えぬ日本での苦悩の中で、その後日本人全体をの特殊性を研究する姿勢とは正反対です。
氏は第二次世界大戦という大嫌いな時代の中で、源氏物語という別世界に入り込みんだようです。通訳として軍役についたときも、頭の中は日本文化への興味でした。加藤周一氏のように、物言えぬ日本での苦悩とは正反対で、ある意味で米国の余裕が育てたともいえます。
キーン氏は、最後まで日本文化にあこがれ惚れ込み、研究を進め、加藤氏は日本の未来への責任という実践的な姿勢があります。
キーン氏は恵まれた生活条件と才能と努力を発揮していき、あくまで個人の興味として日本文化を研究し、アメリカ社会の分析はほとんどありません。加藤氏は日本の個性の遅れを意識しつつ、冷静な分析をされています。
近著「オペラへようこそ」でもそうですが、自伝でも友人である、三島由紀夫・川端康成・安部公房などについても、人間として作品としての評価は、2面的な側面を冷静に見つめています。
平和主義が原点の述べており、ある一定以上の分析と提言は持っていたのでしょうが、それは、書かれていません。
私の課題である、日本人とは何かについては、今後の氏の日本文学史などを読んでみたいと思っています。












