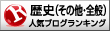「あっ、お父さんだ!」
テレビを見ていた母が叫んだ。指さすほうを見ると、大岡越前の加藤剛であった。
あれ? 昔聞いた母のお父さん、つまり私の母方の祖父は、高橋幸治から甘さを抜いた感じの男前だった、と言っていたように思ったけど……
待て待て、そいえば、この前は、田村高廣を、隣に住んでいた人、と言ってたしなぁ。
街の風情が21世紀になってすっかり変わったように、しゃべる言葉や食べるものが変わって顎の筋肉の動き方が変化したためか、人間の顔もやはり昔とはずいぶん違ってきた。昭和のころ撮影されたフィルム群を見ていると、記憶の中の知り合いによく出会う。
親戚付合いが先代で絶えて、消息はもう分からなくなってしまったのだけれど、子ども心に鶴田浩二にそっくりだと思っていた母方の大叔母の弟は、予科練の生き残りであった。
婚約者が不治の病で入院していた時に、お見舞いに来た婚約者の友人との間に恋愛感情が芽生え、駆け落ちした。
戦後のゴタゴタした時代には、身近に様々なことが起きるので、劇作家はドラマチックなストーリーを編み出すのに、今ほど苦労はしなかっただろう。
さて、母の父は、ずいぶん風邪が長引くなぁ…と周りが思っているうちに、母が高校生のとき白血病で急逝したので、私は祖父の顔を知らないのだ。
きりっとした鼻が高い大正生まれの好男子で、第二子出生の折、連れ合いを亡くした。曾祖父の代に内陸のT県OT原から海に面したI県K浜に出て、主にランプとその油を商い、電気が浜辺の町に通い発展するにつれ、塩やたばこの専売品、郵便切手、生活雑貨、青物、食料品などを扱うようになった。
夏になると、店の横合いに床几を出し、ところてんを、今でいうセルフで出していた。水を張った大きな桶の中に、心太が一本売りされている。その中から、ところてんを取り出してもらい、自分で突いて、酢醤油で食べるのがおいしかったのを覚えている。
母が学校から帰ってくると、おとうさんは女の人に誘われて、いつもお茶屋さんに行ってなかなか帰ってこなかった。母はそれが嫌だった。それを案じてか、商店を切り盛りし、残された二人の子供の面倒をみていた曾祖母が、祖父に後添えを迎えた。
曾祖母は、私が中学1年生の時に亡くなった。気持ちのしっかりとした、頭脳明晰な刀自であった。子どものころはあまりにも長いこと生きている時代がついた古びた感じの、その存在がとても怖くて、私は曾祖母と話ができなかった。曾祖母の葬式の時、“スイ(萃…という字だったか翆という字だったか…)”という、彼女の名をはじめて知った。…ぁぁ、おばあさんにも名前があったのだ、同じ人間だったのだ…と、うかつにも気が付いた。
お彼岸に、妹夫婦が母を墓参りに連れて行ってくれるというので、小旅行用の鞄を探していたら、戸棚の中から大事にしまっていた平成16年・東方出版刊『柴田是真 下絵・写生集』が出てきた。いや、出てきたのではなくて、いつもそこにしまってあったのを、改めて取り出してみたのである。
夏の終わりに、母の新しい塗り絵帳を探しに出向いたら、なんということでしょう、『柴田是真の植物画 季節のぬりえ帖』というのを、書店の棚の中に見つけたのだ。
がびーーーん、世の中は再び進化した。青月社、という美しい名前の会社が版元だった。
やはり蛙の母はカエル。元気なころは美術館の解説ボランティアをしていた母も、柴田是真がたいそう気に入った様子で、ここ2週間ほど、一心不乱に塗り絵に没頭した。
しかし、それがために宮沢賢治の書き取り帳がおろそかになり、先週、字が読めなくなっていたので、私は慌てた。
そんなことがあって、今まで見せたことがない画集を母に見せてみようという気になったのだ。
何年ぶりであろうか、帙入りの大判の本をテーブルに広げ、二人で眺めた。
母は歓声を上げて、ページを繰っている。
「おとうさんはねぇ、何でも買ってくれたの…」
と、いつの間にか、祖父が母に買ってくれた本であったように錯覚したらしい。
「こんな本があったの? はじめて見た…」
もちろん、この本を見せたのは初めてであるが、「こんなのはじめて」というこの言葉は、このところ母の口癖であった。記憶の消失とともに、はじめてのことが矢鱈と多くなったのだろう。母が無邪気で、いつも新鮮な気持ちでいられるのは私にとっても嬉しいことである。
懐かしい、しかしいつ開いてみても常に新しい、瑞々しい生命力に満ちた是真の筆致。
“筆”文化の極致。血の通った流麗さは、日常筆に親しんだ者が為せる粋。
そうだった、母は書道も好きで、殊にかな文字を嗜み展覧会にも出品していたのだった。
…母が時折、私のことを「おとうさん」と呼んだりするのは、わたくしを自分の保護者と思っているからなのか、それとも、生前の私の父に呼びかけていた日常生活の記憶の断片が、傍らの人に呼びかける無意識の「もしもし、」という感嘆詞になっているためなのか。
テレビを見ていた母が叫んだ。指さすほうを見ると、大岡越前の加藤剛であった。
あれ? 昔聞いた母のお父さん、つまり私の母方の祖父は、高橋幸治から甘さを抜いた感じの男前だった、と言っていたように思ったけど……
待て待て、そいえば、この前は、田村高廣を、隣に住んでいた人、と言ってたしなぁ。
街の風情が21世紀になってすっかり変わったように、しゃべる言葉や食べるものが変わって顎の筋肉の動き方が変化したためか、人間の顔もやはり昔とはずいぶん違ってきた。昭和のころ撮影されたフィルム群を見ていると、記憶の中の知り合いによく出会う。
親戚付合いが先代で絶えて、消息はもう分からなくなってしまったのだけれど、子ども心に鶴田浩二にそっくりだと思っていた母方の大叔母の弟は、予科練の生き残りであった。
婚約者が不治の病で入院していた時に、お見舞いに来た婚約者の友人との間に恋愛感情が芽生え、駆け落ちした。
戦後のゴタゴタした時代には、身近に様々なことが起きるので、劇作家はドラマチックなストーリーを編み出すのに、今ほど苦労はしなかっただろう。
さて、母の父は、ずいぶん風邪が長引くなぁ…と周りが思っているうちに、母が高校生のとき白血病で急逝したので、私は祖父の顔を知らないのだ。
きりっとした鼻が高い大正生まれの好男子で、第二子出生の折、連れ合いを亡くした。曾祖父の代に内陸のT県OT原から海に面したI県K浜に出て、主にランプとその油を商い、電気が浜辺の町に通い発展するにつれ、塩やたばこの専売品、郵便切手、生活雑貨、青物、食料品などを扱うようになった。
夏になると、店の横合いに床几を出し、ところてんを、今でいうセルフで出していた。水を張った大きな桶の中に、心太が一本売りされている。その中から、ところてんを取り出してもらい、自分で突いて、酢醤油で食べるのがおいしかったのを覚えている。
母が学校から帰ってくると、おとうさんは女の人に誘われて、いつもお茶屋さんに行ってなかなか帰ってこなかった。母はそれが嫌だった。それを案じてか、商店を切り盛りし、残された二人の子供の面倒をみていた曾祖母が、祖父に後添えを迎えた。
曾祖母は、私が中学1年生の時に亡くなった。気持ちのしっかりとした、頭脳明晰な刀自であった。子どものころはあまりにも長いこと生きている時代がついた古びた感じの、その存在がとても怖くて、私は曾祖母と話ができなかった。曾祖母の葬式の時、“スイ(萃…という字だったか翆という字だったか…)”という、彼女の名をはじめて知った。…ぁぁ、おばあさんにも名前があったのだ、同じ人間だったのだ…と、うかつにも気が付いた。
お彼岸に、妹夫婦が母を墓参りに連れて行ってくれるというので、小旅行用の鞄を探していたら、戸棚の中から大事にしまっていた平成16年・東方出版刊『柴田是真 下絵・写生集』が出てきた。いや、出てきたのではなくて、いつもそこにしまってあったのを、改めて取り出してみたのである。
夏の終わりに、母の新しい塗り絵帳を探しに出向いたら、なんということでしょう、『柴田是真の植物画 季節のぬりえ帖』というのを、書店の棚の中に見つけたのだ。
がびーーーん、世の中は再び進化した。青月社、という美しい名前の会社が版元だった。
やはり蛙の母はカエル。元気なころは美術館の解説ボランティアをしていた母も、柴田是真がたいそう気に入った様子で、ここ2週間ほど、一心不乱に塗り絵に没頭した。
しかし、それがために宮沢賢治の書き取り帳がおろそかになり、先週、字が読めなくなっていたので、私は慌てた。
そんなことがあって、今まで見せたことがない画集を母に見せてみようという気になったのだ。
何年ぶりであろうか、帙入りの大判の本をテーブルに広げ、二人で眺めた。
母は歓声を上げて、ページを繰っている。
「おとうさんはねぇ、何でも買ってくれたの…」
と、いつの間にか、祖父が母に買ってくれた本であったように錯覚したらしい。
「こんな本があったの? はじめて見た…」
もちろん、この本を見せたのは初めてであるが、「こんなのはじめて」というこの言葉は、このところ母の口癖であった。記憶の消失とともに、はじめてのことが矢鱈と多くなったのだろう。母が無邪気で、いつも新鮮な気持ちでいられるのは私にとっても嬉しいことである。
懐かしい、しかしいつ開いてみても常に新しい、瑞々しい生命力に満ちた是真の筆致。
“筆”文化の極致。血の通った流麗さは、日常筆に親しんだ者が為せる粋。
そうだった、母は書道も好きで、殊にかな文字を嗜み展覧会にも出品していたのだった。
…母が時折、私のことを「おとうさん」と呼んだりするのは、わたくしを自分の保護者と思っているからなのか、それとも、生前の私の父に呼びかけていた日常生活の記憶の断片が、傍らの人に呼びかける無意識の「もしもし、」という感嘆詞になっているためなのか。