ちょうど十年ほど前の二月だったか三月だったか、ただひたすら列車に乗り、郡山から磐越西線、そして会津若松で只見線に乗り換え、小出から越後湯沢に出た。
只見線の車窓は、もう春だというのに雪、雪、雪。瞳のなかに雪の記憶だけ残して、私は新幹線に乗って生暖かい風の吹く東京へ戻ってきた。
その車中で、私は懐かしい人に出会った。小学生のとき読んだ松谷みよ子の『まえがみ太郎』に出てくる、突然の洪水に備えて、常に頭に小舟を括りつけている格好の里人そのままの、枯れ枝のようにスレンダーな人に。
そのたとえは誰に話しても伝わらないだろうから、そのままあの雪景色とともに心の奥底に深くしまっていたのだが、今宵、新暦の新年を迎えるにあたり、ついと、♪お正月さんはいいもんだ……という歌詞が浮かんだ。
これは、本の文字からの記憶なのでどういうメロディになるのか分からないのだけれど、やはり『まえがみ太郎』の文中に出てきた歌だったと思う。ゆずり葉に乗って、お正月さんは突然、まえがみ太郎の家だったか、おじいさんの家だったかを訪れる。
子どものころから周囲の期待を裏切ってばかりいたので、すっかり偏向的になってしまった。
ジャスト・ミートじゃないものに惹かれる。
「巨人・大鵬・玉子焼き」なんて思いもよらない。当たり前のものをありきたりの価値観で賞翫すると、自分の存在意義が失くなってしまうような気がする。…というより、その直球度合いが気恥ずかしい。
好んでその正反対のものを偏愛し、どこか傷のあるものに惹かれた。
正攻法の大道をただ考えもなく直進するのも詰まらなく思えて、脇道を見つけるとここぞとばかりに潜り込み、やたらと横道へ逸れてしまう。
十代終わり、ジャズのスタンダードナンバーが好きで、サッチモの唄真似に磨きをかけていたころ、「明るい表通りで」…Sunny side of the streetを、クラリネットで吹いてみたけれど、言い知れぬ諦観に満ちた、切なくやる瀬ないメロディだ。
陽のあたる場所…のはずなのに、なんだか寂しい。無理やり青空に向かって口笛吹いてるような曲調は、全然明るくなくて、人間って日なたにいても…いや日なたにいるからこそ、失望感がつのる場合もあるのだった。
そういえばそのころ丸谷才一の『横しぐれ』を読むのが、友人の間で流行っていたのだが、どうしたわけだか、全然内容が想い出せない。山頭火の「後ろ姿のしぐれていくか」にまつわる話だったような気がするのだけれども。
さて、古くは正道、本道だったのに、世の中がすっかり変わってしまって、裏道のようになってしまったものがある。
敷島の日本列島の内ばかりをあちこち旅行していたら、旧跡の、自分が行きたかったところには大概行ってしまっていた。
しかし、人間、因果なもので、何の密命も帯びていないのに漂泊の想いやまず…それでも旅をせずにはいられない。
関西への旅行帰りに、いつもは通過してしまう遠州か駿河で、一息つくことにした。
♪西行法師は家を出て…長唄『時雨西行』を口ずさみながら、あまりにも一時流行ったので考えたこともなかったが、ふと、小夜の中山へ行ってみようかという気になった。
それに、旧東海道は、もはや天下の大道ではない。国道1号線にその責務をゆずり、隠遁する道なのだ。私は西の日坂方面から辿るので、まさに西行法師と同じ感覚である。
尾根へ出ると、すっかり一面の茶畑。山の斜面も向こうの谷も、さらに向こうの山の斜面も、何面もの茶畑が、天と地の間にある。静岡のお茶栽培は、江戸幕府が亡くなって、失業したお侍さんたちが入植したものだそうだから、じつに立派に丹精したものだ。
もう傾きかけた12月の陽光が、きらめきながらきれいに剪定された茶畑を照らしている。山を渡る風が冷たい。
登りはそうでもなかったが、金谷へ下りて行くその坂道が、あまりに急勾配で、難儀した。
こんなにも明るく、夕陽のあたる坂道なのに、とにかく心細い。一ノ谷兜のように峻厳で、自分の足元が滑り落ちていくようで、気が気ではないのだ。
どうにか通り過ぎることができて安堵して、思わず知らず涙が出てきたのは、風の寒さばかりではない。いにしえ人がこの山を越えるさまを想像すると、いじらしい。昔の人はたいしたもんだ。よくまあ、こんなところを自分の足で歩いた。
しかも、今は開けて茶畑になっているけれど、鬱蒼とした樹々に覆われた、恐ろしい山道だったろう。もとより人間なんて、ちっぽけなものだ。
旅は、物見遊山ではなくて、修行だ。
まだ陽の残る麓で、私は大層ホッとして、自分の生きてある身を有難く思った。
「年長けて また越ゆべしと思いきや 命なりけり小夜の中山」
昔は、お誕生日という概念がなかったので、お正月が来ると一つ、年をとった。
こう、指を折って数えてみたら、自分でもビックリするほど、いつの間にか年をとっていた。
只見線の車窓は、もう春だというのに雪、雪、雪。瞳のなかに雪の記憶だけ残して、私は新幹線に乗って生暖かい風の吹く東京へ戻ってきた。
その車中で、私は懐かしい人に出会った。小学生のとき読んだ松谷みよ子の『まえがみ太郎』に出てくる、突然の洪水に備えて、常に頭に小舟を括りつけている格好の里人そのままの、枯れ枝のようにスレンダーな人に。
そのたとえは誰に話しても伝わらないだろうから、そのままあの雪景色とともに心の奥底に深くしまっていたのだが、今宵、新暦の新年を迎えるにあたり、ついと、♪お正月さんはいいもんだ……という歌詞が浮かんだ。
これは、本の文字からの記憶なのでどういうメロディになるのか分からないのだけれど、やはり『まえがみ太郎』の文中に出てきた歌だったと思う。ゆずり葉に乗って、お正月さんは突然、まえがみ太郎の家だったか、おじいさんの家だったかを訪れる。
子どものころから周囲の期待を裏切ってばかりいたので、すっかり偏向的になってしまった。
ジャスト・ミートじゃないものに惹かれる。
「巨人・大鵬・玉子焼き」なんて思いもよらない。当たり前のものをありきたりの価値観で賞翫すると、自分の存在意義が失くなってしまうような気がする。…というより、その直球度合いが気恥ずかしい。
好んでその正反対のものを偏愛し、どこか傷のあるものに惹かれた。
正攻法の大道をただ考えもなく直進するのも詰まらなく思えて、脇道を見つけるとここぞとばかりに潜り込み、やたらと横道へ逸れてしまう。
十代終わり、ジャズのスタンダードナンバーが好きで、サッチモの唄真似に磨きをかけていたころ、「明るい表通りで」…Sunny side of the streetを、クラリネットで吹いてみたけれど、言い知れぬ諦観に満ちた、切なくやる瀬ないメロディだ。
陽のあたる場所…のはずなのに、なんだか寂しい。無理やり青空に向かって口笛吹いてるような曲調は、全然明るくなくて、人間って日なたにいても…いや日なたにいるからこそ、失望感がつのる場合もあるのだった。
そういえばそのころ丸谷才一の『横しぐれ』を読むのが、友人の間で流行っていたのだが、どうしたわけだか、全然内容が想い出せない。山頭火の「後ろ姿のしぐれていくか」にまつわる話だったような気がするのだけれども。
さて、古くは正道、本道だったのに、世の中がすっかり変わってしまって、裏道のようになってしまったものがある。
敷島の日本列島の内ばかりをあちこち旅行していたら、旧跡の、自分が行きたかったところには大概行ってしまっていた。
しかし、人間、因果なもので、何の密命も帯びていないのに漂泊の想いやまず…それでも旅をせずにはいられない。
関西への旅行帰りに、いつもは通過してしまう遠州か駿河で、一息つくことにした。
♪西行法師は家を出て…長唄『時雨西行』を口ずさみながら、あまりにも一時流行ったので考えたこともなかったが、ふと、小夜の中山へ行ってみようかという気になった。
それに、旧東海道は、もはや天下の大道ではない。国道1号線にその責務をゆずり、隠遁する道なのだ。私は西の日坂方面から辿るので、まさに西行法師と同じ感覚である。
尾根へ出ると、すっかり一面の茶畑。山の斜面も向こうの谷も、さらに向こうの山の斜面も、何面もの茶畑が、天と地の間にある。静岡のお茶栽培は、江戸幕府が亡くなって、失業したお侍さんたちが入植したものだそうだから、じつに立派に丹精したものだ。
もう傾きかけた12月の陽光が、きらめきながらきれいに剪定された茶畑を照らしている。山を渡る風が冷たい。
登りはそうでもなかったが、金谷へ下りて行くその坂道が、あまりに急勾配で、難儀した。
こんなにも明るく、夕陽のあたる坂道なのに、とにかく心細い。一ノ谷兜のように峻厳で、自分の足元が滑り落ちていくようで、気が気ではないのだ。
どうにか通り過ぎることができて安堵して、思わず知らず涙が出てきたのは、風の寒さばかりではない。いにしえ人がこの山を越えるさまを想像すると、いじらしい。昔の人はたいしたもんだ。よくまあ、こんなところを自分の足で歩いた。
しかも、今は開けて茶畑になっているけれど、鬱蒼とした樹々に覆われた、恐ろしい山道だったろう。もとより人間なんて、ちっぽけなものだ。
旅は、物見遊山ではなくて、修行だ。
まだ陽の残る麓で、私は大層ホッとして、自分の生きてある身を有難く思った。
「年長けて また越ゆべしと思いきや 命なりけり小夜の中山」
昔は、お誕生日という概念がなかったので、お正月が来ると一つ、年をとった。
こう、指を折って数えてみたら、自分でもビックリするほど、いつの間にか年をとっていた。










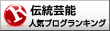

















いや~毎回冴え渡る文章、今回もまた敬服感銘を受けつつ堪能させていただきました。
本年も是非頻繁にアップして下さいませ。
とんでもhappendです。(-edが正しいのでしたっけ?)
らりーずさまの御身を削る越南紀行こそ、まさに、命なりけり…であります。
いつもながら選曲が絶妙。「蘇州夜曲」を彼の地で聴いて後悔した、前世紀末に行った中華紀行を想い出しました。
それから、昔持ち歌にしていた灰田勝彦の「きらめく星座」をくちずさんで…。
お正月なのに懐旧モード全開です。
聴き初めは、志ん朝「崇徳院」でやんした…って、アタシっていつの人?
前回の、昔の庶民の衣服は麻だった・・・に、そうだった! 木綿じゃないんだ、コメントしなきゃと思いつつ、
年が明けてしまい・・・
徳桜さんの思いがどこへ向かうのか、今年も期待しています。
志ん朝師匠亡くなって早や十年ですね。
崇徳院というと、昭和のころは仁鶴師匠の十八番でしたが、志ん朝師匠のもさすがに面白い。
ちょうど、元旦のホール落語会のライブ録音で、やんわりと愚痴のように嫌味のように枕に織り込んでいたのがさらに愉快。
B面は「御慶」でした。