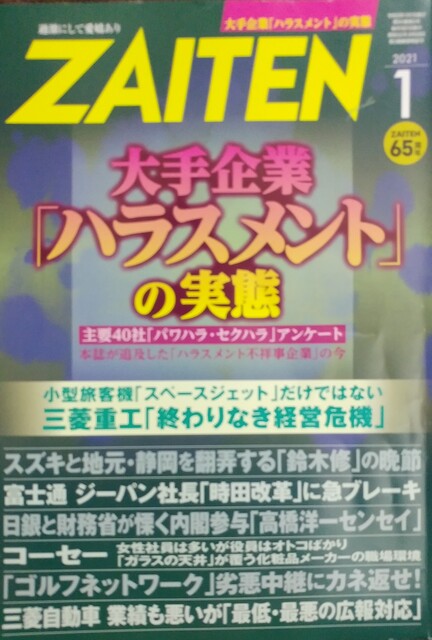働き方改革関連法案がすでに審議入りしており、世論の注目も集まってきました。この法案については、すでに様々な問題点が指摘されており、特に「高度プロフェッショナル制度」(年収1075万円以上、対象職種限定、年間104日の休日保障などの要件で労基法の労働時間規制が適用除外される制度。高プロ制。)について「過労死促進法」「定額使い放題法案」などの異名が定着しています。今年に入ってからは、政府が調査導入の是非を検討した際の基礎データが改ざんされていた問題も浮上し、政府は法案中の裁量労働制の拡大について撤回せざるを得なくなりました。
2007年の第一次安倍政権の時、現在の高プロ制の原型となった法案が「残業代ゼロ法案」と批判されて廃案になったことを意識してか、政府は、この高プロ制について「時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。」などとしており、この「時間でなく成果」が政策の宣伝文句となっていました。新聞紙でも、読売新聞、日経新聞は、いまだに「脱時間給」という世論を誤導しかねない誤ったキーワードを使い続けています。
労基法は「時間ではなく成果」もOKしている
この「時間ではなく成果」という点ですが、もともと、労働基準法は週40時間、一日8時間の法定労働時間制の範囲であれば、どのような賃金制度を契約しても、それは労使自治の問題である、という考え方をしています(ただし最低賃金法の規制はあります)。成果があがった労働者の賃金を高くすることも、成果をボーナス査定することも、何ら禁止されていないのです。
そうすると、この「時間ではなく成果」「脱時間給」というキーワードは、法定労働時間制を超えた労働や、法定休日の労働に対して、そもそも禁止する規制や、可とされる場合でも割増賃金の支払を強制する労基法の規制に対するものと考えられます。確かに、直近のところでも、医師について残業代込み込み(基本給等と判別不能)の状態で年俸1700万円とする契約はダメですよ、という最高裁判決が出されました(最二判平成29年7月7日 医療法人社団康心会事件)。
しかし、そうだとすると高プロ制の「時間ではなく成果」「脱時間給」というフレーズは「残業代ゼロ」を言い換えただけ、ということにもなります。このように労働時間規制を取り払うだけでは、https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180516-00085290/
2007年の第一次安倍政権の時、現在の高プロ制の原型となった法案が「残業代ゼロ法案」と批判されて廃案になったことを意識してか、政府は、この高プロ制について「時間ではなく成果で評価される働き方の下、高度な専門能力を有する労働者が、その意欲や能力を十分に発揮できるようにしていくことなどが求められており、健康確保措置を前提に、こうした働き方に対応した選択肢を増やしていくことも課題となっている。」などとしており、この「時間でなく成果」が政策の宣伝文句となっていました。新聞紙でも、読売新聞、日経新聞は、いまだに「脱時間給」という世論を誤導しかねない誤ったキーワードを使い続けています。
労基法は「時間ではなく成果」もOKしている
この「時間ではなく成果」という点ですが、もともと、労働基準法は週40時間、一日8時間の法定労働時間制の範囲であれば、どのような賃金制度を契約しても、それは労使自治の問題である、という考え方をしています(ただし最低賃金法の規制はあります)。成果があがった労働者の賃金を高くすることも、成果をボーナス査定することも、何ら禁止されていないのです。
そうすると、この「時間ではなく成果」「脱時間給」というキーワードは、法定労働時間制を超えた労働や、法定休日の労働に対して、そもそも禁止する規制や、可とされる場合でも割増賃金の支払を強制する労基法の規制に対するものと考えられます。確かに、直近のところでも、医師について残業代込み込み(基本給等と判別不能)の状態で年俸1700万円とする契約はダメですよ、という最高裁判決が出されました(最二判平成29年7月7日 医療法人社団康心会事件)。
しかし、そうだとすると高プロ制の「時間ではなく成果」「脱時間給」というフレーズは「残業代ゼロ」を言い換えただけ、ということにもなります。このように労働時間規制を取り払うだけでは、https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20180516-00085290/