本末転倒「労働ビッグバン」
「働かせ方」を自由化
1986年に男女雇用機会均等法、労働者派遣法が制定され、労働情勢は大きく様変わりを始めた。「派遣」は職業安定法で(一部を除いて)違法とされていた労働者供給事業が、派遣対象業務を制限することで合法化された。
それが、99年労働者派遣法改正で原則自由化され、労働者派遣業務が開花した。それは、正社員を駆逐し、賃金のダンピングを招いた。
しかし、資本はなおそれを不満として、経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)の御手洗冨士夫キャノン会長(日本経団連会長)ら民間議員は「労働ビッグバン」を提唱した。
労働ビッグバンは、働き方の多様化など労働市場の流動化を図るもの。働き方とはいかにも労働者の立場に立った物言いだが、実は働かせ方の自由化だ。
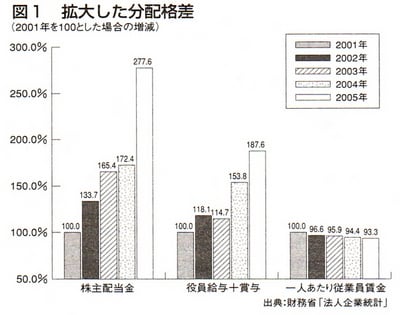
非正規労働者に対する派遣期間3年の制限を撤廃して派遣の固定化をねらい、企業が気に入らない労働者をいつでも雇い止めできる権利を留保する。
正規労働者に対しても格差の縮小を理由にあげ、正規労働者の権利を剥ぎとり、非正規と変わらぬ待遇に落とし込もうとする。
企業の勝手な解雇も金銭で解決できる方途や、裁量労働制という実際に働いた時間ではなく、仕事の実績評価で一定の時間働いたとみなして賃金を決める賃金決定システム制がホワイトカラーに99年の労働基準法の改正で採用されたが、それが業種拡大されていく。
現在、本紙でもたびたび報道しているように、違法のサービス残業(時間外手当の不払い=ただ働き)や長時間労働が日常化し、1日8時間労働制の原則は崩れ、労働時間の概念さえなくなってしまい、過労死が増加している時代である。
昨年暮れに発表された中労委の労政審報告により、労働法制の本格的改悪が準備されている。これらが通ると、「企業が労働者を直接雇用するのが原則」という労働法制の基本原則に深くかかわり、戦後60年近く守られてきたこの原則がなくなることになる。
安倍内閣の最重要課題として教育が取り上げられ、教育基本法の10条「不当な支配に服することなく」が「法律に基づく」と根幹が覆された。
そして、安倍首相は会議で「労働市場改革は内閣の大きな課題」と言明。府省横断の検討の場をつくって、この夏の「骨太の方針」に方向性や工程表を盛り込む方針と言われている。
さらに諮問会議の民間議員は、「市場化テスト」をハローワークの職業紹介事業にも導入し、労働・雇用そのもので儲けようと考えている。
労働法制の改悪は、働かなければ生きていくことができない労働力という特殊な商品の、売り手である労働者にとって、ある意味で、労働強化による健康破壊や過労死といった死に直結する問題である。
これに対して、連合などは「労働者の代表がいない場で議論されており、企業側に都合のいい中身になる」と警戒を強め、不退転の決意を見せている。今こそナショナルセンターの枠を越えた労働側総がかりの闘いが必要だ。
『週刊新社会』(2007/1/1)
「働かせ方」を自由化
1986年に男女雇用機会均等法、労働者派遣法が制定され、労働情勢は大きく様変わりを始めた。「派遣」は職業安定法で(一部を除いて)違法とされていた労働者供給事業が、派遣対象業務を制限することで合法化された。
それが、99年労働者派遣法改正で原則自由化され、労働者派遣業務が開花した。それは、正社員を駆逐し、賃金のダンピングを招いた。
しかし、資本はなおそれを不満として、経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)の御手洗冨士夫キャノン会長(日本経団連会長)ら民間議員は「労働ビッグバン」を提唱した。
労働ビッグバンは、働き方の多様化など労働市場の流動化を図るもの。働き方とはいかにも労働者の立場に立った物言いだが、実は働かせ方の自由化だ。
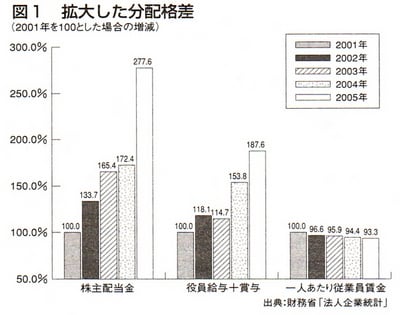
非正規労働者に対する派遣期間3年の制限を撤廃して派遣の固定化をねらい、企業が気に入らない労働者をいつでも雇い止めできる権利を留保する。
正規労働者に対しても格差の縮小を理由にあげ、正規労働者の権利を剥ぎとり、非正規と変わらぬ待遇に落とし込もうとする。
企業の勝手な解雇も金銭で解決できる方途や、裁量労働制という実際に働いた時間ではなく、仕事の実績評価で一定の時間働いたとみなして賃金を決める賃金決定システム制がホワイトカラーに99年の労働基準法の改正で採用されたが、それが業種拡大されていく。
現在、本紙でもたびたび報道しているように、違法のサービス残業(時間外手当の不払い=ただ働き)や長時間労働が日常化し、1日8時間労働制の原則は崩れ、労働時間の概念さえなくなってしまい、過労死が増加している時代である。
昨年暮れに発表された中労委の労政審報告により、労働法制の本格的改悪が準備されている。これらが通ると、「企業が労働者を直接雇用するのが原則」という労働法制の基本原則に深くかかわり、戦後60年近く守られてきたこの原則がなくなることになる。
安倍内閣の最重要課題として教育が取り上げられ、教育基本法の10条「不当な支配に服することなく」が「法律に基づく」と根幹が覆された。
そして、安倍首相は会議で「労働市場改革は内閣の大きな課題」と言明。府省横断の検討の場をつくって、この夏の「骨太の方針」に方向性や工程表を盛り込む方針と言われている。
さらに諮問会議の民間議員は、「市場化テスト」をハローワークの職業紹介事業にも導入し、労働・雇用そのもので儲けようと考えている。
労働法制の改悪は、働かなければ生きていくことができない労働力という特殊な商品の、売り手である労働者にとって、ある意味で、労働強化による健康破壊や過労死といった死に直結する問題である。
これに対して、連合などは「労働者の代表がいない場で議論されており、企業側に都合のいい中身になる」と警戒を強め、不退転の決意を見せている。今こそナショナルセンターの枠を越えた労働側総がかりの闘いが必要だ。
『週刊新社会』(2007/1/1)

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます