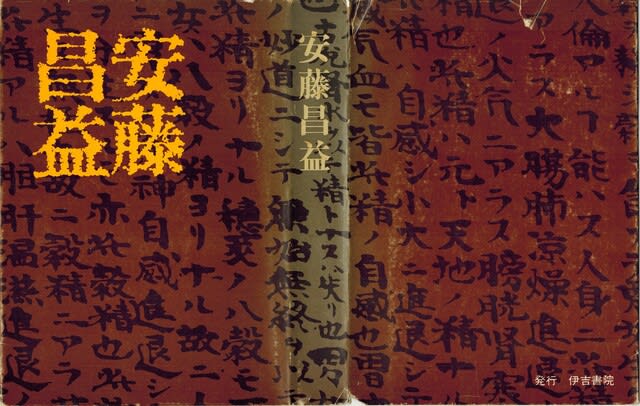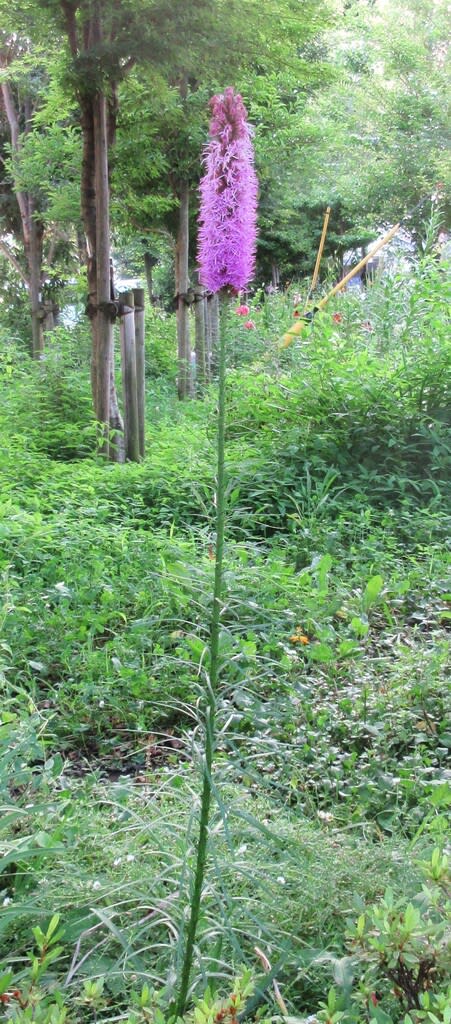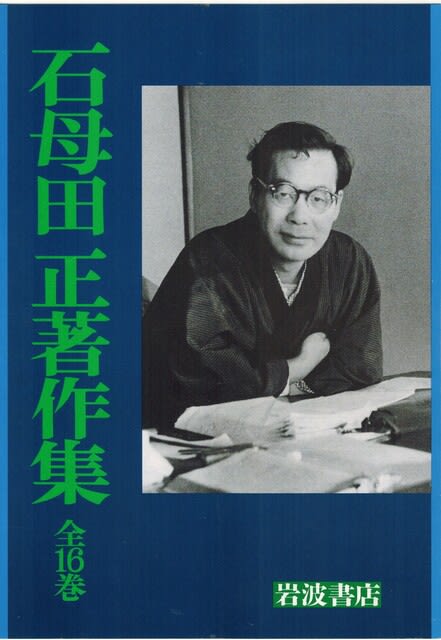【コレクション 18】
(1)日本で見る世界地図は、中央に日本があり、西に朝鮮半島や中国・ロシア、東に太平洋・アメリカというのが普通です。
しかし、社会の発展、とくに資本主義の発展を歴史的に見ると、ヨーロッパが中心となります。まずイギリスやフランスで経済が発展し、それに続いて西はアメリカ、そして東はドイツ・ロシアそして日本の順となります。つまり、日本は経済の近代化という観点からいうと世界の端にある国ということになります。
(2)これを、経済理論の発展の観点からいうと、まず、中世以来の商品経済が発展してきて、1800年前後の産業革命をへて機械制大工場化した資本主義経済が確立します。この間、アダム・スミスやデイヴィッド・リカードウらの経済理論の形成が見られますが、資本主義が自立すると、こんどは失業や貧困など、資本主義経済の問題点が表面化してきます。
産業革命がおよそ1830年ころに終わりますが、1840年代には早くも経済恐慌や革命運動が梶まってきて、マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』が1848年に出されます。これは、1868年の明治維新より20年も前のことです。
(3)一方、日本と同じく当時の後進国だったドイツは、先進国英仏に追い付くために国家財政を使って政策的に大企業体(独占体)をつくって対抗しようとします。その財政理論として発展したのがドイツ財政学(講壇社会主義)です。
そして、ドイツは、資本主義が遅れているという点での問題と、急激に大規模資本主義化したことによる問題が起こって、一気に革命への方向が生まれてきます。そのために、社会主義鎮圧法などの悪法が導入されていきます。
(4)これよりさらに遅れて近代化が始まった日本には、イギリスが資本主義に向かって発展する時代の、自由競争の伸び伸びとしたアダム・スミスの理論と、資本主義が問題点を生み出してきてかげりを見せ始めたころのデイヴィッド・リカードウ理論と、さらに国民を弾圧しながら大企業体をつくって対抗して行こうとするドイツの理論とが、混然として一気に流れ込んできます。
これは、欧米に出かけた人が、どこの誰のところへ行ったかによって影響のされ方に濃淡があったといってよいわけですが、日本の場合は、伝統的な在来の思想の上に、欧米からの思想や理論が重なって近代思想が形成されていったわけです。
(5)長くなりましたが、きょうは『明治大正言論資料』です。

このパンフレットはB5判大、表紙とも12ページです。
この表紙には、左右両側に署名(サイン)があります。これを読むのも楽しいですか、できるだけ大きくしておきました。ぜひどうぞ。
内容は次のようになっています。
1ページ.表表紙(上記)
2ページ.上4分の3に「刊行にあたって」、下4分の1に「全体の構成」
3~9ページ.「全体の構成」にしたがって、次の解説
Ⅰ 近代新聞の誕生
Ⅱ 大記者の時代
Ⅲ コラムの時代
Ⅳ 戦争報道
Ⅴー1 内乱と相乗
Ⅴー2 大陸時代
Ⅴーー3 差別問題
Ⅵ 外事新聞
10~11ページ 組方見本(
12ページ 「本資料集の特色」
刊行予定:84年1月末日
第1回配本 中江兆民集 東雲新聞 明治21―23年 後藤孝夫編 9800円
以上です。なお、各解説は8ポくらいの小さい活字で細かく書かれています。そのためもあり、ここでは割愛し、次の項に「刊行の意義」をとりあげておくことにします。
(6)この資料集は、当時すでに入手可能となっていた『幕末明治新聞全集』、『明治文化全集』、『福沢諭吉全集』、『陸羯南全集』を除いて、「入手不能または閲覧不自由な資料を総合的に提供」することを目的としていること、そしてこの刊行の意義を次のようにいいます。
「1868年にはじまる日本の近代化の百年の歩みは、最近とみに注目されている、この革命のもたらした重要な一側面は、自由な論議の誕生であり、そのメディアとしての新聞の誕生である。新聞は1925年(大正14年)ラジオ放送の開始されるまで、言論と情報の唯一メディアであり、内容的には日本人の public mind の最良の表現が示されている。
内政または国際関係の重要な局面あるいは危機状況において、このメディアは何を、いかにして伝達したか、また何を伝達しなかったか、それらを歴史の資料として、ここにはじめて系統的・全体的に編集し公刊しようとするものである。」

昭島市郷土資料館
(7)私は、ここを読んで2つのことを思いました。
一つは、ラジオ放送が開始されるのが1925年であることです。
政府は、1900年に治安警察法を制定し、これを強化して治安維持法を制定します。これによって、政府に批判的な意見を押しつぶしていきました。とくに、天皇制と私有財産問題で最もマークされた日本共産党が解党的打撃を受けます。
これは、上に書いたドイツの社会主義鎮圧法ともつながるものですガ、ドイツではその対策が遅れたために、アメ〔福祉などの社会政策〕とムチ〔労働運動や社会主義者弾圧〕のうちのアメが比較的に強化されます。ところが、日本はこのドイツの経験に「学び」いち早く治安維持法などによって弾圧してしまいますから、その後、日本で社会政策が遅れる原因になります。
福祉や医療などは膨大な経費を必要とします。哀れみでは十分な政策はとれませんし、いまの年金と同じで、財政が苦しくなると、真っ先に切り捨てられます。これを整備し充実させるには、強い政治勢力・圧力がないと政府はやりたがりません。国民がそれを理解するようにならないと、本当に安心できる政策はとらせることができるようになならないものです。
いまでもそうですが、パーティー券を買ってくれるとか、政治献金をくれる方の意見に傾くのはそういう理由からです。軍事に傾くのも、国際情勢とかいろいろありますが、結局がそういうことです。
もう一つは、『御料局測量課長 神足勝記日記』(J-FIC)でも出てきますが、神足が、いち早くラ時をを購入していたことです。そうして、当時のおもだった人たちの講演・講義などを聴いて、定年後の「耳学問」がをやっていました。
神足の晩年を考える場合に、このラジオの問題と新聞などの問題は切り離せません。どこまで手が回るかわかりませんが、注目しているところの一つです。
長くなりました。では、きょうはここで。

西の空