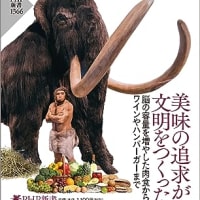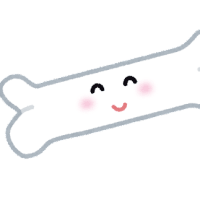江戸時代の酒-近世日本の食の革命(15)
文化人類学的には、江戸時代は飲酒が「ハレ」から「ケ」に変わる時代と見ることができます。
「ハレ」とは祭りなどの非日常の行いであり、「ケ」とは日常生活のことを指します。つまり、それまでは祭りなどのハレの場で飲まれていた日本酒が、江戸時代になると日常生活で飲まれるようになったということです。例えば、江戸時代には「居酒屋」が江戸を皮切りに全国に普及するようになり、庶民も気軽に酒を楽しむことができるようになりました。
このような背景には、江戸時代になって日本酒の生産量が大幅に増えたことがあります。日常的に飲んでも大丈夫なほどに日本酒の生産が増えたというわけです。
今回は「日本酒」を中心に、江戸時代の酒について見て行きます。

***************
古代の酒は神様にお供えした後に集まった者たちで飲むものであり、神事に欠かせないものだった。各神社に関連した寺ではお神酒(おみき)が醸造されたことから、関西、特に奈良の寺が日本酒醸造の中心だった。
室町時代には、麹米と仕込み米(蒸米)に精白した米を用いる「諸伯(もろはく)」や、麹米と仕込み米を何度かに分けて加えて行く「段仕込み」、加熱殺菌を行う「火入れ」などの技術が開発され、良質の日本酒が醸造されるようになった。そして、このような新規技術は寺から伊丹などの民間の造り酒屋にも広まって行った。
しかし、織田信長や豊臣秀吉が強大な勢力を有していた寺院を弾圧した結果、寺での酒造りは廃れてしまい、民間の造り酒屋が酒造りを担うようになる。
江戸時代になると、江戸への輸送の便が良い大阪府や兵庫県の沿岸部での酒造りが盛んになって行った。特に灘は良水にも恵まれたことから、日本酒の一大生産地に成長した。このように関西で醸造された日本酒は「下り酒」として、「樽廻船(たるかいせん)」に乗せられて江戸に運ばれた。
江戸幕府は生活必需品を上方に頼るのを嫌って、関東での「地廻り酒」の生産を奨励したが、美味しい酒を造ることはできなかった。一方、上方の酒の生産量を抑制するような政策が取られた結果、18世紀末頃から尾張や三河などの東海地方の「中国酒」の生産が増えたが、やはり、上方の酒に匹敵するものにはならなかった。その結果、江戸時代を通して日本酒の7~9割は上方で造られていたと推測されている。
なお、江戸っ子の「初物好き」は有名で、上方の新酒をどれだけ早く江戸に運ぶかと言うレースが冬の風物詩になっていたと言われている。兵庫の西宮を出発した樽廻船は、おおよそ6日間で江戸に到着したらしい。
ところで、日本酒醸造の多くは冬場に行われるが、これが始まったのは江戸時代のことだ。
江戸時代初期までの日本酒造りは四季を通して行われていた。しかし、冬場の方が酵母の働きを上手にコントロールできることが分かり、冬場に仕込みを行う「寒造り(寒仕込み)」の技術が1667年に伊丹で確立される。さらに、食用のコメを確実に確保したい幕府の思惑から、1673年にはコメの収穫後に行われる寒造りだけが許可されるようになった。こうして、冬場の日本酒造りが定着して行ったのである。北陸などの寒村出身の杜氏が生まれたのも、寒造りのはじまりがきっかけとされている。
さて、江戸に着いた酒は下り酒問屋が荷受けしたのち、大卸や仲卸の手を経てから酒屋に渡され、一般に販売された。問屋や卸、酒屋は儲けを多くするために、それぞれが水を加えたため、店で買うときには2~3倍に薄まっていたと言われている。ただし、大名屋敷などに販売される酒は薄められていなかったため、酔いやすかったらしい。
江戸時代は太平の世であったため、それまでよりもコメの生産量が増えるとともに、水車を利用した精米技術も発展することで、日本酒の生産量も増えて行った。また、江戸は単身の男性が多かったため、日本酒の消費量も多くなりやすかった。
造り酒屋で武士などに酒を飲ませることは鎌倉時代から行われていたが、18世紀半ばの江戸では、酒の小売店の店先で一般客に酒を飲ませるところが現れるようになった。特に、江戸場近くの神田にあった豊島屋は人気を博した酒の小売店で、酒と一緒に豆腐田楽を出しところ大好評となる。これをきっかけに酒を飲ませるのを専業とする「居酒屋(煮売居酒屋)」が増えて行った。こうして19世紀の初めの江戸には1000件以上の居酒屋が営業していたと言われている。そして、この居酒屋が地方や全国各地に広がって行った。
このようにして、江戸時代には特別なハレの日に飲んでいた酒は日常のケの日に飲まれるようになって行った。それでも、自宅で一人で飲むようなことはまだ行われず、店などの人が集まるところで飲むのが普通だった。飲酒が完全に日常化するのはもう少し先の話になる。
なお、19世紀初め頃の下り酒は1合20文くらいで飲めたらしい。今の価格で200円から600円だから、現代とそれほど変わらない。また、下り酒よりも安い地廻り酒や中国酒も販売されていたし、麹米に玄米を使った「片白(かたはく)」やすべて玄米で造った「並酒(なみざけ)」はもっと安かった。また、さらに安い濁酒(どぶろく、だくしゅ)もあり、貧しい者でも酒を飲むことができた。
最後に、蒸留酒である「焼酎」について見て行こう。
イスラムを発祥とする蒸留技術は14世紀の終わりから15世紀の初めにかけてタイから琉球に伝わったとされる。琉球ではこの技術を用いて「泡盛」が醸造されるようになった。
16世紀になると、蒸留技術は九州に伝わり、さらに日本各地に広まって行った。九州南部のように暖かくて日本酒造りに適さない土地では、コメやムギ、ソバ、サツマイモをコウジカビと酵母で発酵させた醪(もろみ)を蒸留することで、「焼酎」が造られるようになった。
一方、日本酒が醸造できるところでは、主に低品質の日本酒の醪から米焼酎が作られるとともに、日本酒をしぼったあとの酒粕を蒸留することで「粕取り(かすとり)焼酎」が造られるようになった。また、このような焼酎は日本酒に加えられて、「柱焼酎」と呼ばれる酒が造られた。これは保存性を高めるためだったと考えられている。江戸でも、濁酒を造っていた業者は、酒が腐りやすい夏には焼酎を造っていたと言われている。