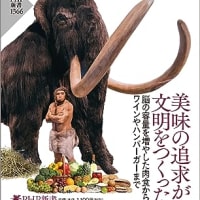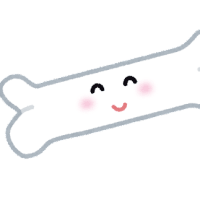コンブと鰹節-近世日本の食の革命(16)
「コンブだし」と「カツオだし」は日本料理の代表的な出汁(だし)で、それぞれコンブと鰹節を煮出してとります。
コンブにはグルタミン酸ナトリウムといううま味成分が含まれており、鰹節にはイノシン酸という別のうま味成分が含まれていて、これらのうまみ成分によって料理がより美味しくなるというわけです。
西洋や中国では、動物の肉からとったエキスが料理のベースになります。このエキスには脂肪分が含まれているため、料理には濃厚な風味が加わります。一方、昔の日本人は動物の肉を食べなかったため、料理の味が素材そのままの単調なものになってしまいがちです。それを補うために発達してきたのが出汁と考えられています。
出汁が一般的に広く使われるようになるのは江戸時代からと言われています。今回は、江戸時代のコンブと鰹節、そしてそれらを使ってとった出汁について見て行きます。

鰹節(荒節)(ウイキペディアより:ライセンス)
***************
中世までのコンブについては、「コンブを運ぶ-中世日本の食(11)」で詳しくお話しした。
江戸時代になって西廻り航路が確立すると、蝦夷のコンブは日本海→関門海峡→瀬戸内海というルートで大阪に運ばれるようになった。こうして大阪や京都でコンブの流通量が増えると、コンブから出汁がとられるようになる。
コンブだしは味や香りが控えめで、素材の味や香りを生かした料理に適している。京都や大阪ではたくさんの種類の野菜が手に入ったことから、これらの味を楽しむためにコンブだしが広く使用されるようになった。
また、コンブから塩コンブやとろろコンブが作られたりもした。塩コンブは小さく切ったコンブを醤油と塩で煮詰めたもので、塩が吹き出ることからこう呼ばれる。江戸時代になるとコンブと醤油の流通量が増えたため、盛んに作られるようになった。
一方、大阪に集まったコンブのかなりの量が琉球に運ばれ、さらに琉球から中国へ貢物として輸出された。貢物に適さない低品質のコンブは琉球で消費されたため、琉球料理ではコンブを使ったものが多くなった。現在でも沖縄県ではコンブの消費量が多い。
コンブは大阪から江戸にも運ばれたが、品質が高いものは上方で消費されていたため、江戸に流通したものは低品質のものだった。また、上方の水が軟水だったのに対して、江戸の水は硬度が高い(ミネラル分が多い)ため、コンブだしには適していなかった。この2つの理由のため、江戸ではコンブだしは広まらなかったと言われている。
次は鰹節だ。
鰹節の材料のカツオは熱帯から温帯にかけての比較的暖かい海域によく見られる魚で、日本近海では主に太平洋沿岸に生息している。日本では縄文時代からカツオを食べてきたと考えられており、奈良時代には朝廷への貢物になっていた。
鎌倉時代以降になると、武士がカツオを「勝つ魚」と言い換えて、縁起の良い魚と考えるようになり、出陣の際によく食べられるようになった。このようにカツオを縁起物として食べる風習は江戸時代には庶民にも広がって行った。
春になって海水温が上昇し始めると、カツオは黒潮に乗って北上を始める。この時に獲れたカツオは「初ガツオ」と呼ばれて古くから珍重されてきた。初物好きの江戸っ子は狂ったように初ガツオを求めたそうで、「初ガツオは女房を質に入れてでも食え」と言われるほどだった。ただし、カツオ1本が1~3両(10万円~40万円)ほどしたため、一般庶民には手が届かなかったと思われる。
冷蔵・冷凍技術がほとんどなかった時代には、カツオは干物にされることが多かった。奈良時代になると、腐りにくくするために、煮てから干すようになった。
カツオは干すととても固くなることから『古事記』には「堅魚(カタウオ)」と記載され、このカタウオが変化してカツオになったと考えられている。そして、魚と堅の字を組み合わせて「鰹」という漢字が作り出された。
干して堅くなったカツオは小さく割ってから煮て食べられていたが、室町時代には現在の削り節のように、削ったものが食べられるようになったと言われている。また、煮汁は調味料としても利用された。
現在の鰹節は、煮たカツオを煙でいぶすことで乾燥させるとともに、香りづけを行っている。この方法は17世紀の半ばに紀州の漁師が考案したと言われている。こうして出来上がったものは「荒節(あらぶし)」と呼ばれ、現在削り節(花かつお)として出回っているもののほとんどは、荒節を削ったものだ。
荒節にはまだ水分が残っているため、長期保存すると悪いカビが生えてダメになってしまうことがある。これを防ぐために、良いカビを積極的に生やす方法が17世紀の終わり頃に土佐で開発された。
繁殖したカビは長期間をかけて鰹節から水分を除去し、さらに脂肪分を分解することで雑味を除く働きをする。こうして「枯節(かれぶし)」と呼ばれるカチコチの鰹節が出来上がる。私たちが目にする黄土色の鰹節がこの枯節だ。
枯節の製造方法は18世紀から19世紀にかけて、土佐から紀州や薩摩、伊豆、安房などに広まって行った。現在の鰹節の主な生産地は鹿児島県と静岡県で、この2県で全国の99%の生産量を占めている。
なお、荒節でとった出汁はうま味が濃いが少し粗野な感じがするのに対して、枯節でとった出汁は上品な味わいを特徴とする。と言っても、コンブだしよりもはるかに風味が強く、魚介類によく合うことから、関東地方で急速に広まって行った。
また、鰹節は「勝つ魚武士」と読めることから、江戸時代には縁起物の贈答品として武士だけでなく、裕福な商人たちの間でも人気を博した。
なお、コンブだしとカツオだしを混ぜ合わせた「合わせだし」も江戸時代中頃に利用されるようになった。合わせ出しにはグルタミン酸ナトリウムとイノシン酸が含まれており、これらの「相乗効果」によって、深いうま味が生み出されるのである。
*今回で「近世」の章が終了します。次回から「近代」が始まります。