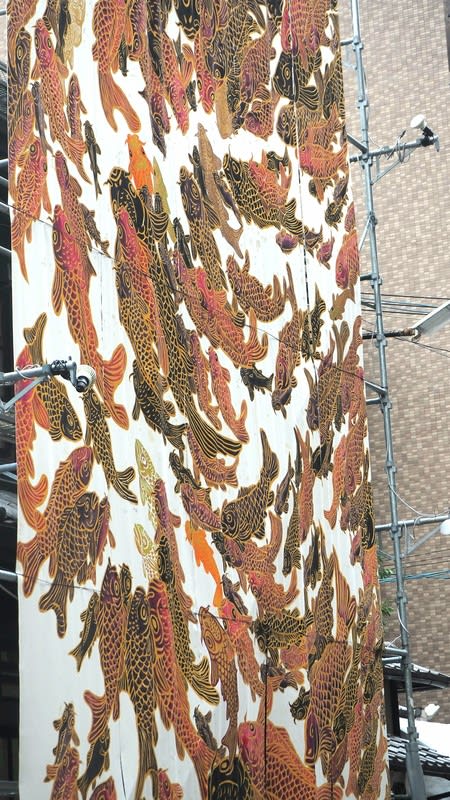夏の花がつぎつぎ開花しています。
レンゲショウマ
日本固有の1属1種の植物で、東北地方南部から近畿地方にかけて分布します。
深山のやや湿った林床に多く見られ、やや薄暗い林に大群落をつくっていることもあります。
シャンデリアのように咲く姿は、夏の花の風物詩としてマスコミなどでも毎年取り上げられています。
国内はもとより海外でもとても高い人気を博しています。



スズカケソウ
非常にめずらしい山野草で、絶滅が危惧される花です。
青色の花で、花のつき方が「鈴懸け(山伏が衣装の上に羽織る衣)」に似ているので名付けられた。



シマジタムラソウ(島路田村草)
シソ科アキギリ属の多年草。東海地方の固有種で環境省の絶滅危惧II類(VU)に分類されています。
7〜9月頃、茎の先端付近にアキノタムラソウに似た淡青紫色の花を穂状につけます。


ハマボウ
関東以西の本州・四国・九州に分布し、韓国にも分布する落葉低木の花です。
7月から8月にかけ黄色の美しい花を咲かせる。中心部は暗赤色です。


カリガネソウ



キンミズヒキ

ヤマシャク

ヤマコンニャク

ヤブカンゾウ

オトギリソウ

桔梗


ヒオウギ