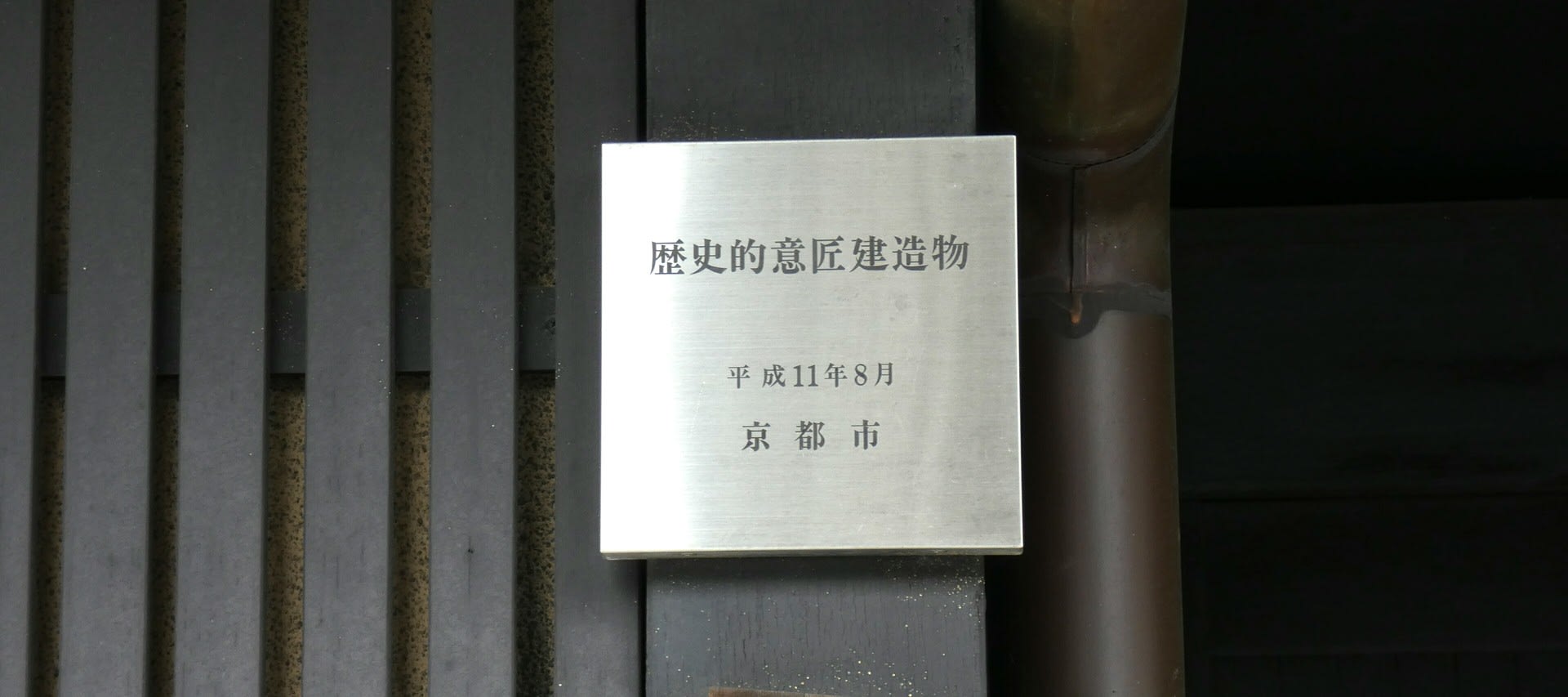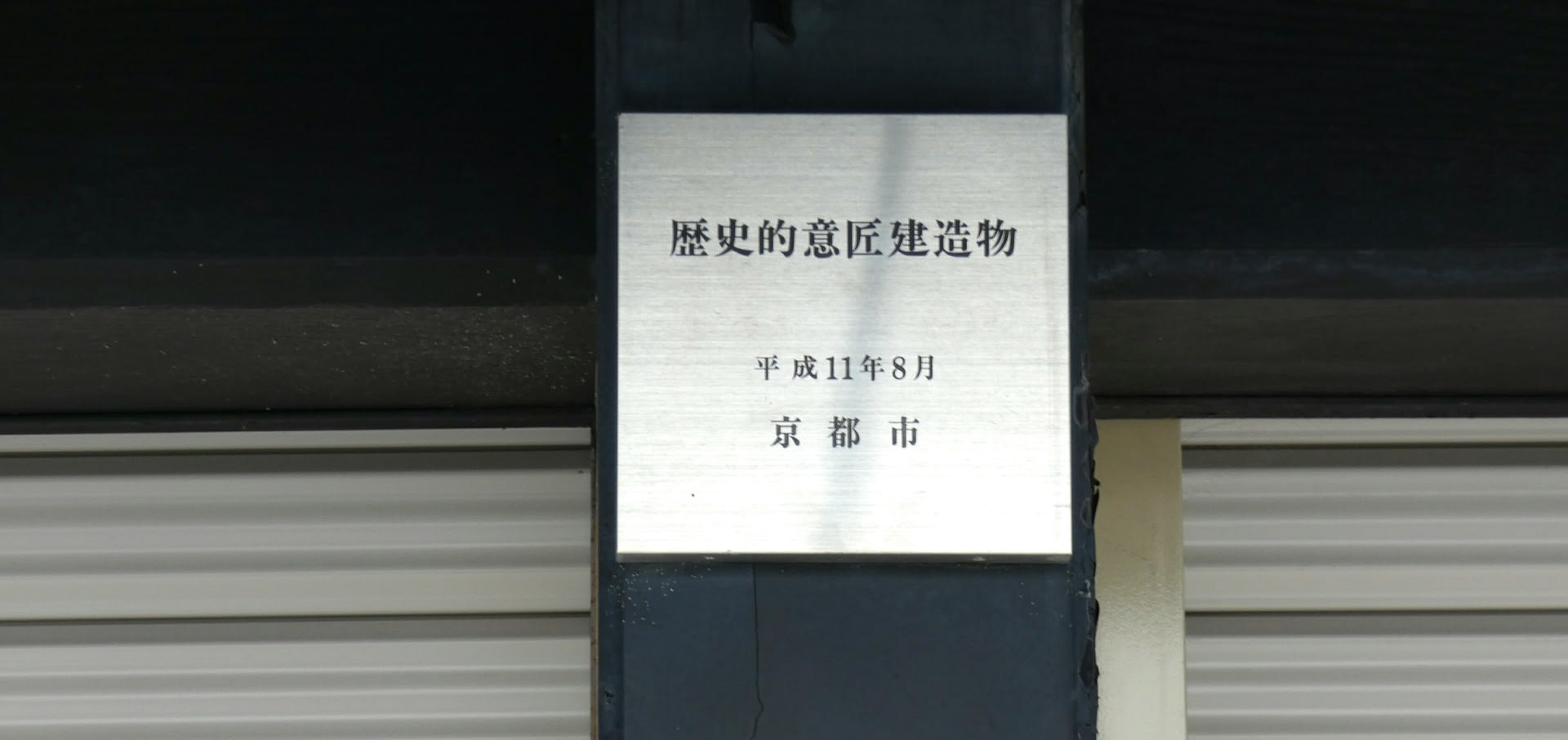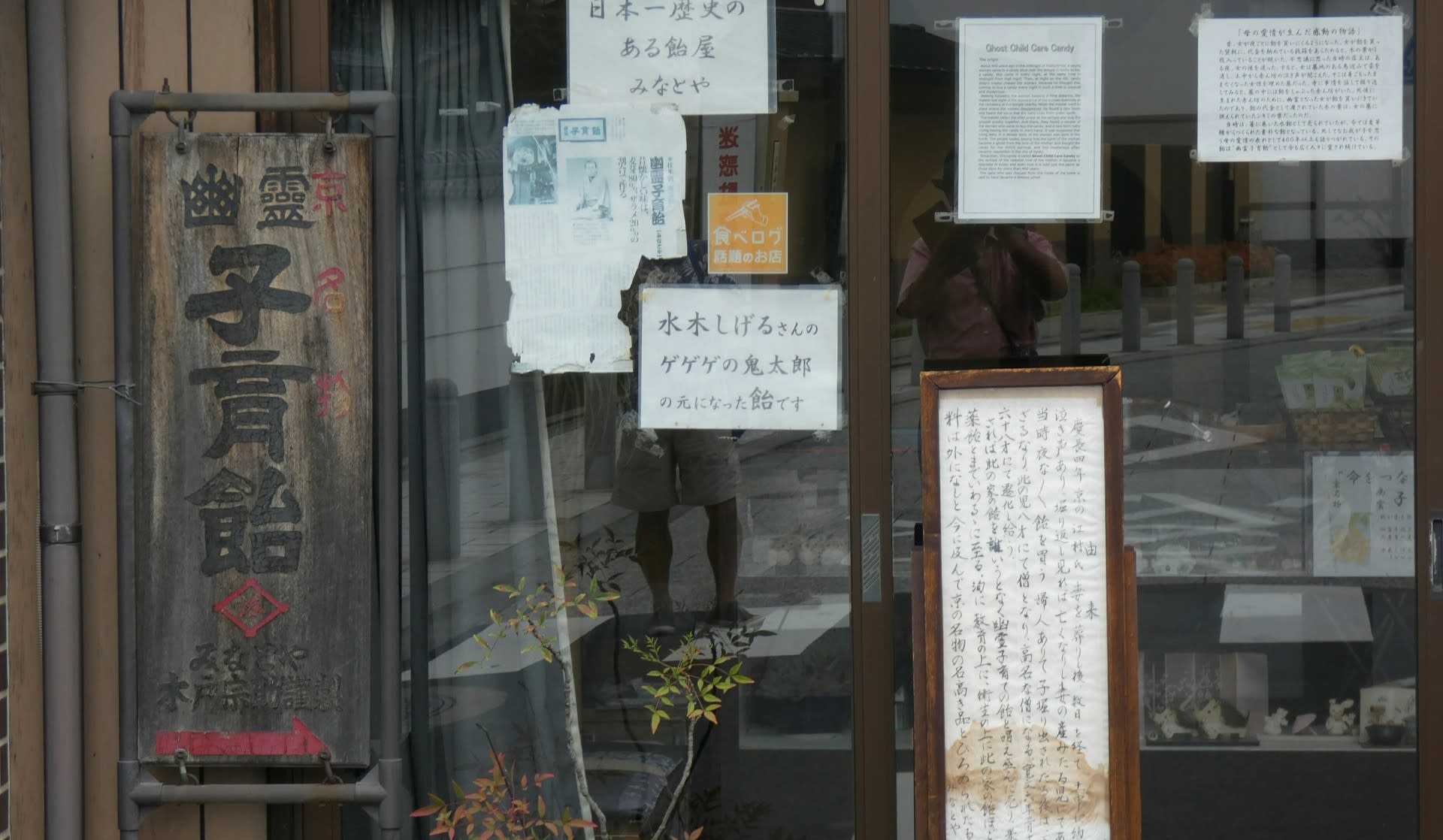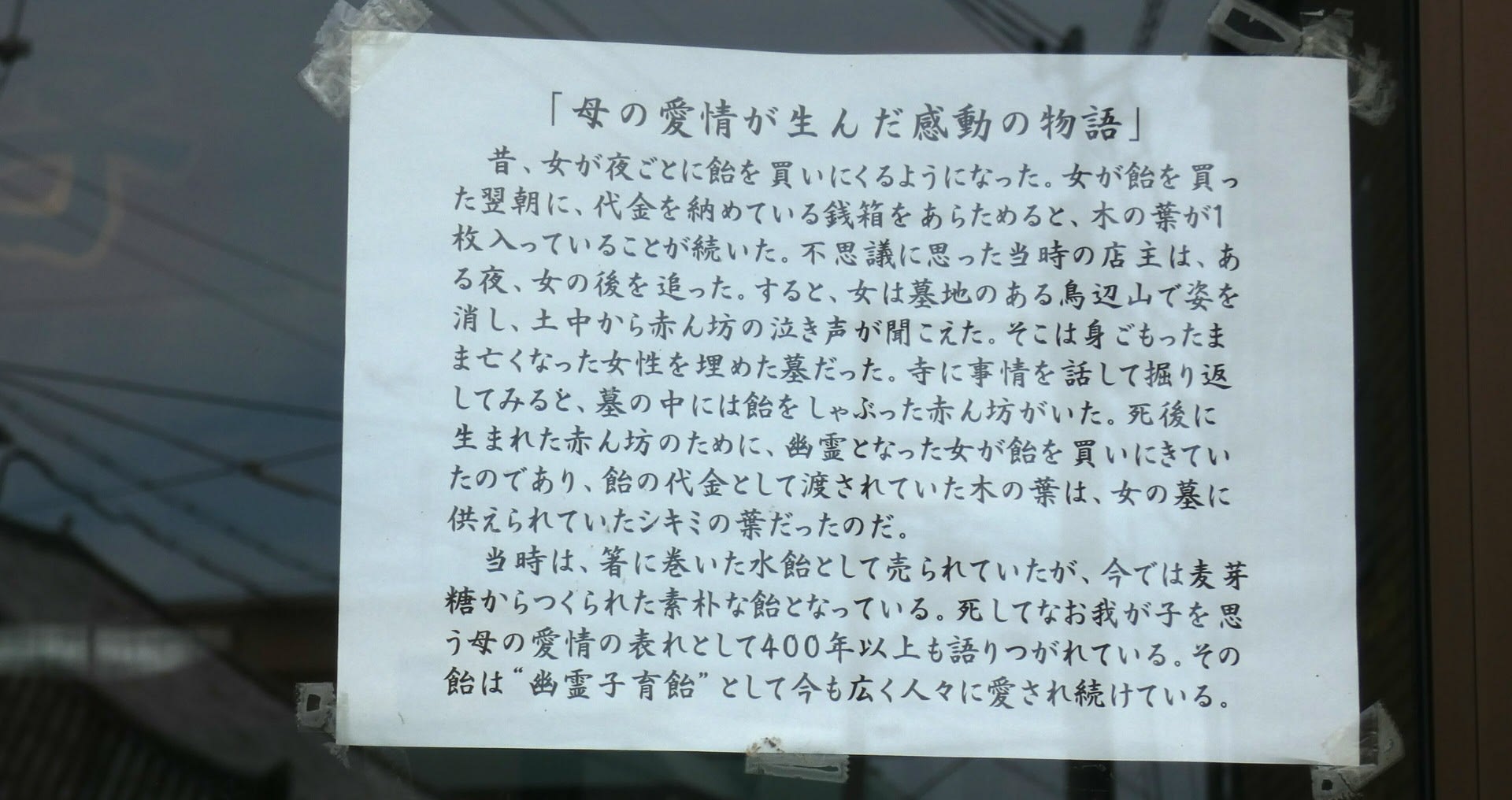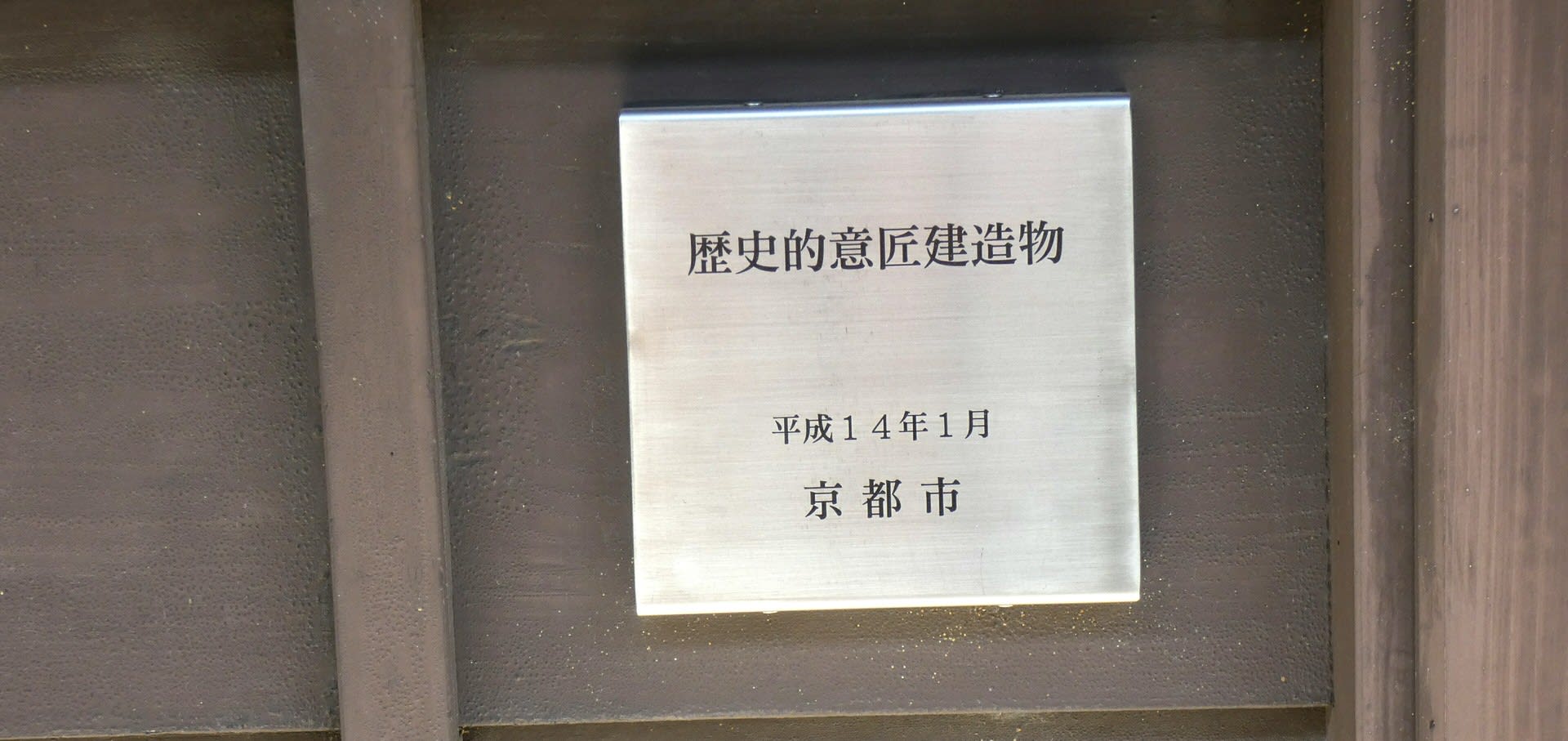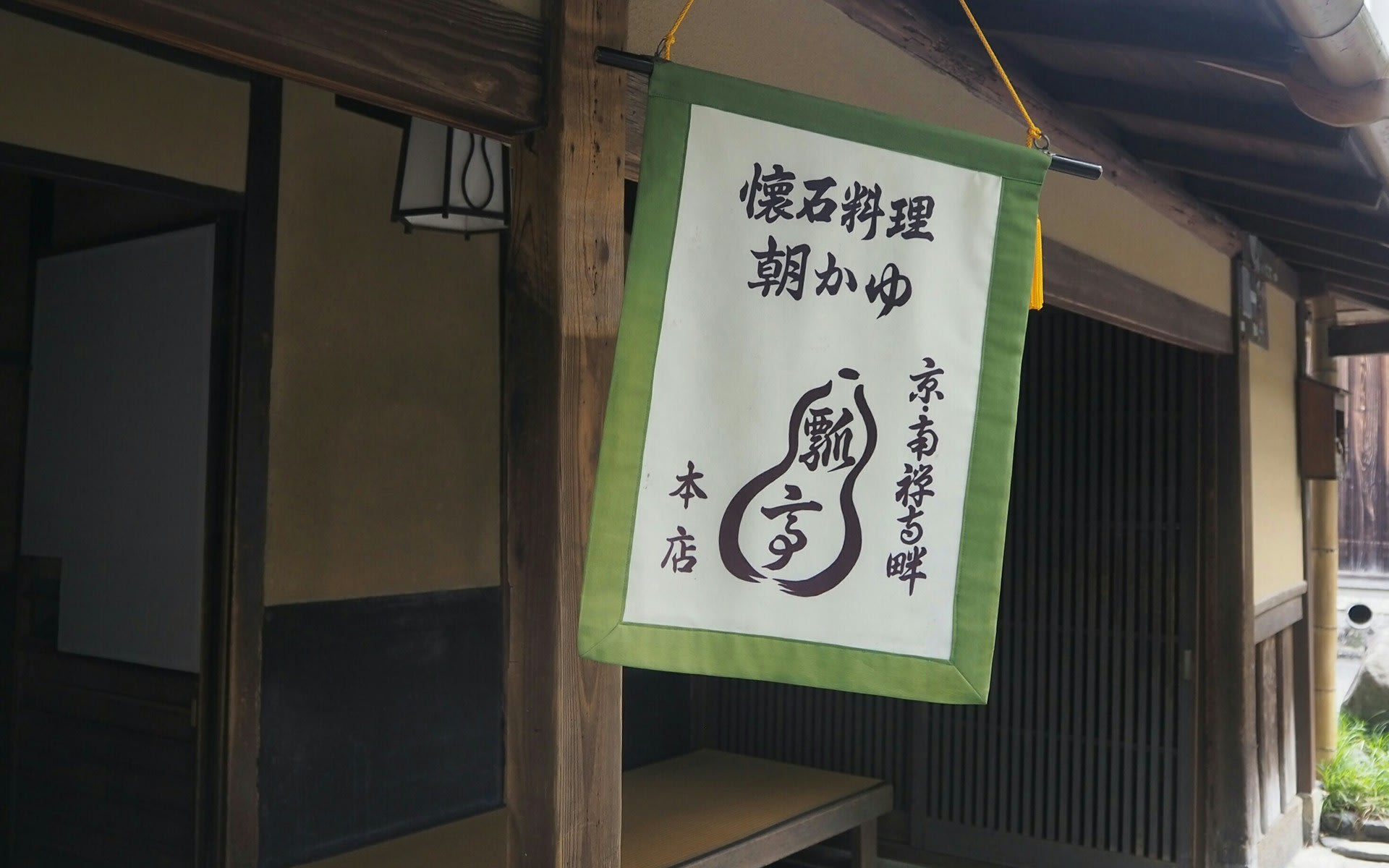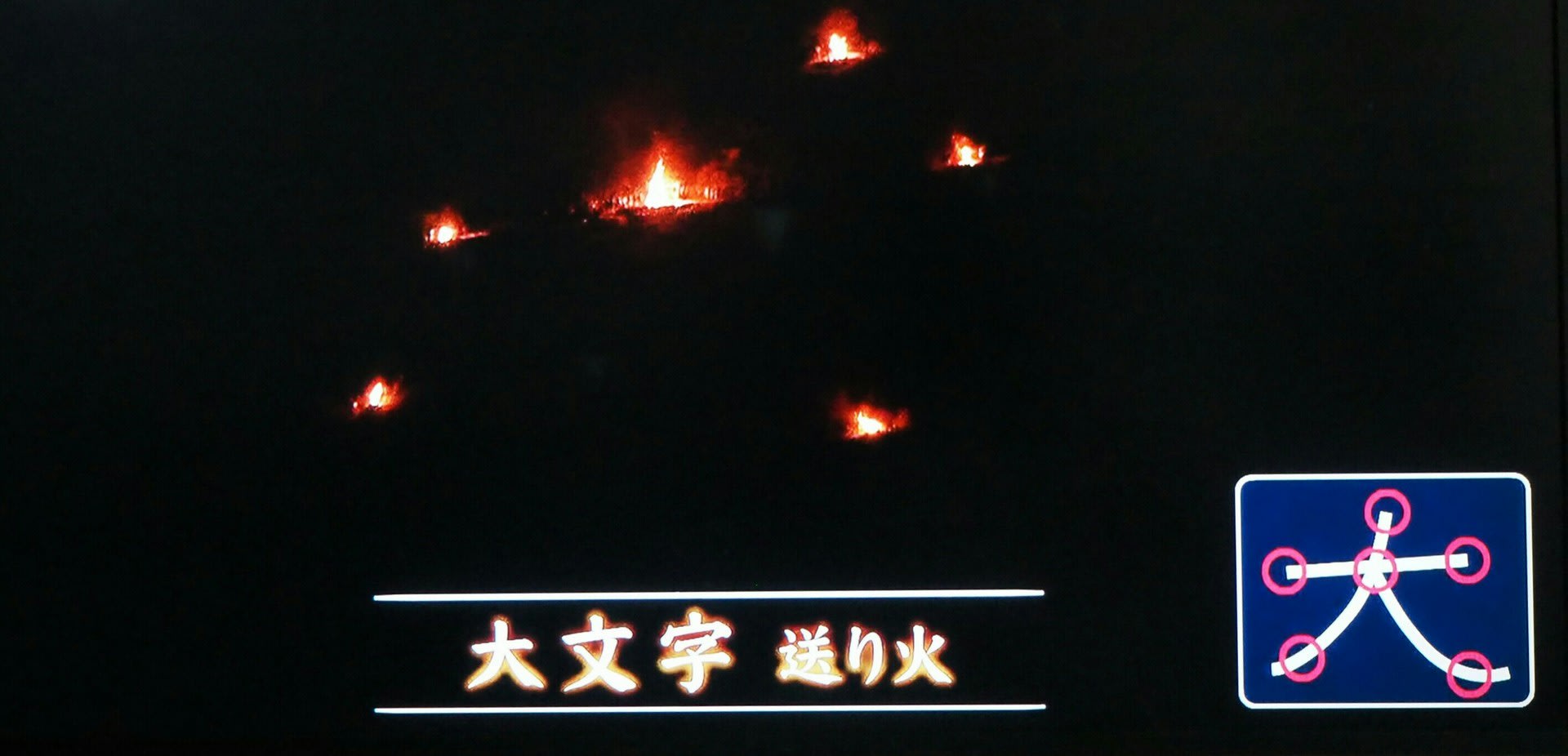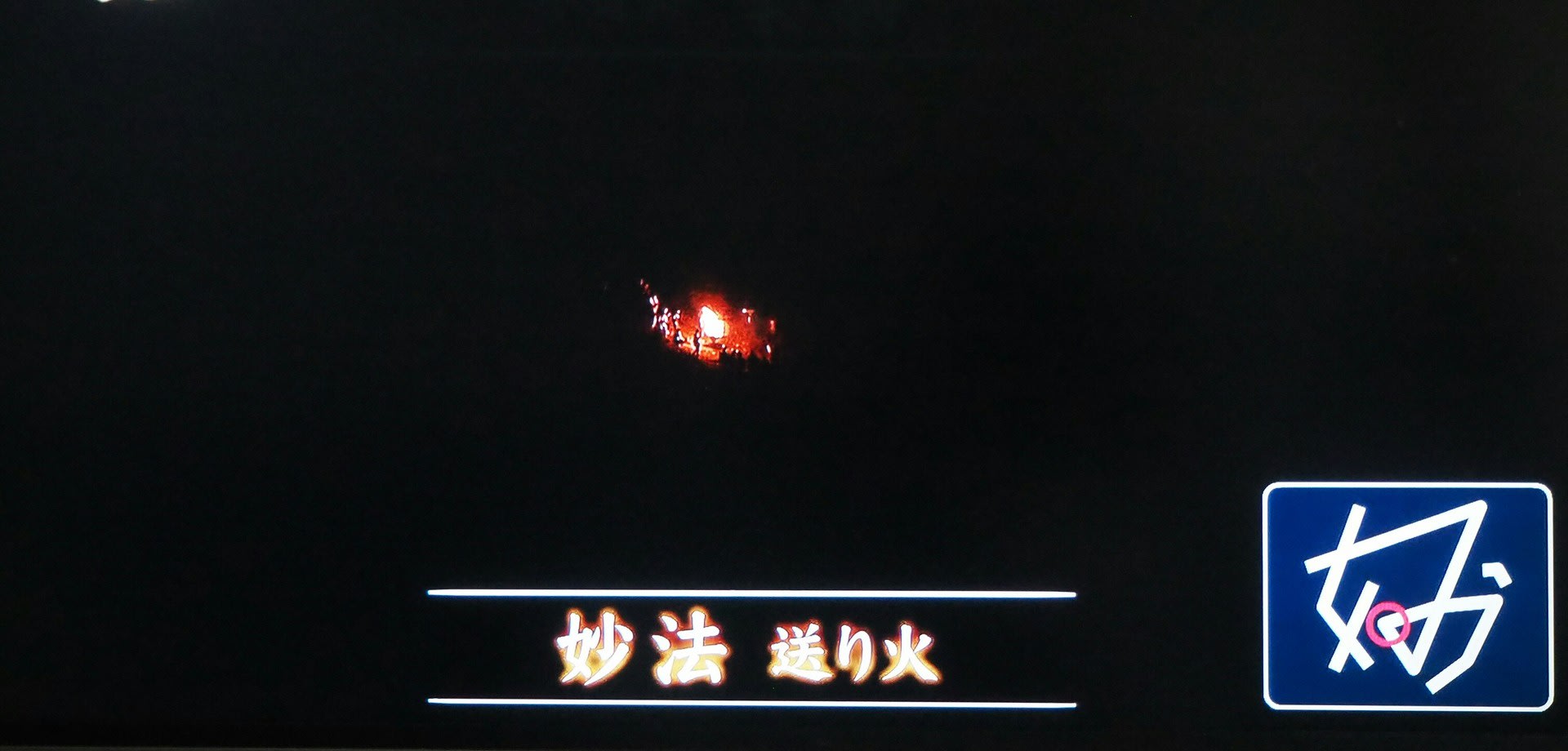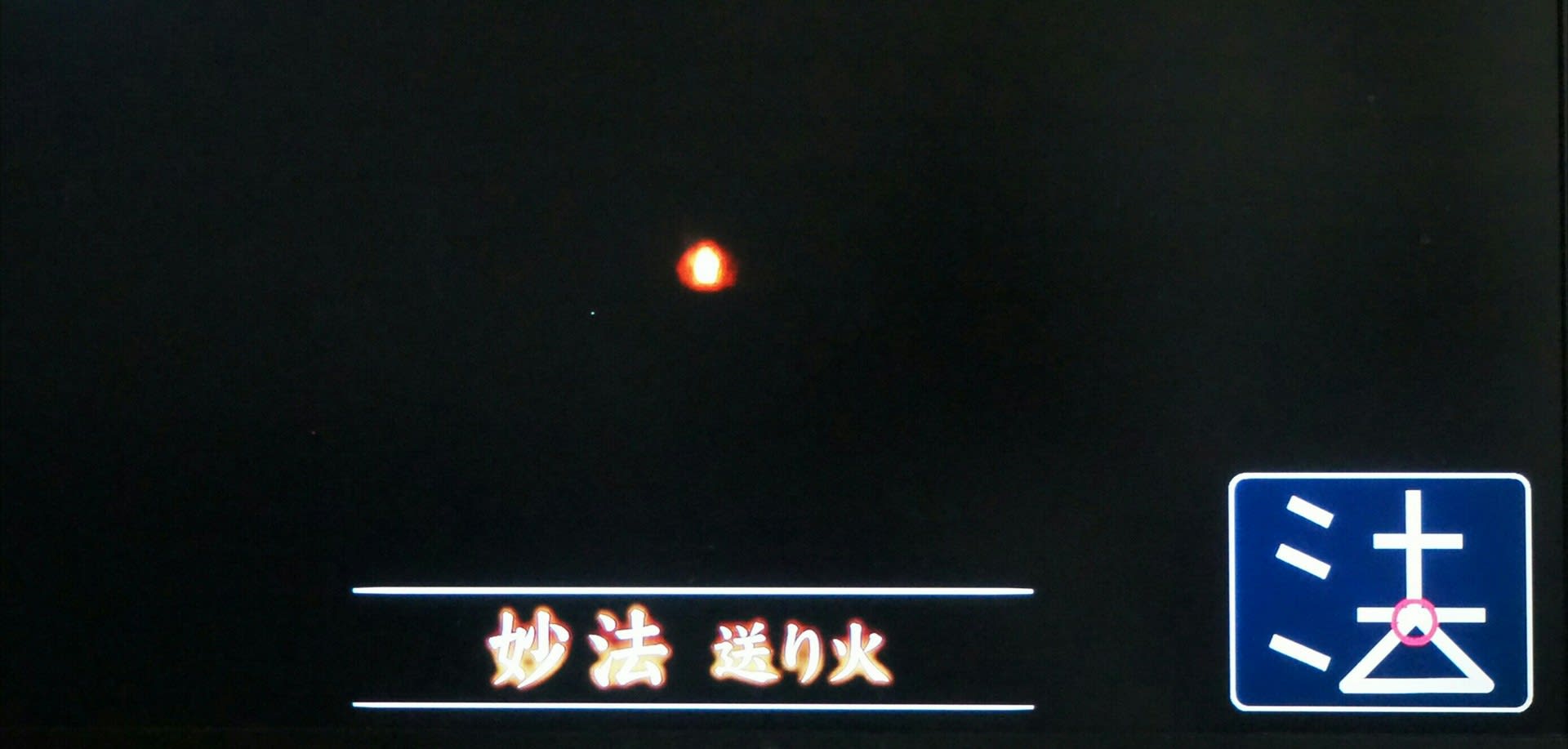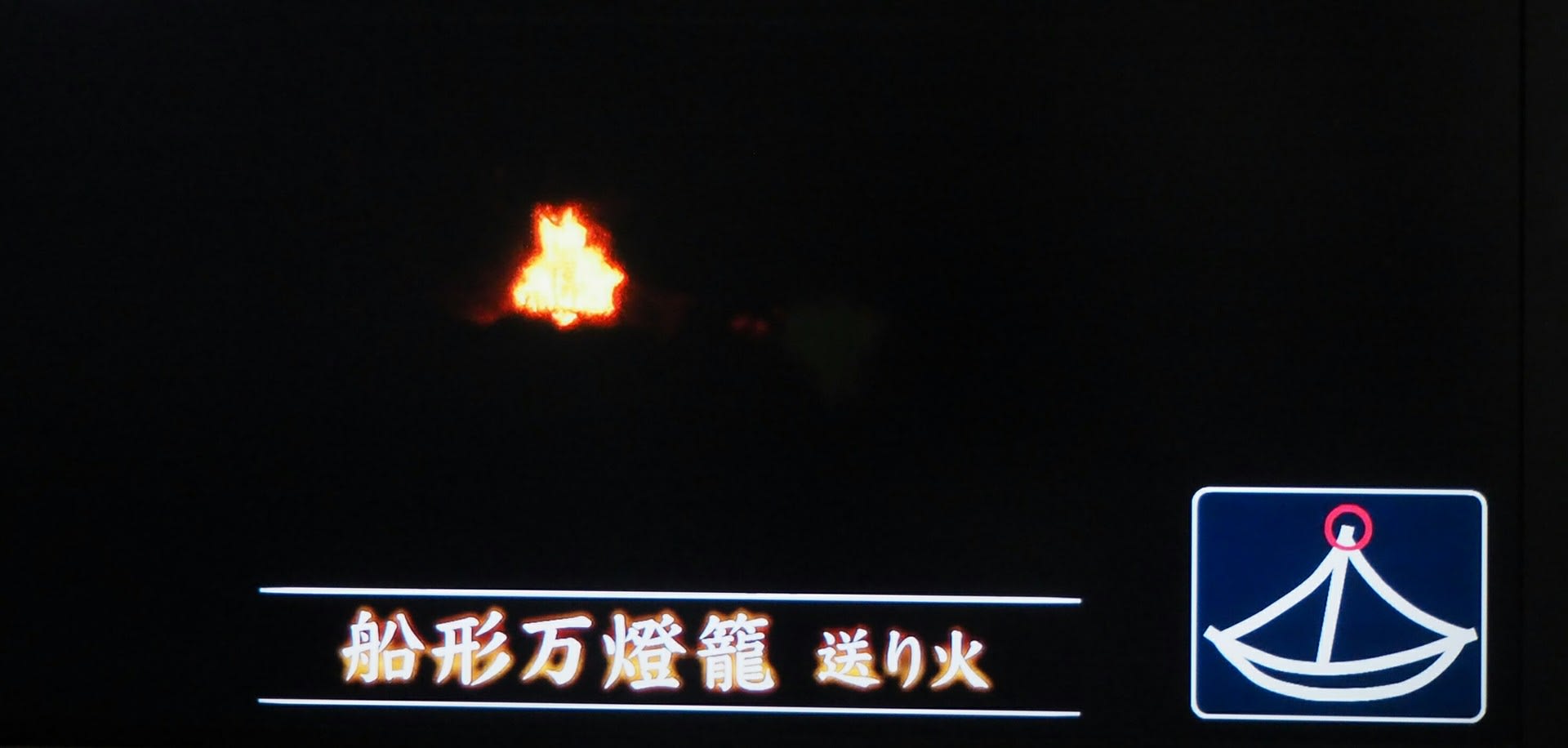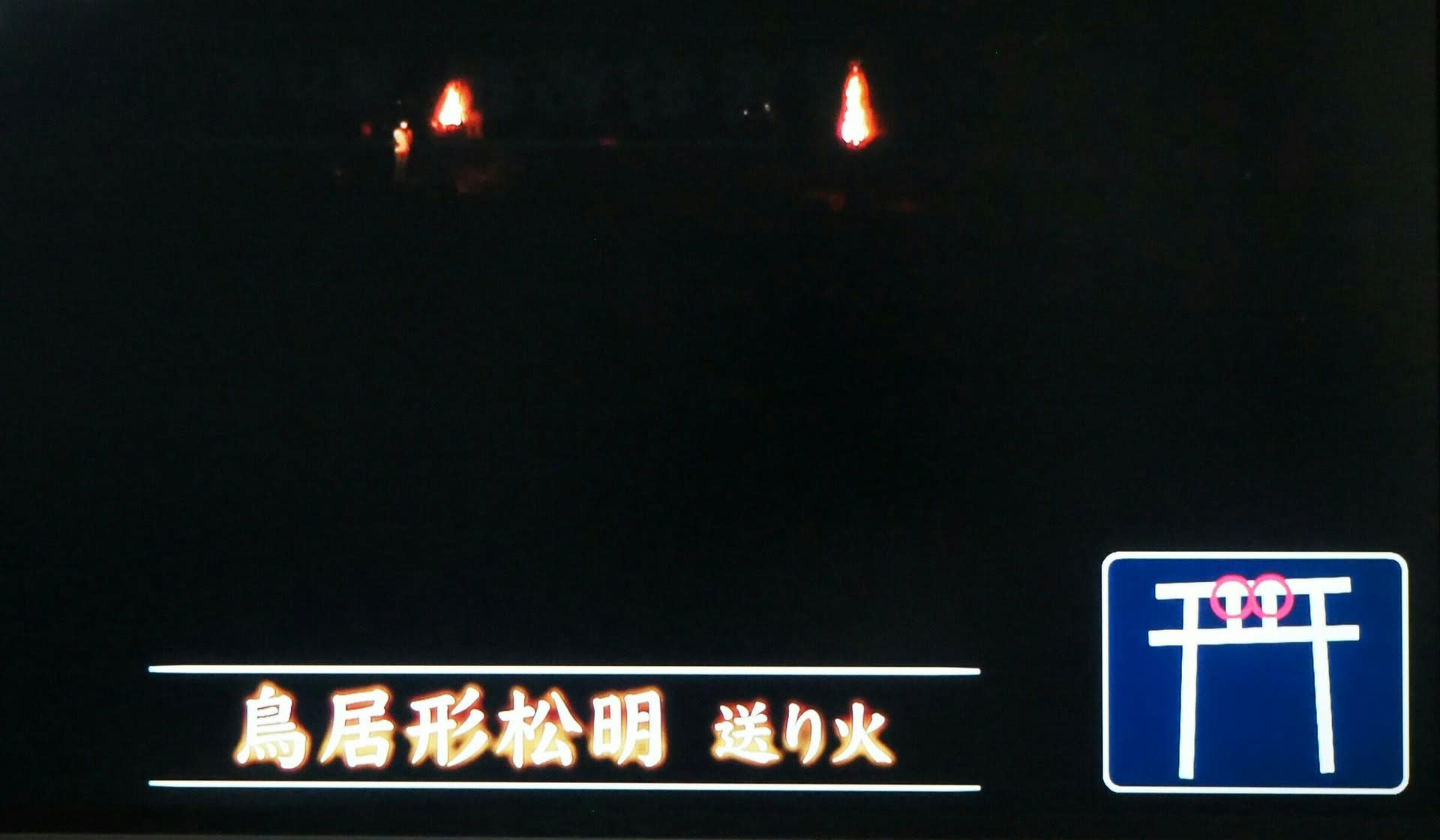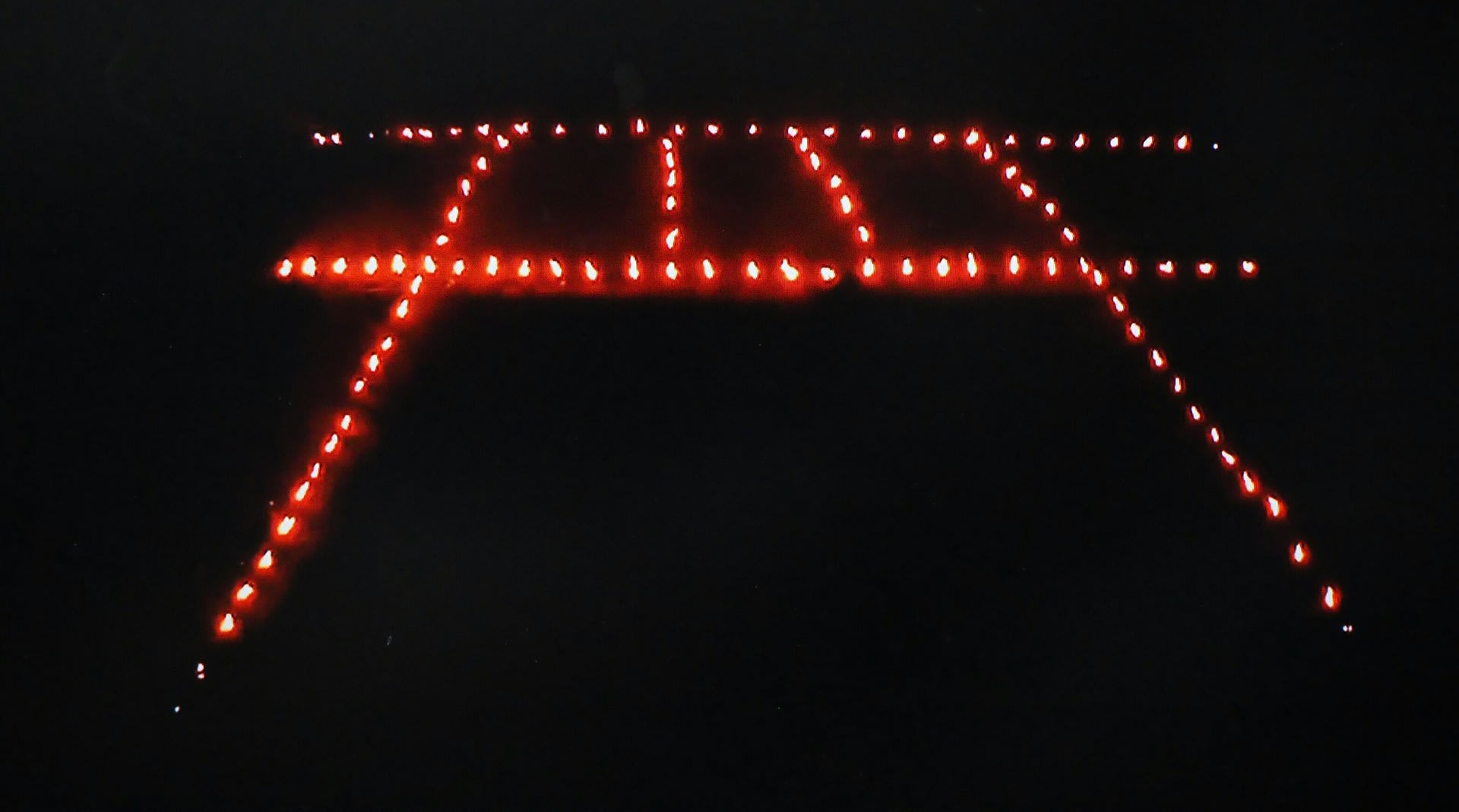昨日まで38度超えの猛暑でしたが、本日は36.8度と下がりました。
また先ほどから雷雨があり、久しぶりの雨という感があります。
明日から処暑です。それに合わせたかのように、天気予報では少しずつ気温が下がり、猛暑日は少なくなりそうです。
今日も新型コロナウィルスについて考えていました。
日本感染症学会に続き、政府の新型コロナ対策の分科会が21日開催され、全国的には7月下旬がピークだったことを明らかにしました。
一方、お盆の時期の分析データが無いこと、高止まりしているところもあり、引き続き感染防止に注意をする必要があることが指摘されました。
私たちはマスコミ報道に躍らされることがないように、過度に恐れず、しっかりと感染対策を行っていけば良いと思います。
3密を避け、感染機会を減らして、社会経済活動を行っていくという現在の考え方で良いのだと思います。
7月以降の再感染拡大で、再度緊張事態宣言を出すべきだと主張する意見がありました。
私は国として宣言を出すことには異論あり、実際に出されずに良かったと思っています。
〇〇〇党の〇〇代表は7月29日のラジオ日本番組で、新型コロナウイルスの感染急増を踏まえた緊急事態宣言の再発令について、「(自らが首相だったら)出さざるを得ない」と述べ、政府の対応に関し「最初の宣言を緩めるのが早すぎた」と批判しました。
私は〇〇代表の通りに緊急宣言を出せば、第一派と同じ二の舞で、感染ピークを過ぎてからの宣言になるだけでなく、社会経済活動のさらなる悪化を招いていたと思います。
国の緊張事態宣言は諸刃の剣です。
アメリカの失業率は2月の3.5%から、3月は4.4%、4月には14.7%、5月上旬で17.2%(2507万3000人)までハネ上がりました。
フランスでは12月末までに90万人の雇用(フルタイム雇用換算)が失われるとしています。
イギリスでは4月に失業者向けの手当を申請した人の数が210万人に上りました。3月末から新型コロナウイルスの流行を受けたロックダウン(都市封鎖)に入り、4月は事業活動などがまひしていた。手当ての申請者数は、3月から約85万6500人増えました。
ドイツの失業率も5月に上昇し、2015年後期以来の高さとなった。手厚いセーフティーネット(安全網)を備えた同国でも、新型コロナウイルスによる危機から労働者を守るのは厳しいことがあらためて示された。5月の失業者数は、前月から23万8000人増加し、失業者数が今年300万人を突破する可能性があると予測されている。5月の失業者数は287万5000人。
日本も緊急事態宣言で失業者が増えています。
5月の完全失業率は2.9%と前月比0.3ポイント悪化、完全失業者数は197万人と同19万人増えた。
総務省によると、4月に600万人近くまで膨らんだ休業者の約7%が5月に職を失った。潜在的な失業リスクを抱えた休業者は423万人となお高水準で、今後も失業者や労働市場から退出する人が増える恐れがある。としています。
また有効求人5月1.20倍、46年ぶり下げ幅で失業200万人迫っています。
5月の就業者数は全体で前年同月に比べて76万人減少。
今回の再感染拡大で、緊急事態宣言を再発令すれば、さらに経済が泊まり、当然失業者数も増え、それに伴う死亡者数も残念ながら増えます。感染症などの専門家との連携を密にしながら、感染流行や医療逼迫の正確が判断が求められるのだと思います。
一部で命が大事か、経済が大事かといった無意義な議論もありました。
これはどちらも大事で比べること事態がおかしいのです。
コロナで亡くなる人を減らすためにとして、社会経済活動を止めれば、失業者があふれます。それにともなう自殺者や事件も増えます。
両者のバランスをとっていくことしかないのが現実でしょう。
今回政府の緊急事態宣言が発令されませんでしたが、都道府県独自で宣言発令したところがいくつかあります。
東京都は東京アラートが出されました。
愛知県は8月6日から24日まで県独自の緊張事態宣言中です。
沖縄県は8月1日から29日までの県独自の緊張事態宣言中です。
その他の県でも独自の宣言を出したようです。
これらも検証が必要だと思います。
2020/8/21 NHKニュースWEBより
21日行われた新型コロナウイルス対策の政府の分科会では、感染状況について、最新の分析結果が報告され、専門家は、全国的には今回の感染拡大はピークに達したと考えられるものの、再び増加するおそれがあり引き続き注意が必要だと指摘しました。
全国的には7月下旬がピーク 再び増加の可能性に引き続き注意を
これは会合のあとの会見で分科会の尾身茂会長や分科会のメンバーで東北大学の押谷仁教授らが明らかにしました。
各自治体では新たに感染が確認された人の数を毎日、発表していますが、検査の実施状況などの影響を受けるため感染状況を正確に分析するには、発症した日ごとのデータが重要となります。
21日の会合では最新の発症日ごとのデータが示されました。
それによりますと全国的には、今回の感染拡大で7月27日から29日にかけて発症者数がピークとなり、その後、緩やかに下降傾向になっていて、一部地域では新たな感染者の数が減少傾向にあるとみられるということです。
都道府県別では、東京都や大阪府、それに愛知県などでは、7月末ごろがピークとなっていた可能性があるほか、福岡県や沖縄県などでも8月中旬にかけてゆっくりと減少傾向が見られたということです。
一方で、お盆の時期などの状況についてまだ分析できるデータが無いことやピークは過ぎたように見えても高止まりの状態とみられる地域もあることなどから、この先、再び増加する可能性があるとして引き続き注意が必要だとしました。
そのうえで分科会では、3月から5月にかけての第1波の際には流行の後期に高齢者施設や医療機関などの施設内で感染が増える傾向があったことや大阪府や沖縄県、愛知県、それに福岡県などで重症者の数が増加傾向にあることなどからマスクの着用や手洗い、それに3密を避けるなどの感染対策を引き続き徹底する必要があるとしています。
会見で東北大学の押谷教授は、「大きな集団感染がどこかで起きれば感染が再び拡大することも十分考えられる状況だ。高齢者施設や医療機関で感染が広がると重症者や死亡者が増えるおそれがある。患者数の推移でピークが見えたとしても、重症者の数や医療機関のひっ迫の問題は全く別の話だと捉える必要があり引き続き注意が必要だ」と話していました。
尾身会長「ワクチン 必要な数の確保目指すのが重要」
21日の分科会では、新型コロナウイルスに対するワクチンが実用化された場合に重症化するリスクの高い高齢者や持病のある人、そして、医療従事者などから優先的に接種するとした方針が取りまとめられました。
会合のあとで開かれた記者会見で、分科会の尾身茂会長は、感染を予防するなど、理想的なワクチンができる可能性は必ずしも保証されていないものの感染拡大に伴って期待が高まっているという認識を示しました。
そのうえで、「国としてワクチンの確保に全力で取り組んでもらうとともに、海外からの購入については安全性や有効性が明確になっていない時点で判断しないといけない。安全性や有効性が全部分かってからでは遅いのですべて使用されなくても必要な数の確保を目指すのが重要だ」と述べ、早い段階から国としてワクチンの確保を進める必要性を強調しました。
また、尾身会長は、「日本はワクチンの副作用に対する国民の関心が諸外国に比べて高いということもあり、ワクチンがなかなか普及しなかった歴史もある。どこまで効果があるのか、どんな副作用があるのかなど分かった時点で速やかに透明性をもって情報を国民に伝えることが専門家の責務だと思う」と述べ正確な情報を発信することが重要だという認識を示しました。
尾身会長「重症者 国への報告は統一指標で」
新型コロナウイルスの重症者について、国の基準と東京都などの一部の自治体が異なる基準で集計していることについて、政府の分科会の尾身茂会長は「自治体によっては、地域の実情に合わせた対策を考えるうえで、より現実的な指標として独自の基準を使いたいという思いがあり、それ自体は尊重すべきだ。ただ、全国的な感染状況を評価するためには、国に対して報告する際には統一した指標を使ってもらったほうがより便利だ」と話しました。